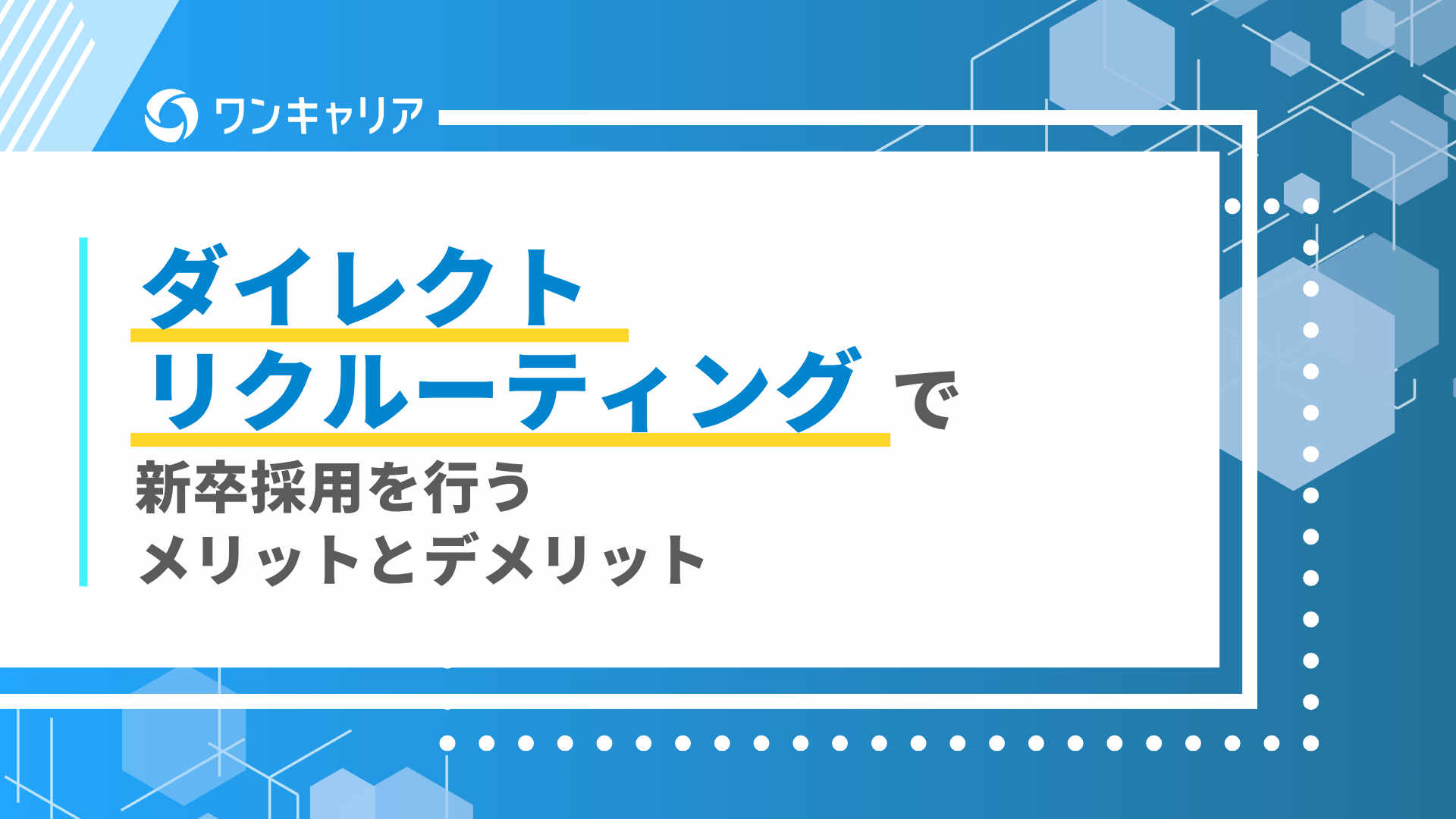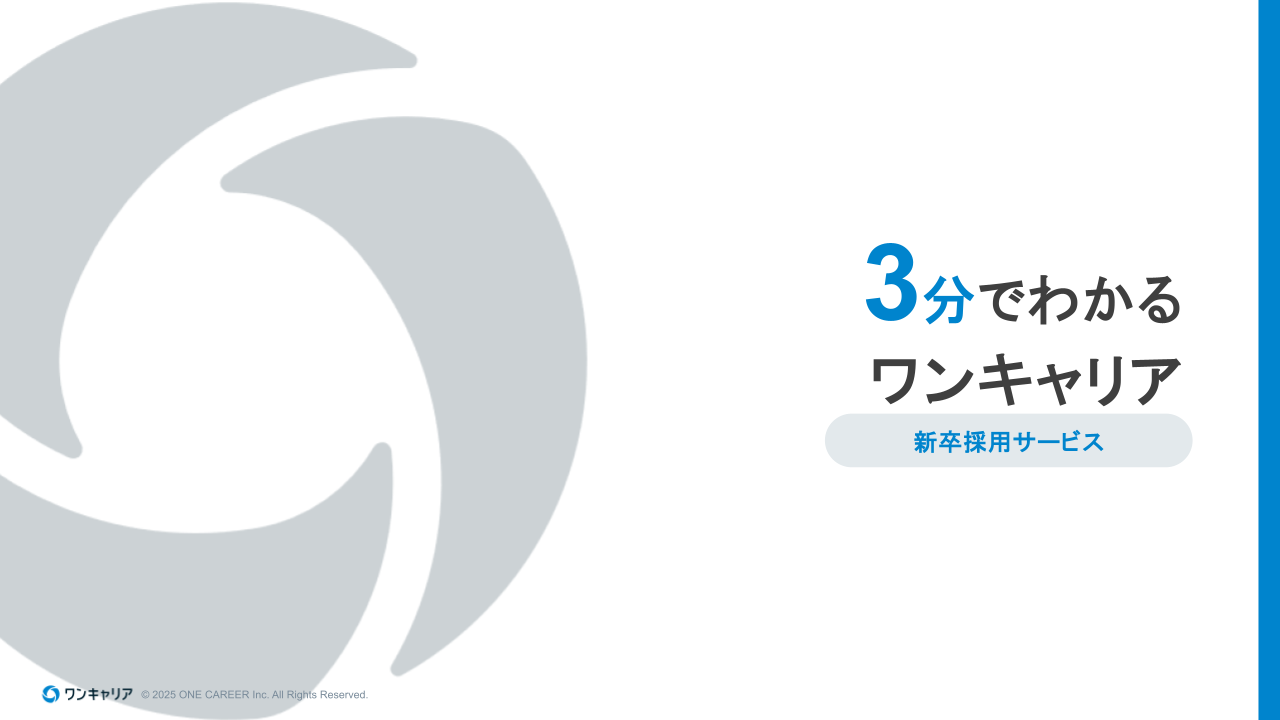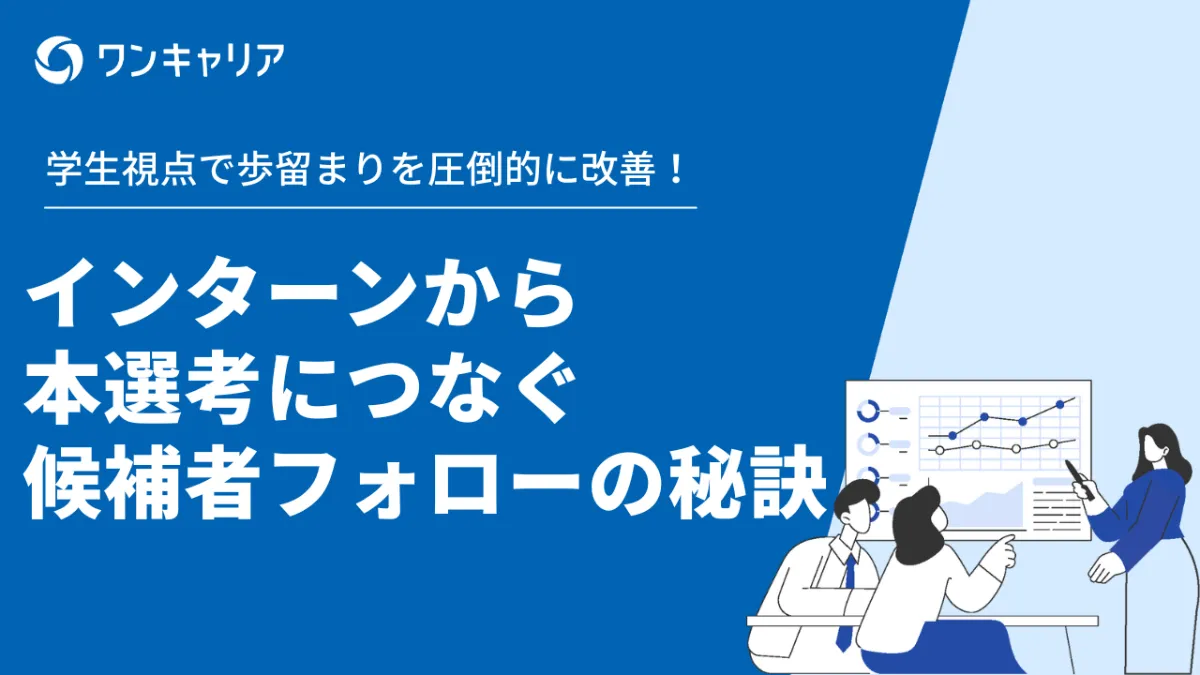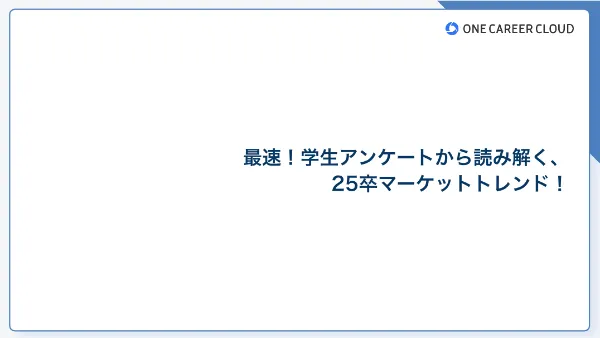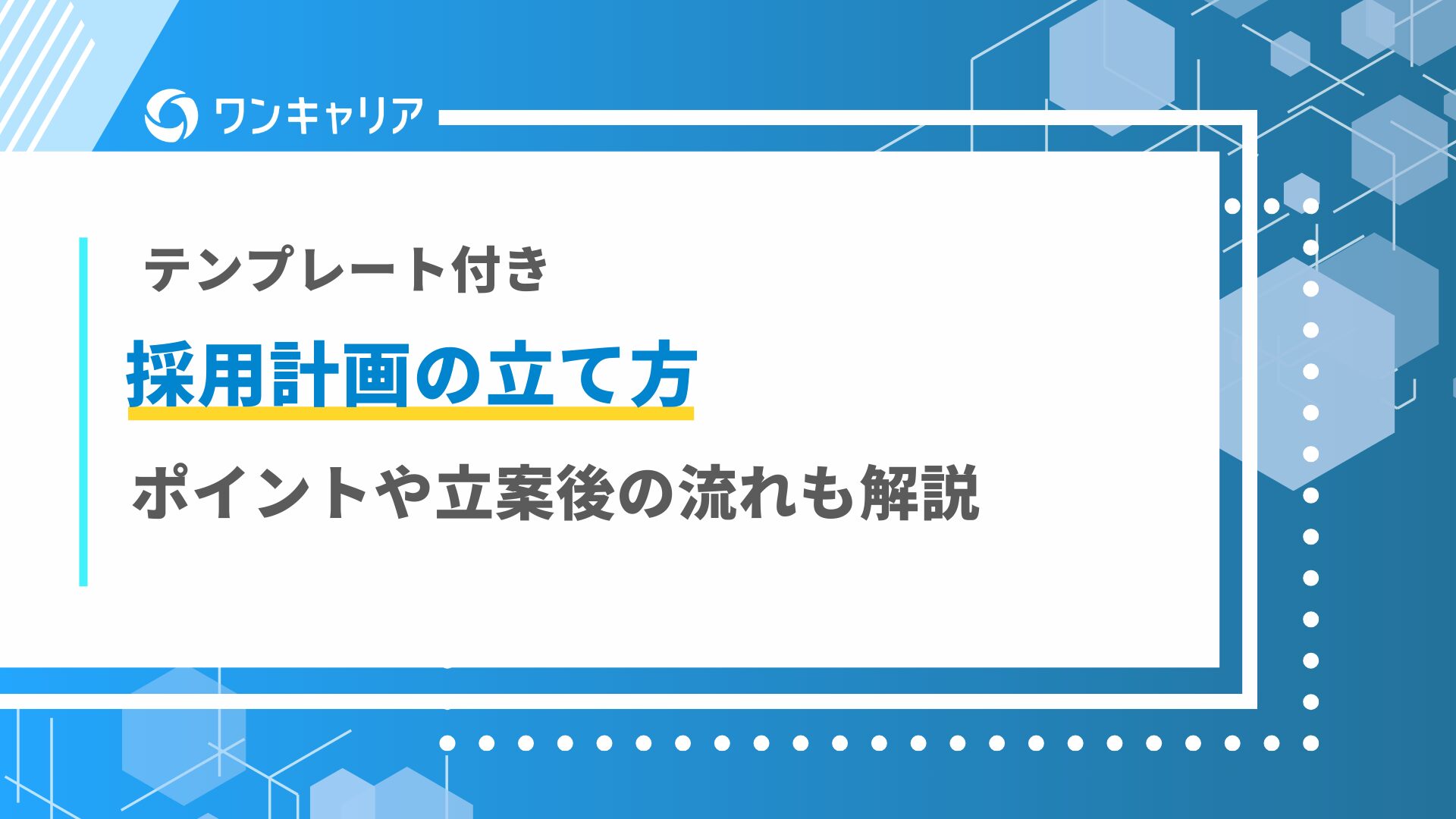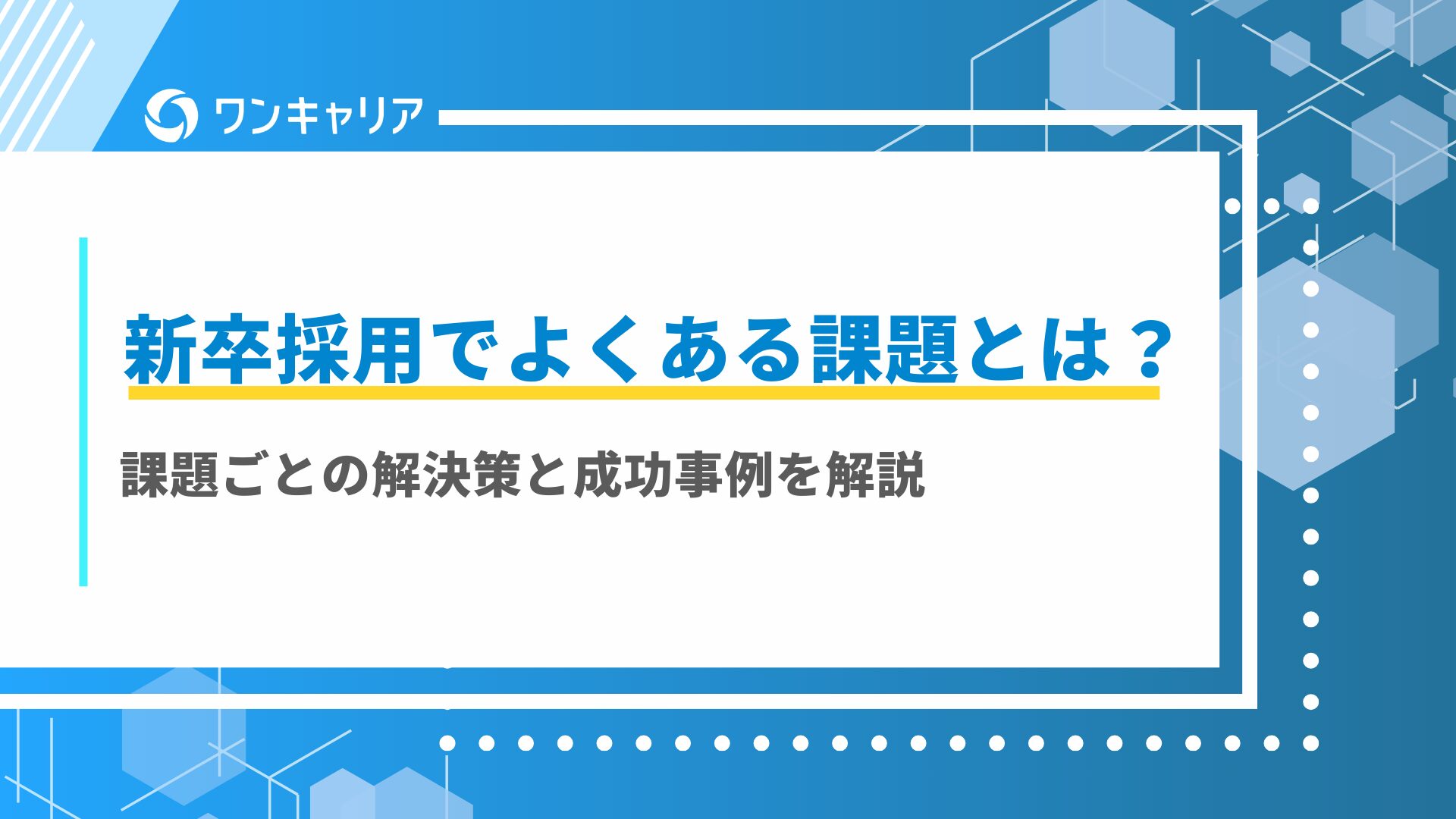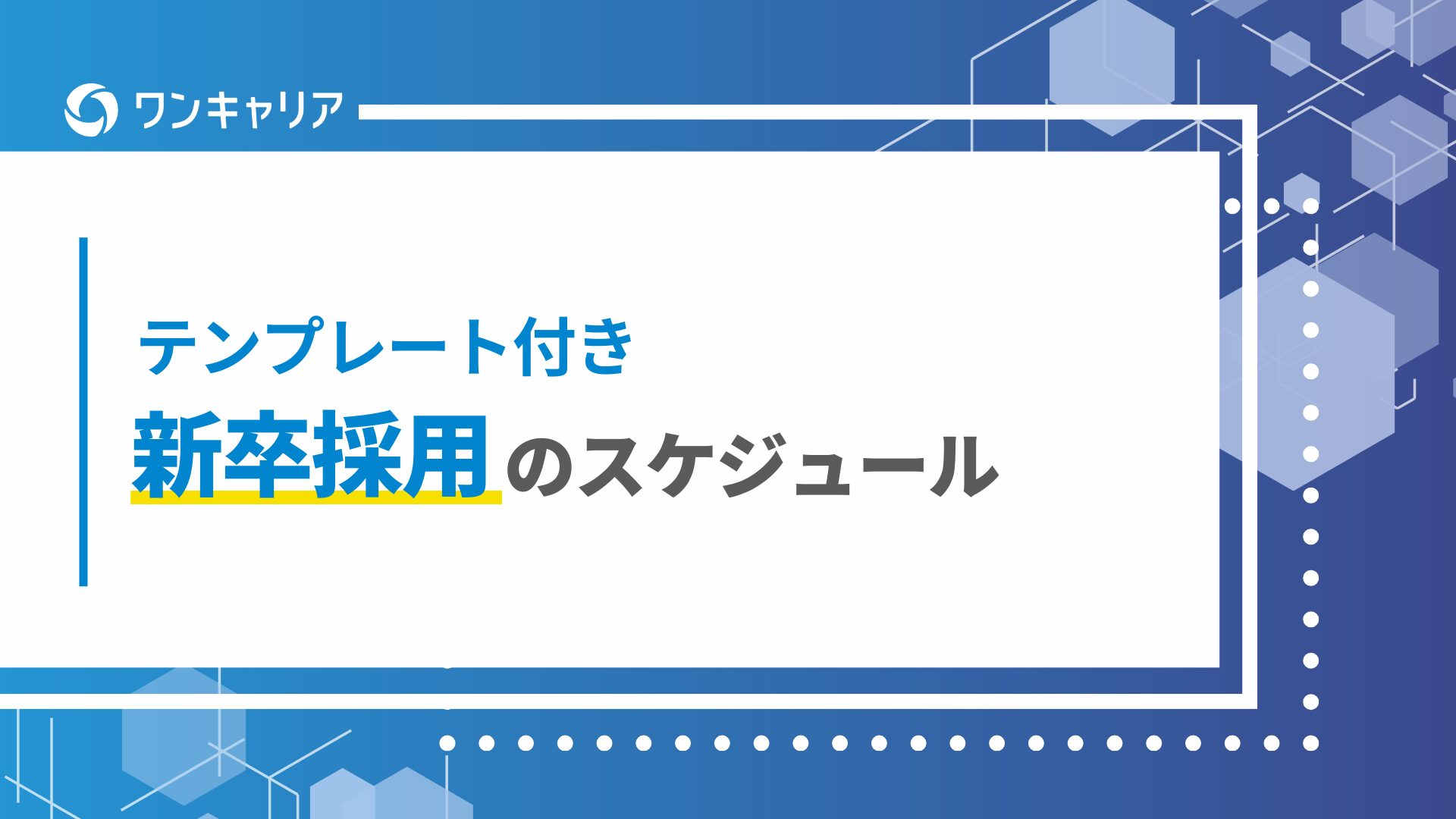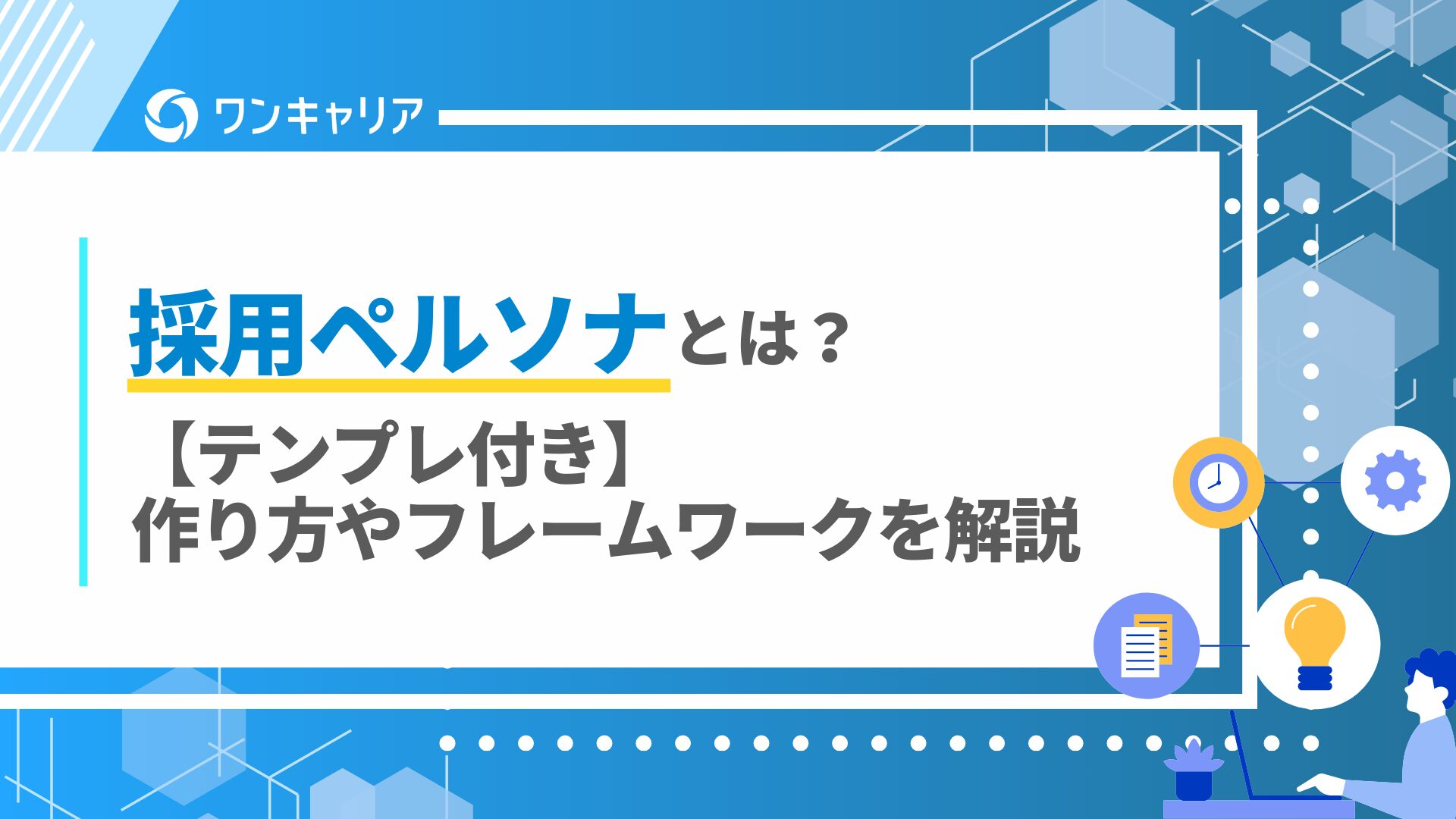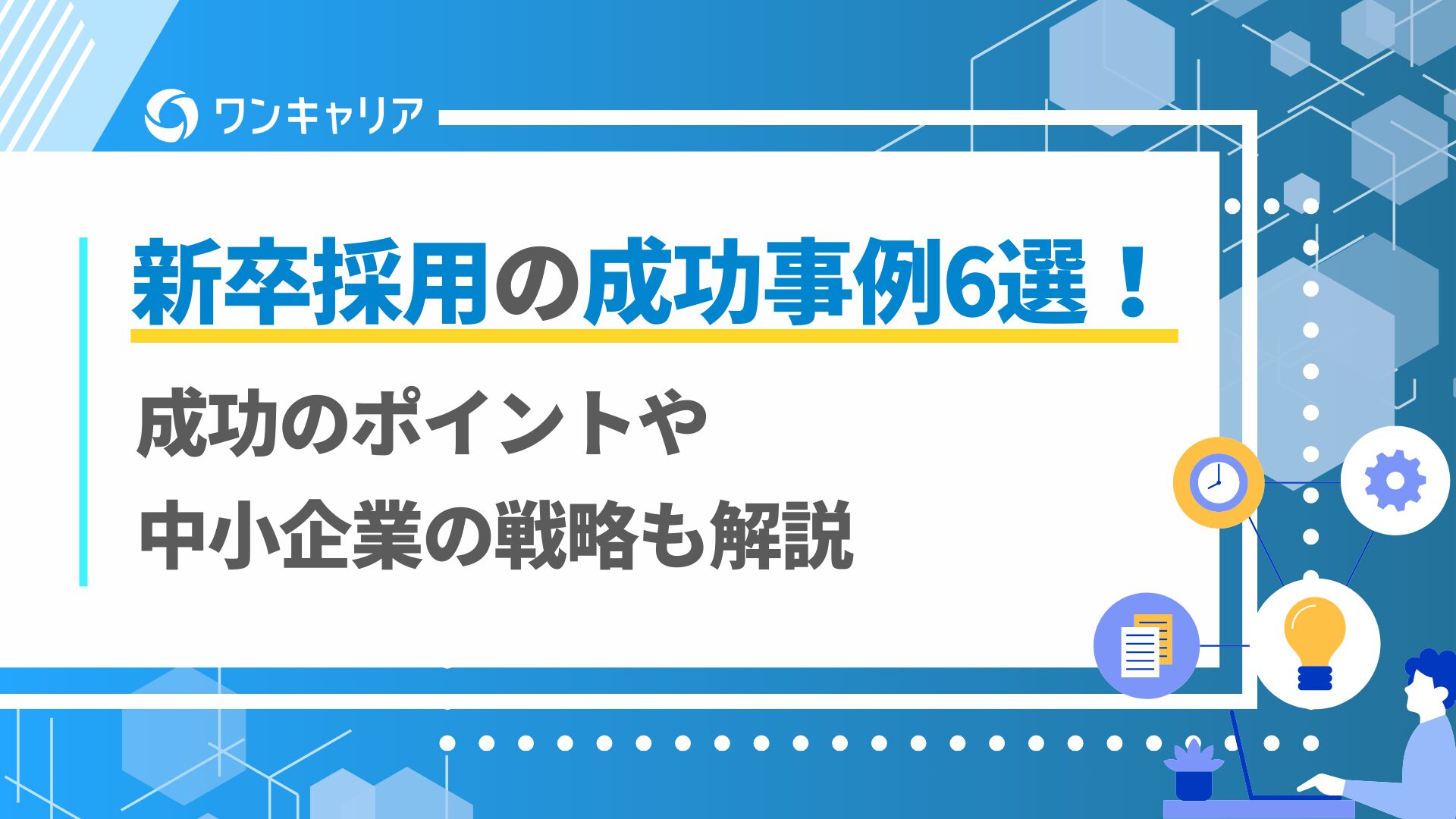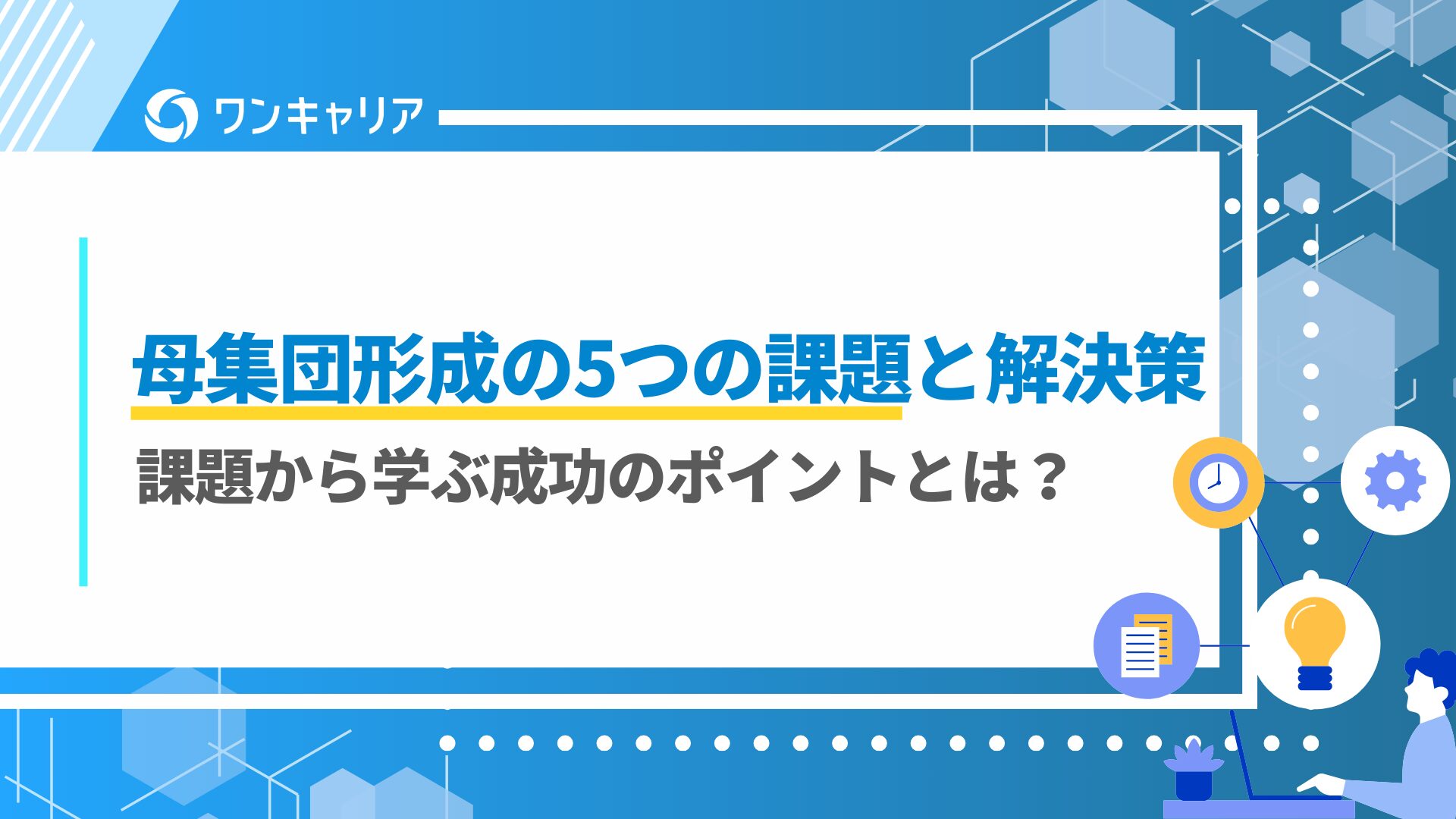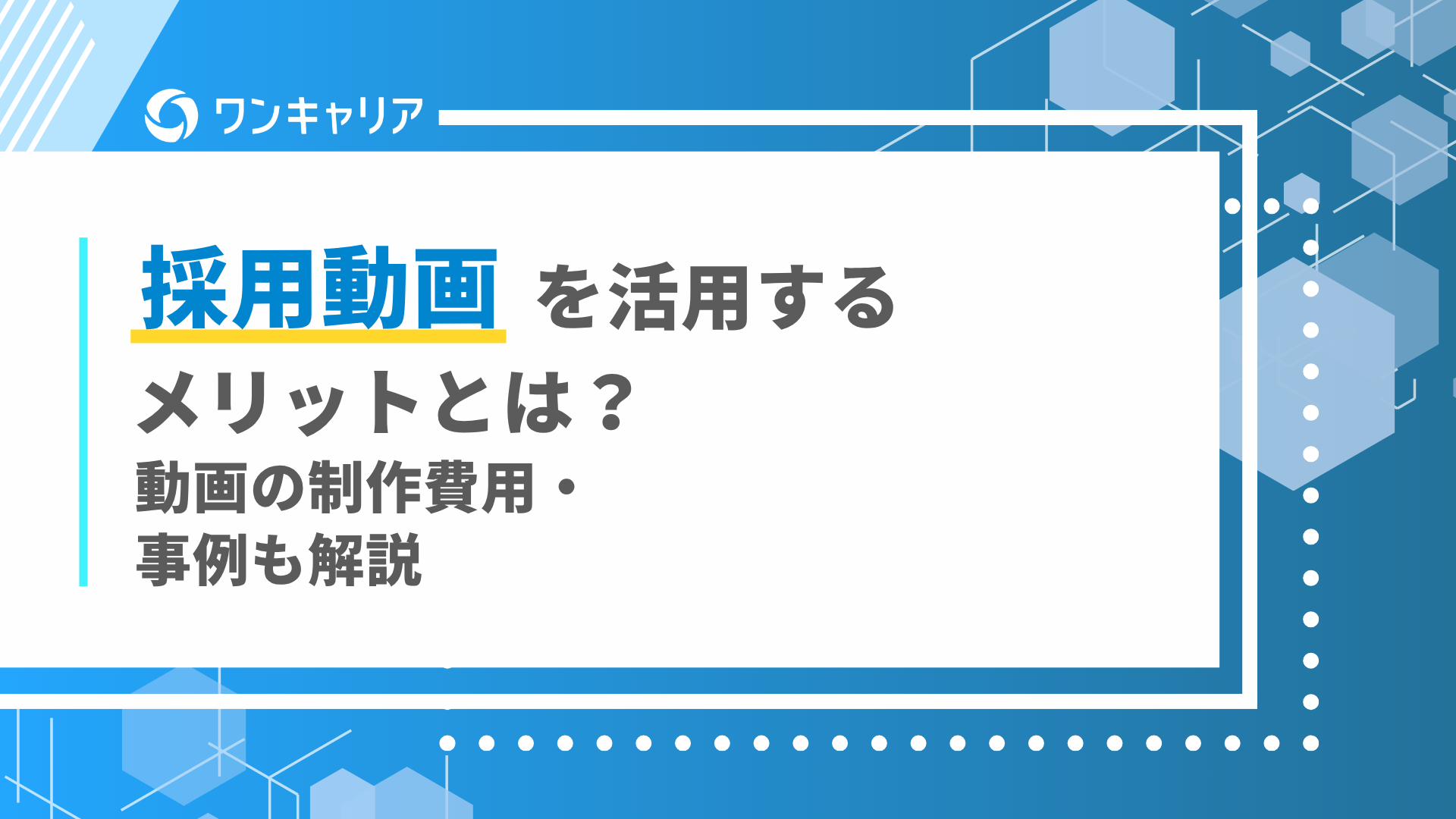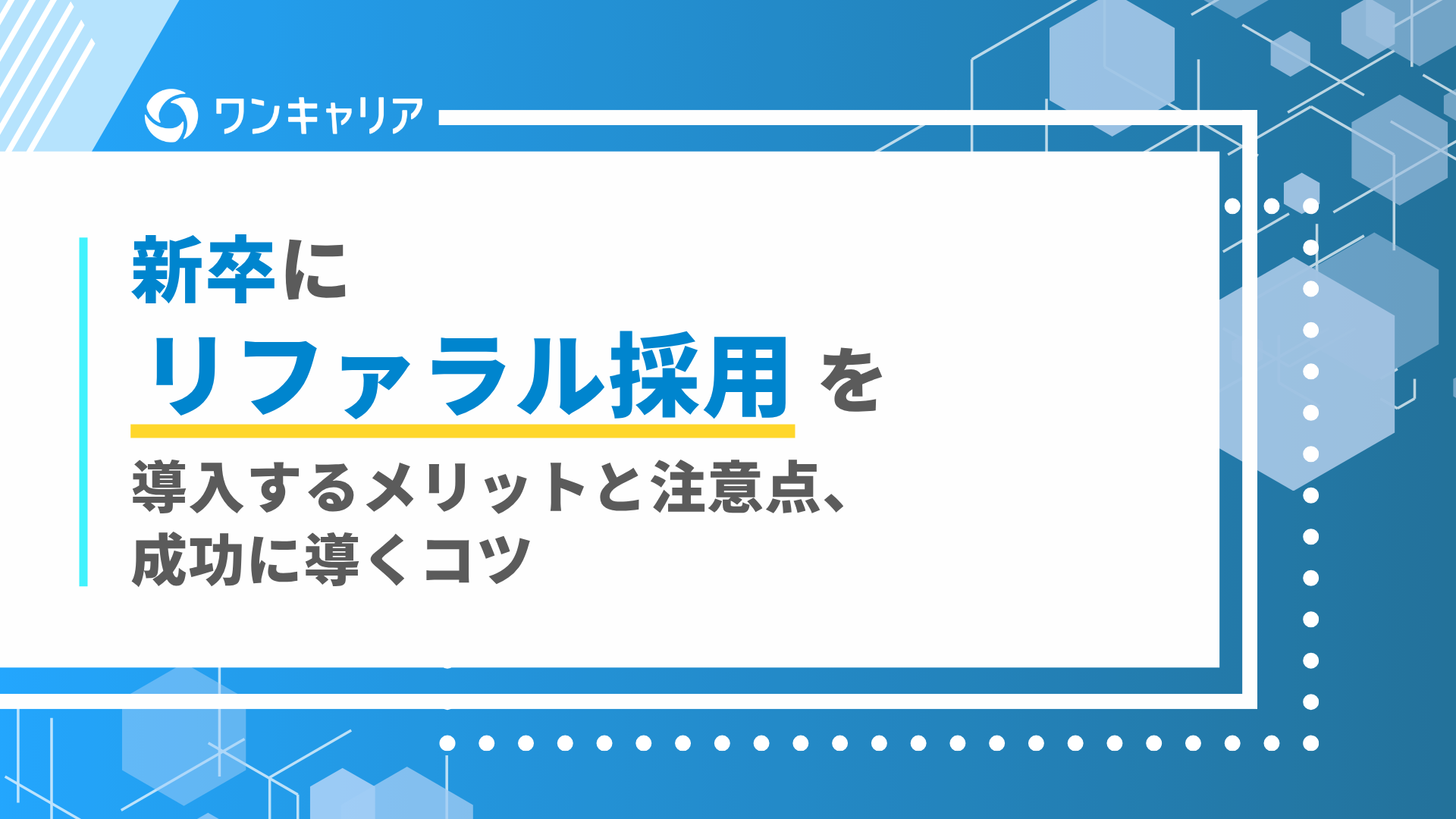目次
近年、少子高齢化などの影響で人手不足はいっそう深刻化しています。特に新卒採用は「売り手市場」といわれており、優秀な学生の多くは大手を目指す傾向にあるため、中小企業などは人材の確保が難しい状況だとされています。 そのため、各企業の人事担当者は就活生に興味を持ってもらうための工夫を凝らすのはもちろん、能力・スキルの高い学生に自らアプローチする「ダイレクトリクルーティング」を取り入れることをおすすめします。そこで本記事では、ダイレクトリクルーティングの活用方法や、新卒採用を行うメリットとデメリットについて解説します。
新卒採用でダイレクトリクルーティングは有効?
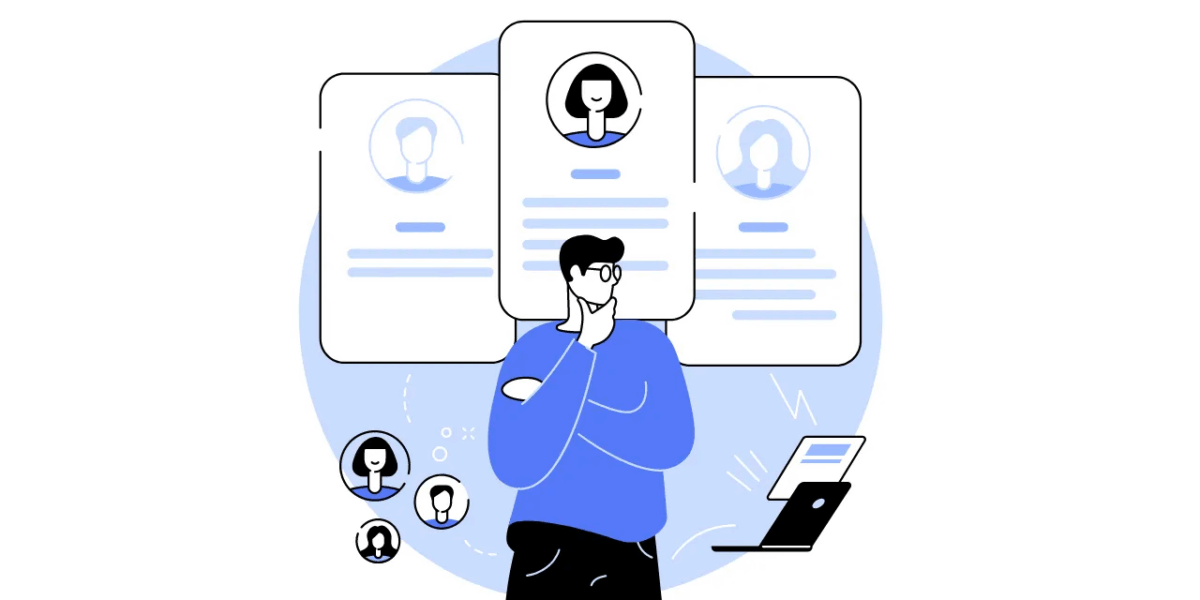
はじめにダイレクトリクルーティングの特徴や有効性、実際に行う場合の流れなどを解説します。
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、企業が直接、求職者(見込みを含む)にアプローチする採用手法のことです。
求人広告や人材紹介サービスといった仲介会社を通さず、企業から積極的にコンタクトを図る「攻め」の採用活動であり、近年では中途採用だけでなく、新卒向けの採用で導入を検討する企業が増えています。
新卒採用にダイレクトリクルーティングを取り入れる場合は、既存の採用手法も行いつつ、新たな採用戦略として用いるのが一般的です。なお、ダイレクトリクルーティングの手法は複数の種類があるため、自社に適した方法を見極め、単独もしくは組み合わせて活用することが成功のポイントといえます。
主な手法3種類を以下で紹介します。
ソーシャルリクルーティング(SNSの活用)
FacebookやTwitterなどのSNSを活用し、求職者と企業を結びつける新しい採用手法のことです。応募者が応募し、企業が選考する従来の採用活動とは異なり、ソーシャルリクルーティングでは、両者の信頼関係を築くことが重要視されます。これにより、より多くの人にアプローチでき、採用活動の効率化が図れます。
リアルイベントの実施
セミナー、説明会、交流会などを通して学生の情報を収集し、実施後に直接アプローチする方法です。
就活生向けの企業説明会だけでなく、キャリア相談会、業界説明会などさまざまな切り口が考えられます。
スカウトサービスの利用
企業が求職者へスカウトメールを送る手法です。ソーシャルリクルーティングと同様、直接採用したい求職者へアプローチできます。
従来のスカウトサービスでもスカウトメールは活用されていましたが、求人サイトのシステムを利用して条件に合う求職者にメールを一括送信する方法が一般的でした。一方、ダイレクトリクルーティングにおけるスカウトメールでは、企業がマッチする人材へ直接メッセージを送るため、ミスマッチが少ないメリットがあります。
ダイレクトリクルーティングによる新卒採用に注目が集まる背景

近年、少子高齢化の影響により新卒学生の数が減少していることは、多くの方がご存知でしょう。新卒学生数が少ない状況では、従来の新卒一括採用で用いられてきた「待ちの手法」だけでは、目標とする人材の確保が難しいのが現実です。
そのため、就活の早期化により、選考より前のタイミングで企業側が学生にアプローチするなど、攻めの採用の必要性が増加したといえます。
また、近年はSNSの普及などにより、企業側から情報発信やコンタクトをしやすい環境になっているほか、コロナ禍によってオンライン化が普及し、Webを活用した就活・採用活動が進むなど、ダイレクトリクルーティングに適した環境に変化していることも、魅力が高まっている理由といえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングの流れ
リサーチしてターゲットをまとめる
まずは採用したい人材のイメージを固めたうで、ダイレクトリクルーティングのターゲットとなる人を見つけるためリサーチを開始します。リサーチの手段としては、SNSのほか、ダイレクトリクルーティングの専用サービスの活用が効果的です。
専用サービスを使えば就職活動をしている方のプロフィール、キャリア・経験などの詳細をチェックした後にアプローチできるうえ、運営会社の充実したサポートも受けられます。
そのため、ピンポイントで採用したい人材を見つけやすくなるでしょう。
学生にコンタクトを図る
次にスカウトメールなどを送り、採用したい学生と直接コンタクトを図ります。スカウトメールは複数の学生に送る可能性が高いため、前もって文章を作成しておきましょう。スカウトをした理由や自社の魅力を端的に伝えることがコツです。
ターゲットとのコミュニケーションと折衝を図る
ターゲットとのコミュニケーションを取る際は、メールやチャットによる連絡だけでなく、採用担当者が実際に学生の通うキャンパスの付近まで赴き、会社案内の資料説明をするなど対面で話をするとより気持ちが伝わりやすいでしょう。
また、学生側の緊張をほぐすため、まずは相談ベースで話をすることをおすすめします。
選考、面接を実施する
スカウトメールなどを通して接点を持った学生から前向きな返答があれば、できるだけ早めに日程調整を行い、面談の日時を決定するようにしましょう。従来の採用手法と異なり、ダイレクトリクルーティングは求職者の本心をヒアリングしやすいです。
相手の現状や希望を聞き取りながら自社の魅力をアピールして、入社後のイメージを膨らませてもらいましょう。
新卒採用におけるダイレクトリクルーティングのメリット
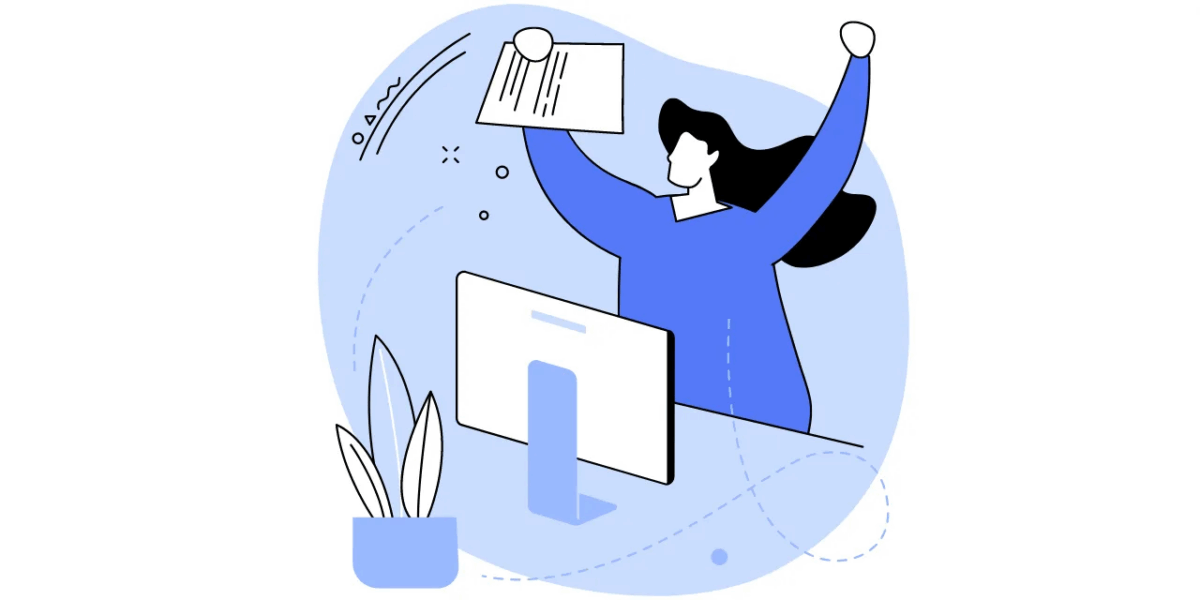
企業が新卒採用でダイレクトリクルーティングを取り入れた場合、具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。
優良な母集団形成を実現できる
ダイレクトリクルーティングのよる新卒採用には、母集団の質と量を向上できるメリットがあります。なお、新卒採用における母集団とは、自社の選考にエントリーする応募者を指します。
ダイレクトリクルーティングによる新卒採用では、企業側が求める学生に直接アプローチするため、理想の人材とのマッチング率を高められ、エントリー率の向上、早期離職の防止などにつなげられます。
また、ダイレクトリクルーティングでは、従来の手法では自社に応募してきていなかったと想定される新卒学生にもアプローチできるため、潜在層の掘り起こしが可能です。
採用コストの削減につながる
ダイレクトリクルーティングは既存の採用手法よりもコストが低くなる傾向があります。
企業が直接、求職者にアプローチすることから、求人広告の掲載費用や説明会などの出展費用を削減しやすいためです。例えばTwitterやフェイスブックなどSNSの検索から人材を見つけ、コンタクトを取り獲得できれば、コストはほとんどかからないでしょう。
ダイレクトリクルーティングサービスを活用する場合は、登録している学生を採用担当者がプロフィールやポートフォリオを見たうえでアプローチするため、ミスマッチが起こりにくく、求職者の選考や面接対応などの工数を削減できるメリットがあります。
また、ダイレクトリクルーティングサービスの料金形態は、人材データベース利用料に加えて成功報酬費が発生するケースが多くなっています。
しかし、中には初期費用、運用代行手数料が無料であり、内定時のみ成果報酬が発生する完全成功報酬型や、利用料(月額)のみがかかる定額プラン型など、さまざまな種類があります。採用人数や採用戦略に適した料金プランを選択すれば、無駄なコスト削減につながることでしょう。
自社の採用ノウハウを蓄積できる
ダイレクトリクルーティングを通して、自社に最適な採用手法、学生との接し方、PR方法などのノウハウを蓄積できます。新卒の学生とのやりとりで気付きなどを得られるためです。
そのため、自社の採用ノウハウを高めたい企業にもおすすめです。
新卒採用におけるダイレクトリクルーティングのデメリットと注意点
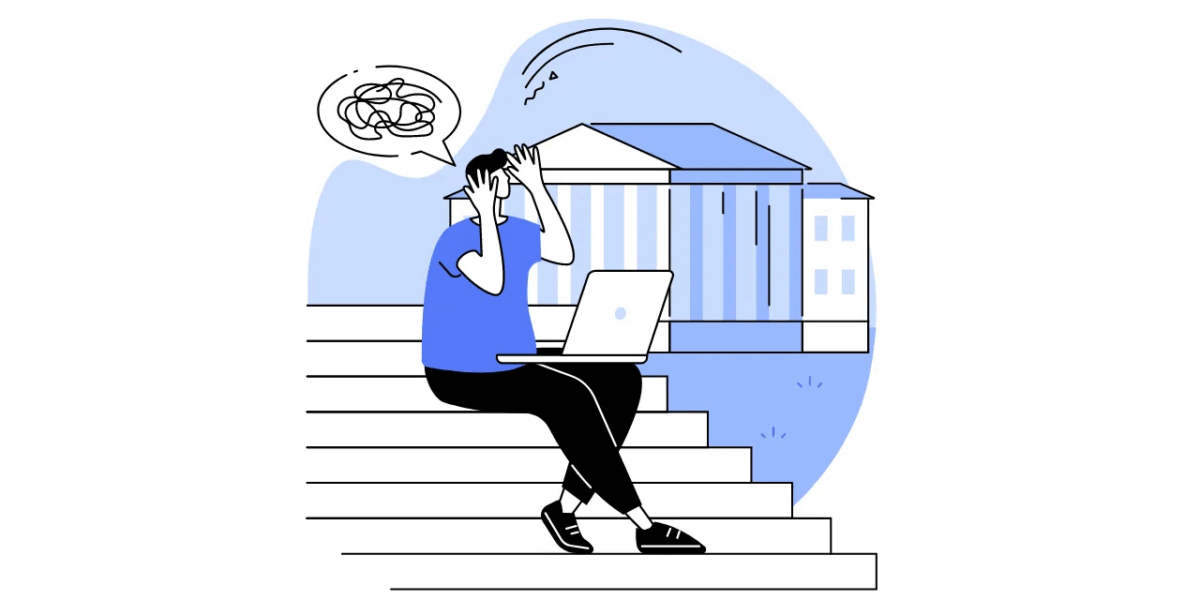
ダイレクトリクルーティングにはデメリットも少なからず存在します。特に注意すべき2点を以下に解説します。
業務の負荷が増大しやすい
通常の採用と並行する場合、ダイレクトリクルーティングが大きな負担となるおそれがあります。一人ひとりへのアプローチに特化する採用手法である関係上、リサーチ、スカウトメールの送信、候補者1人対1人とのやりとりなどの業務に手間や時間を取られるためです。
また、専門の担当者を配置することが推奨されているため、新たな人員の投入も必要になるでしょう。
効果が出るまで一定の期間が必要
ダイレクトリクルーティングの効果は、すぐには期待できません。導入当初はかかったコストのほうが得られた効果より大きいケースも考えられます。短期的な成果を求めるのではなく、長期的な採用活動と捉え、ノウハウを蓄積し、より効率的に運用できるようPDCAを回し続けることが大切です。
そのためには経営層を含む関係者の意識改善、協力体制の構築が不可欠といえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングによる新卒採用はノウハウの構築が大切

ダイレクトリクルーティングは近年注目が集まっているものの、日本ではまだ認知度が低く、新しい採用方法といえます。今後、人手不足がますます進む日本では、こうした新しい手法を有効活用できるかどうかが、人材採用の今後を左右するといっても過言ではないでしょう。
従来の採用活動との違いや仕組みを明確に理解したうえで、長期的な視点を持ち、ノウハウを蓄積することが大切です。なお、ダイレクトリクルーティングの専門サービスは多数あり、求人サイトなどと同様に幅広い業界を扱うサービスのほか、特定の業界や職種のみを扱う特化型のサービスもあります。
知名度、料金体系、登録者数などの違いも大きいため、まずはネット上の口コミを参考にしたり、直接運営会社に資料請求や問い合わせをしたりして、複数のサービス内容を確認したうえで判断するようにしましょう。