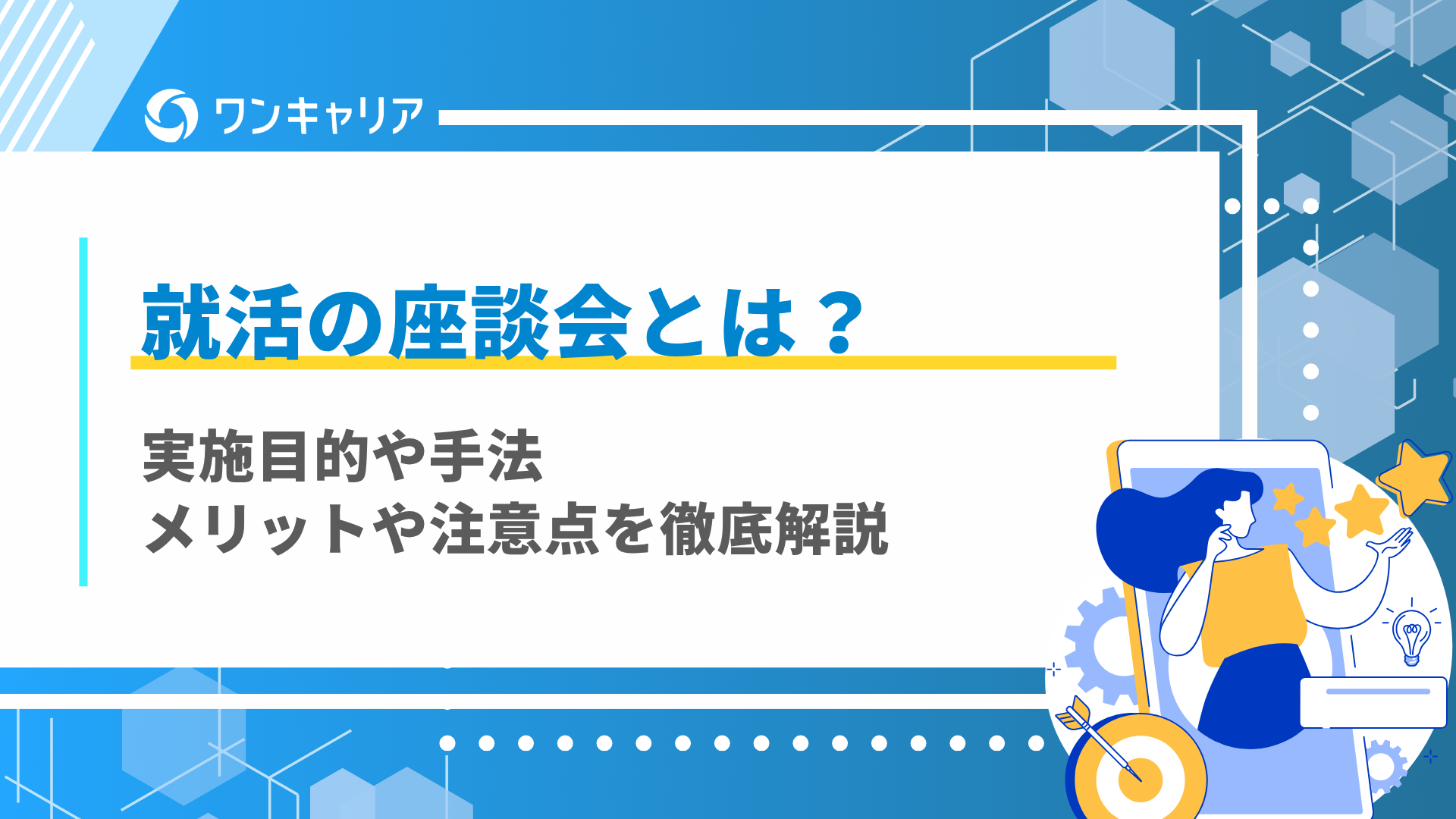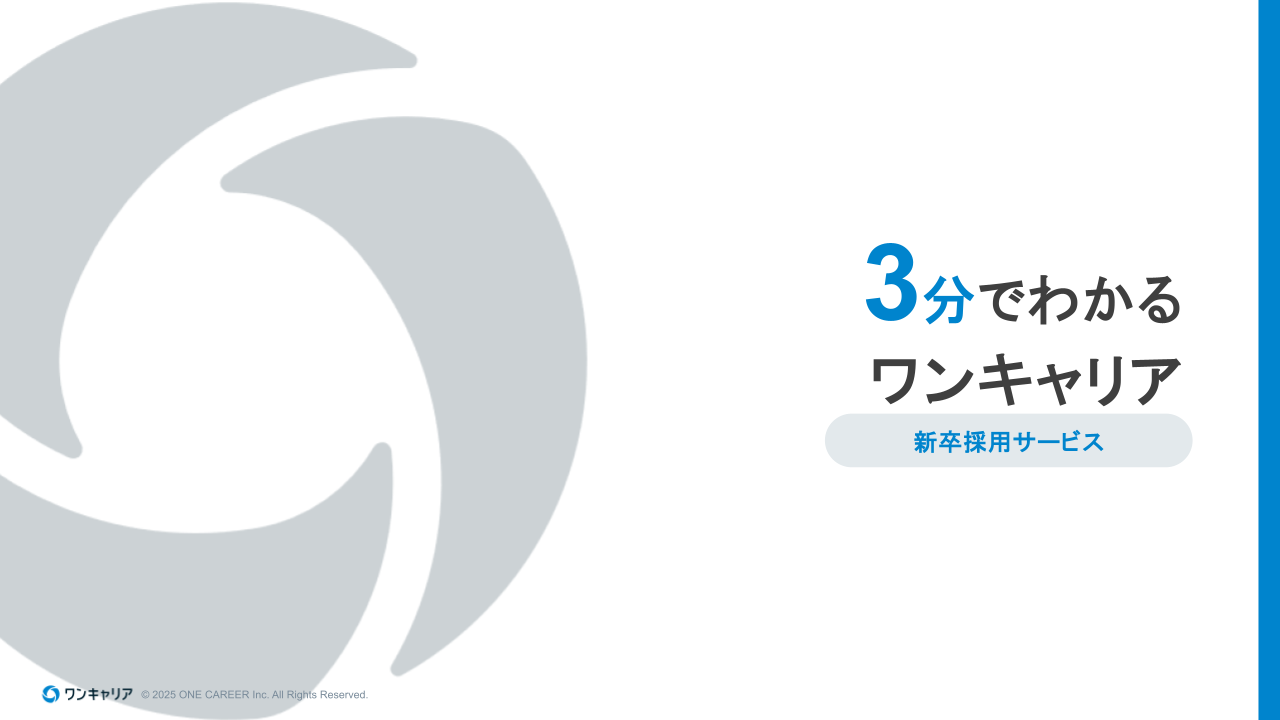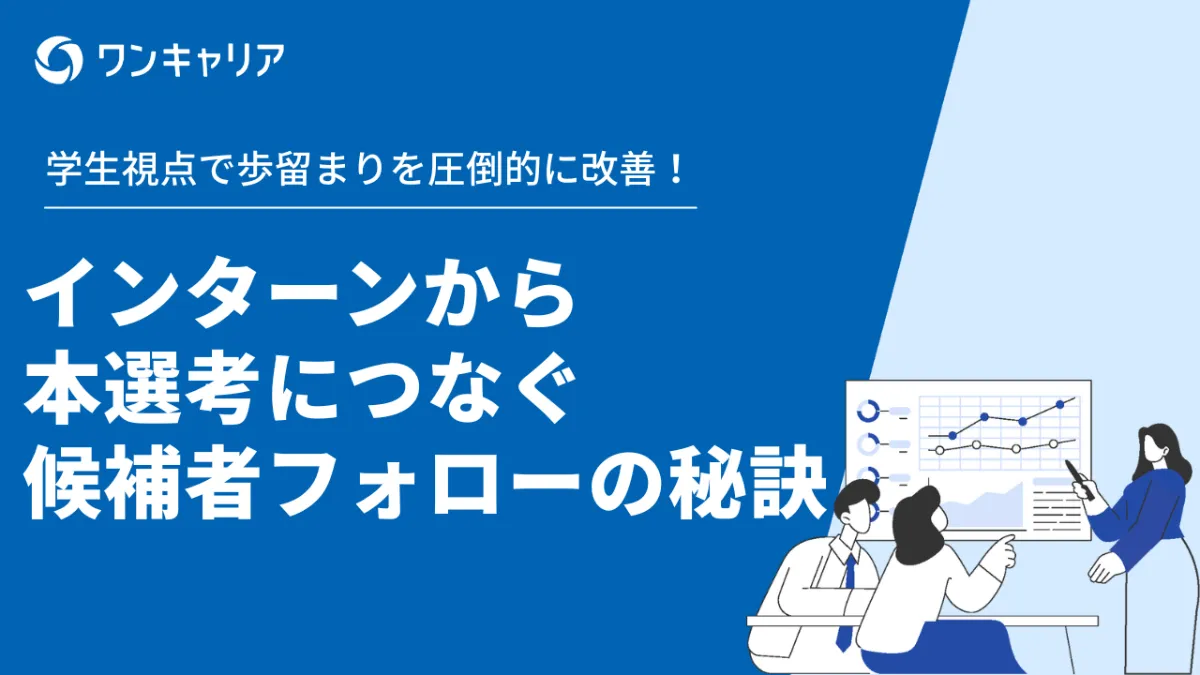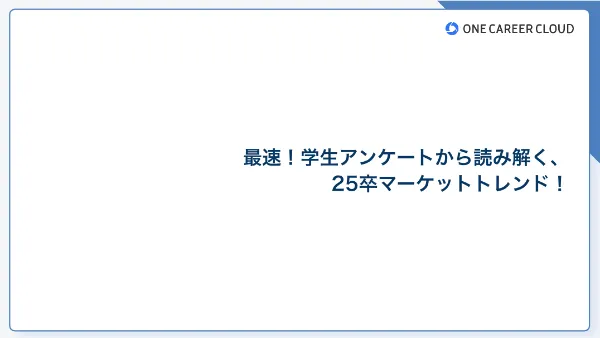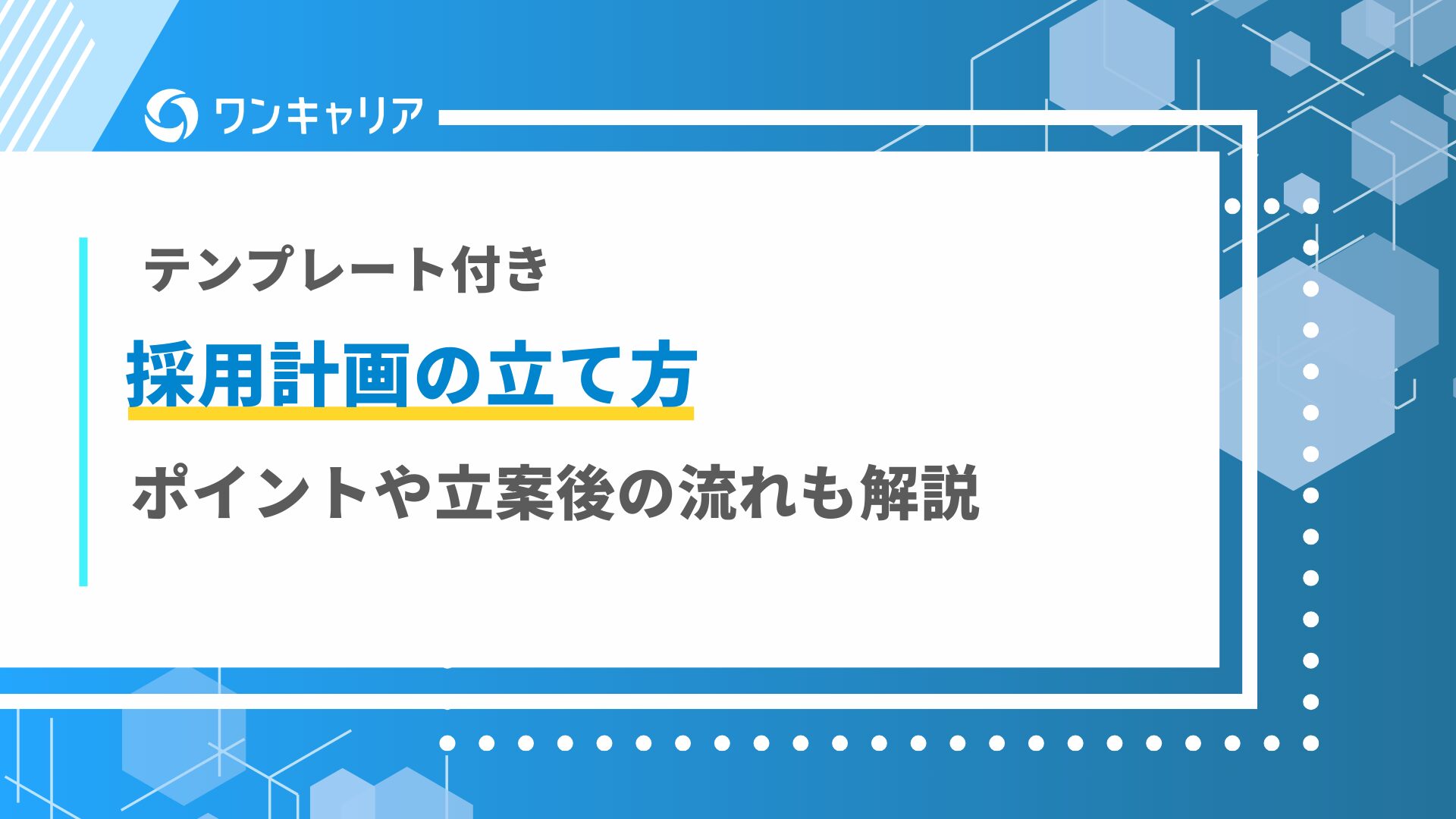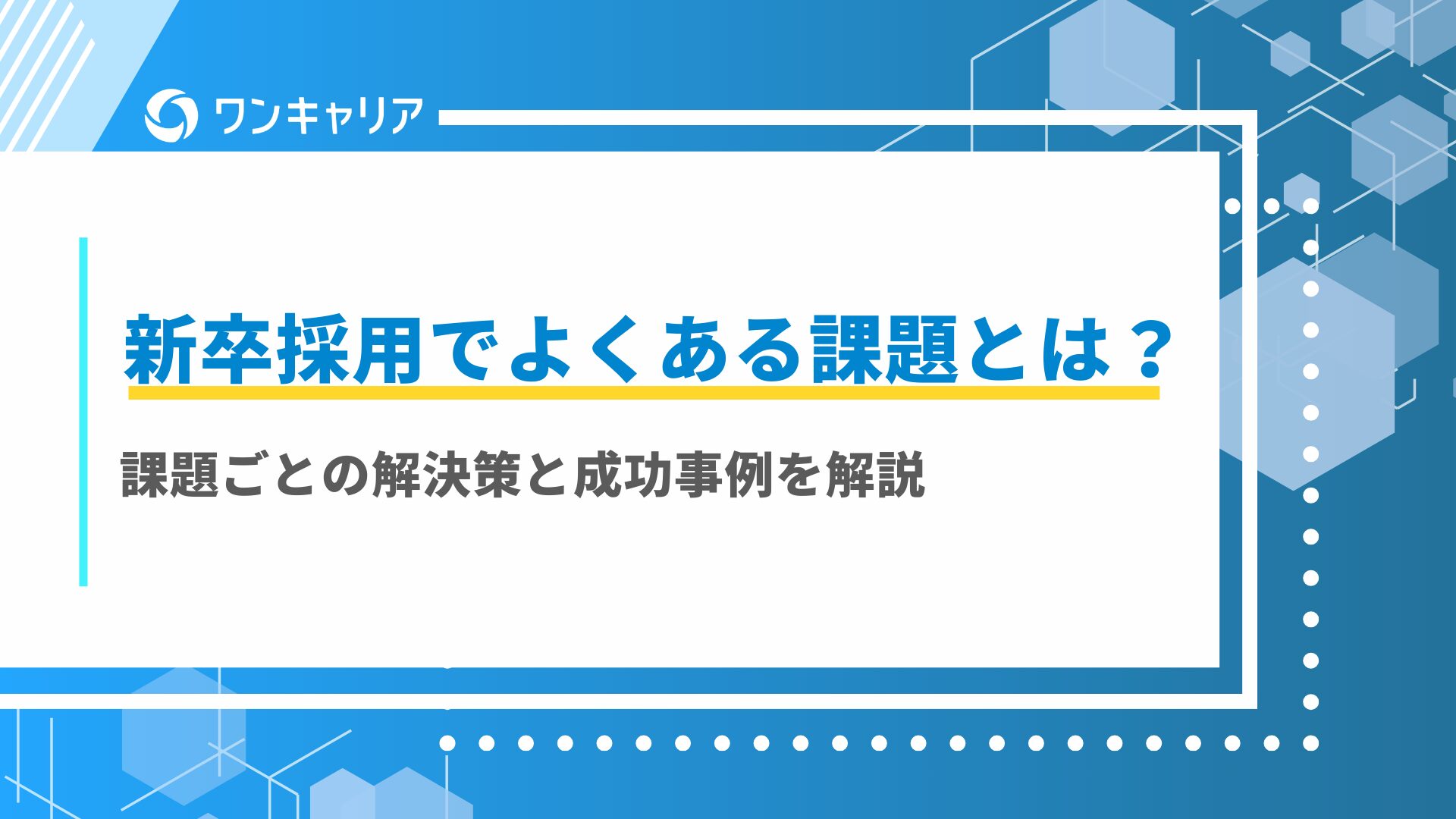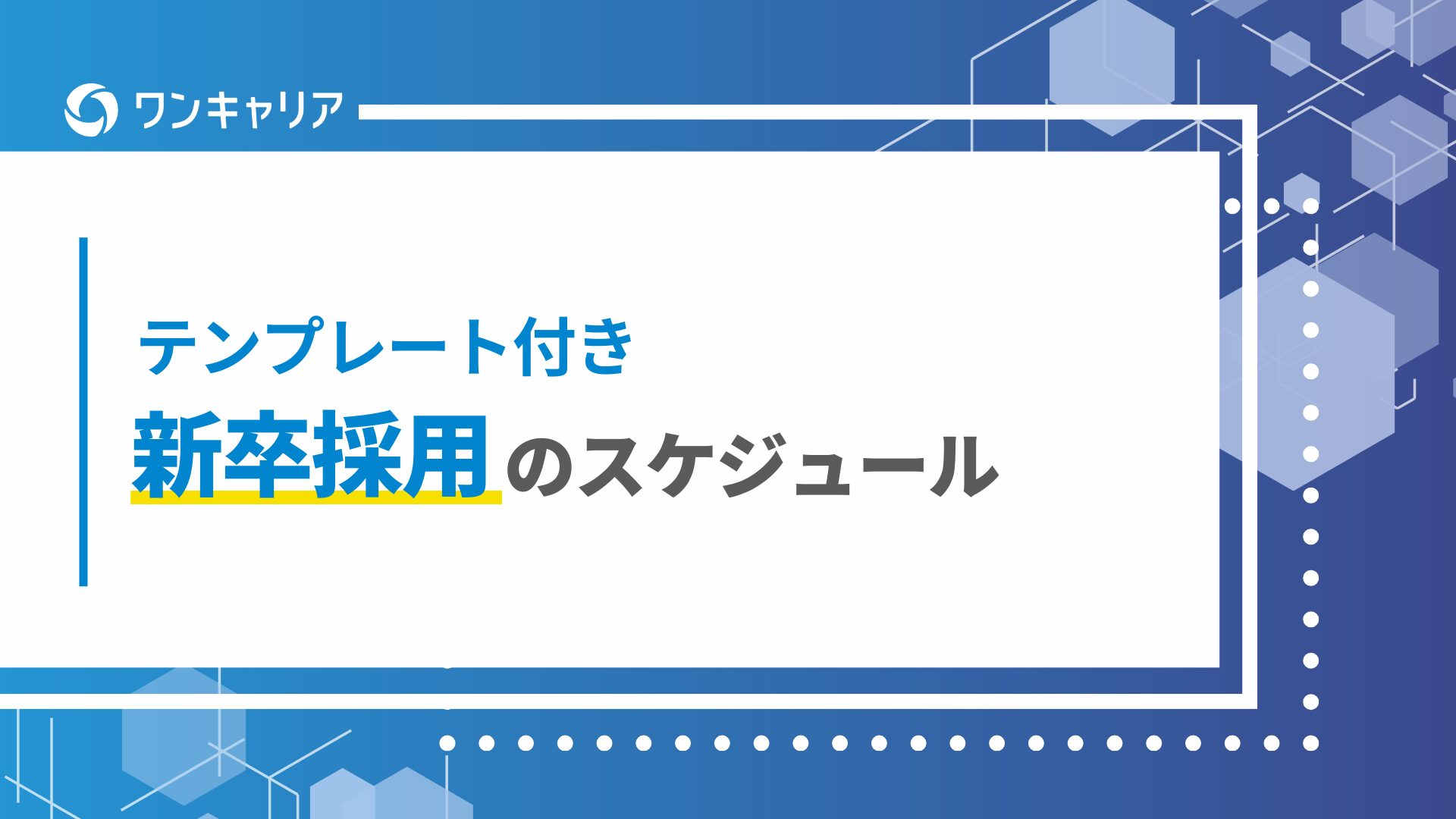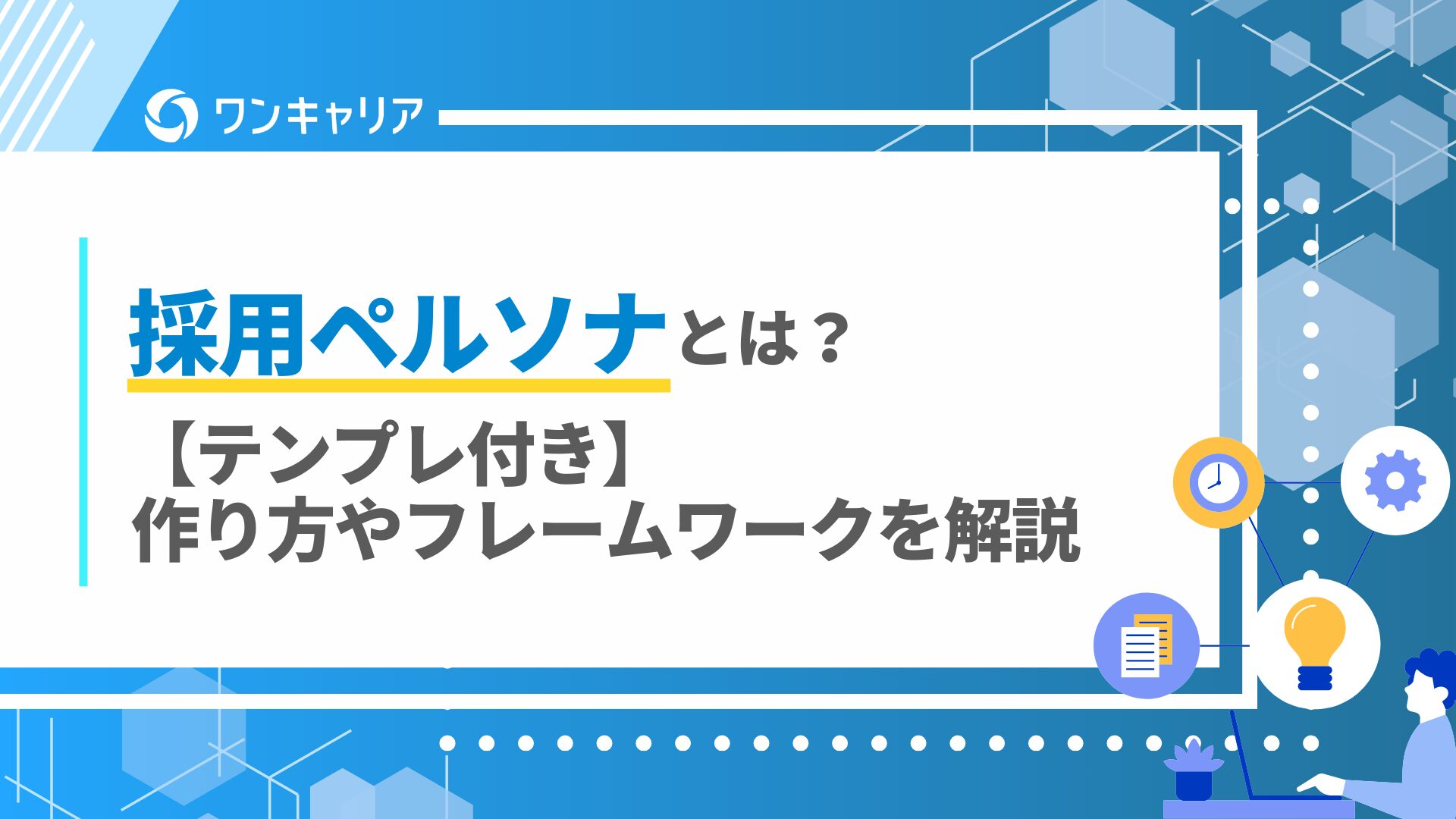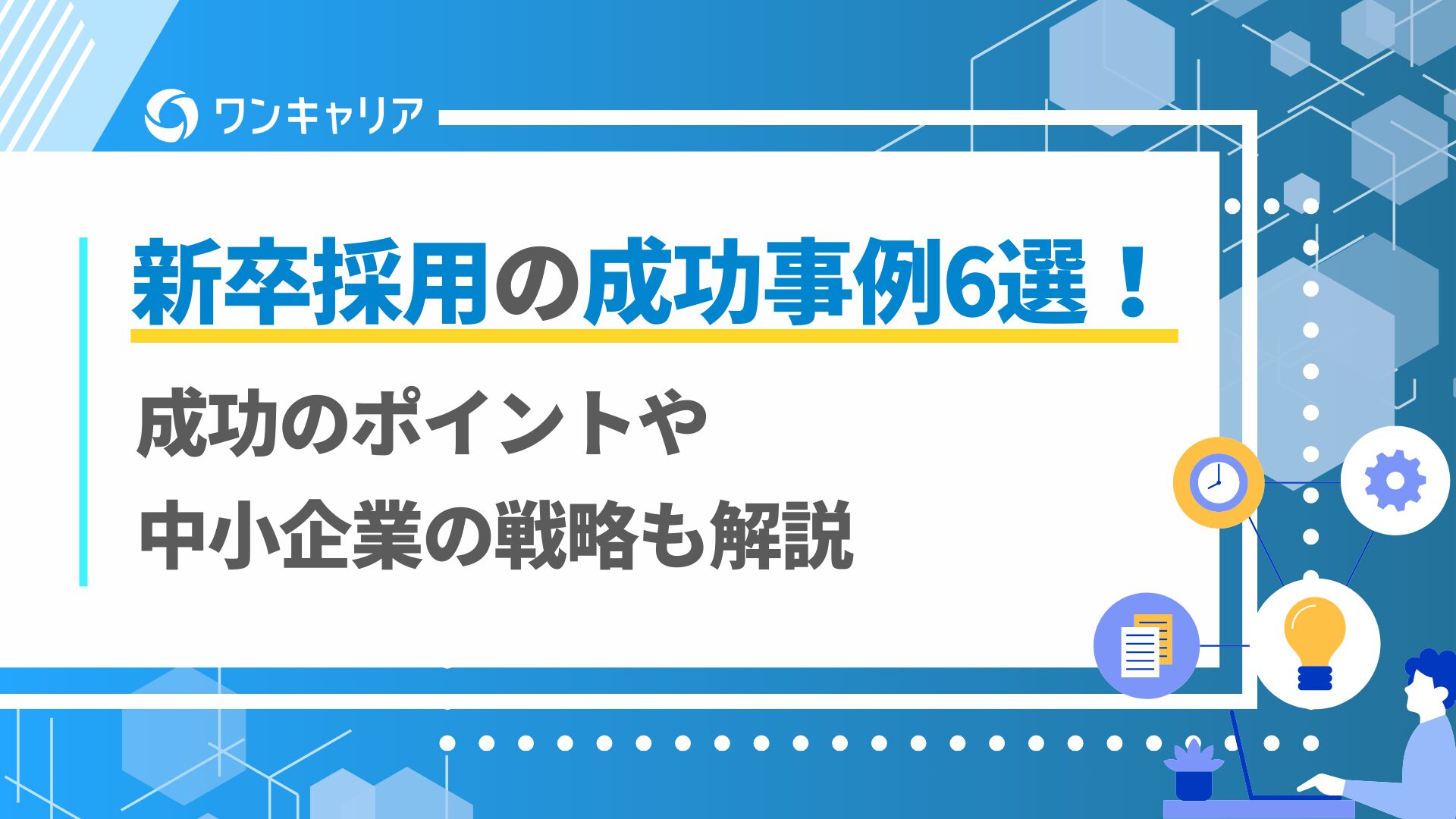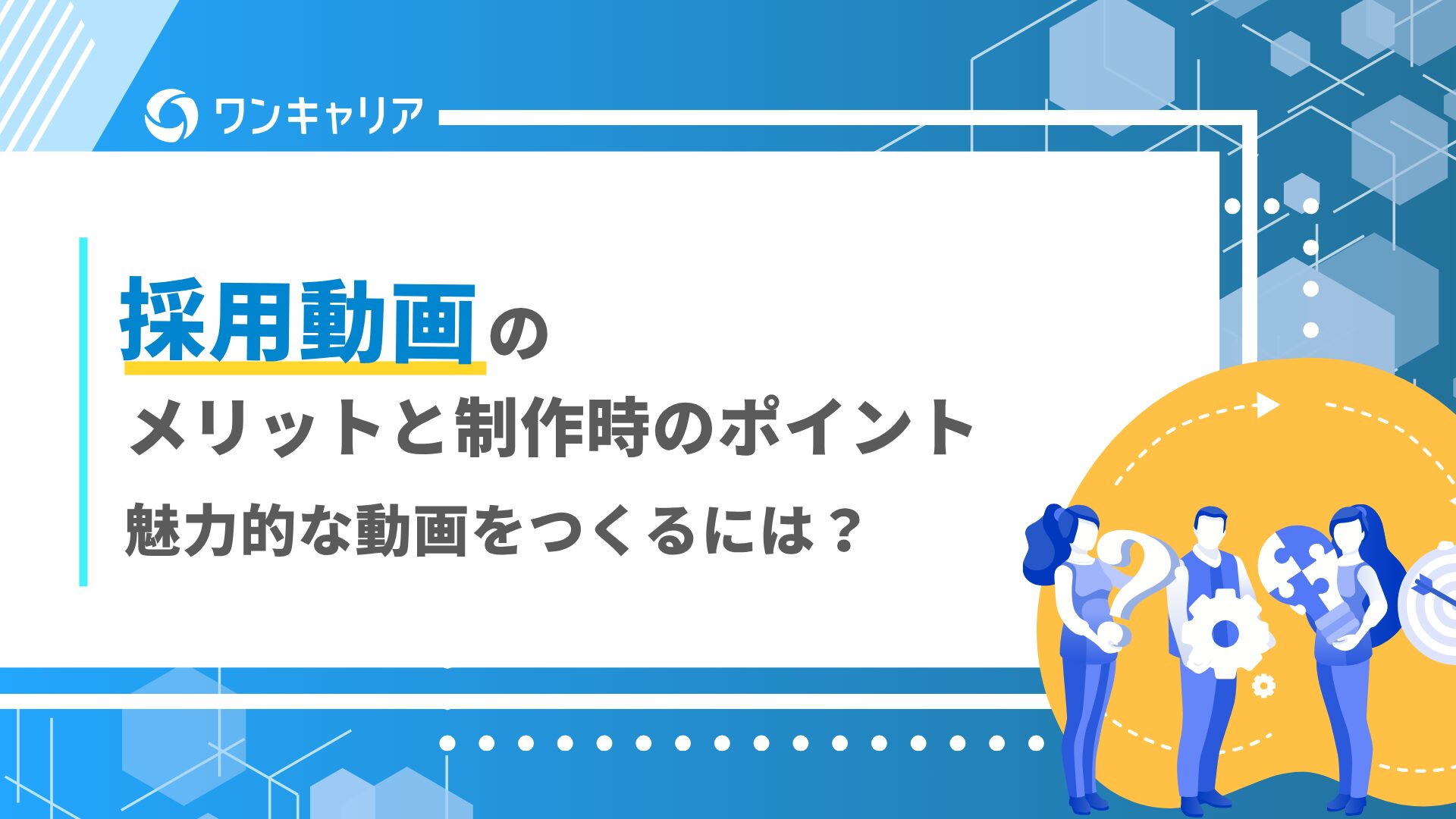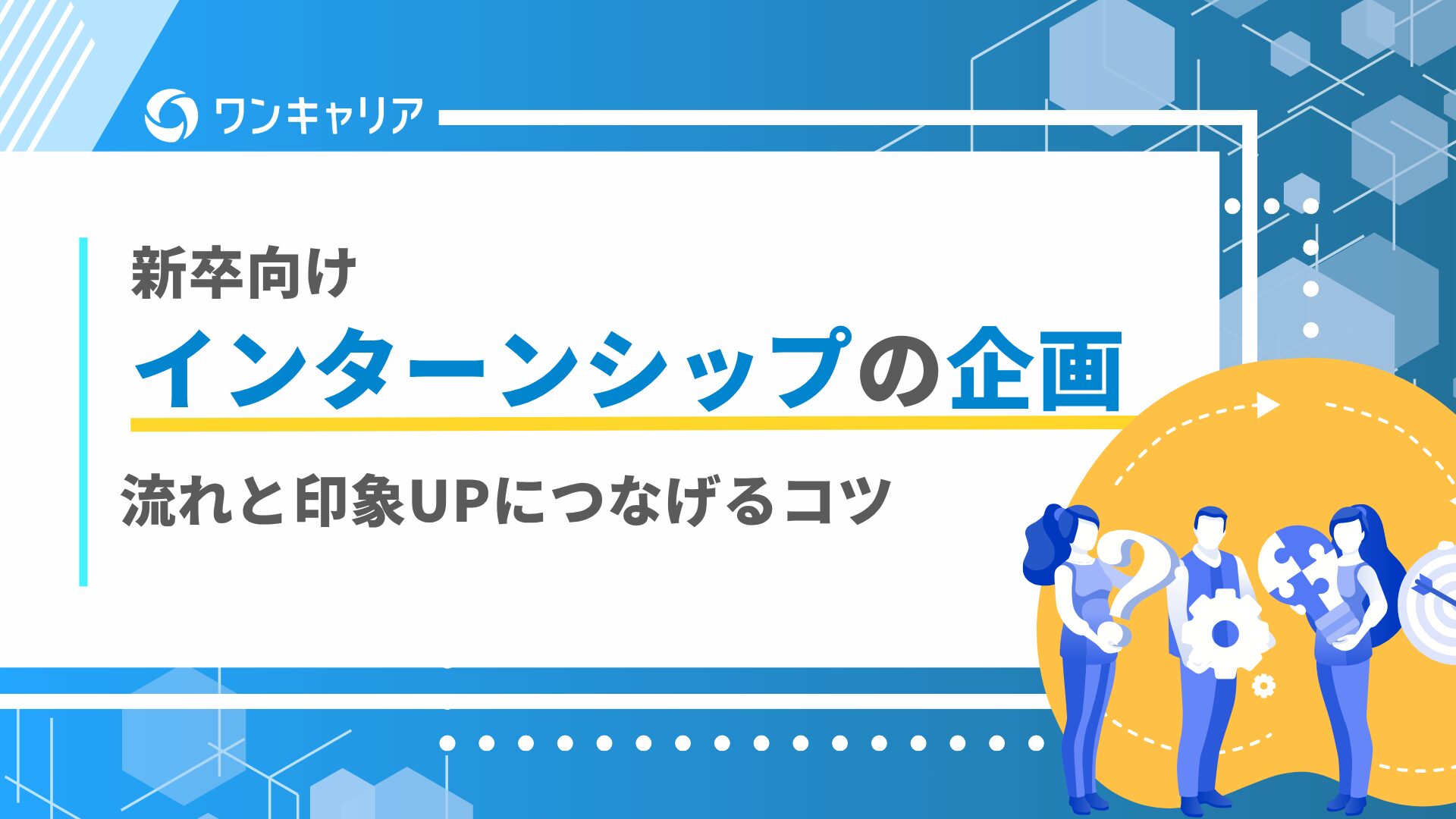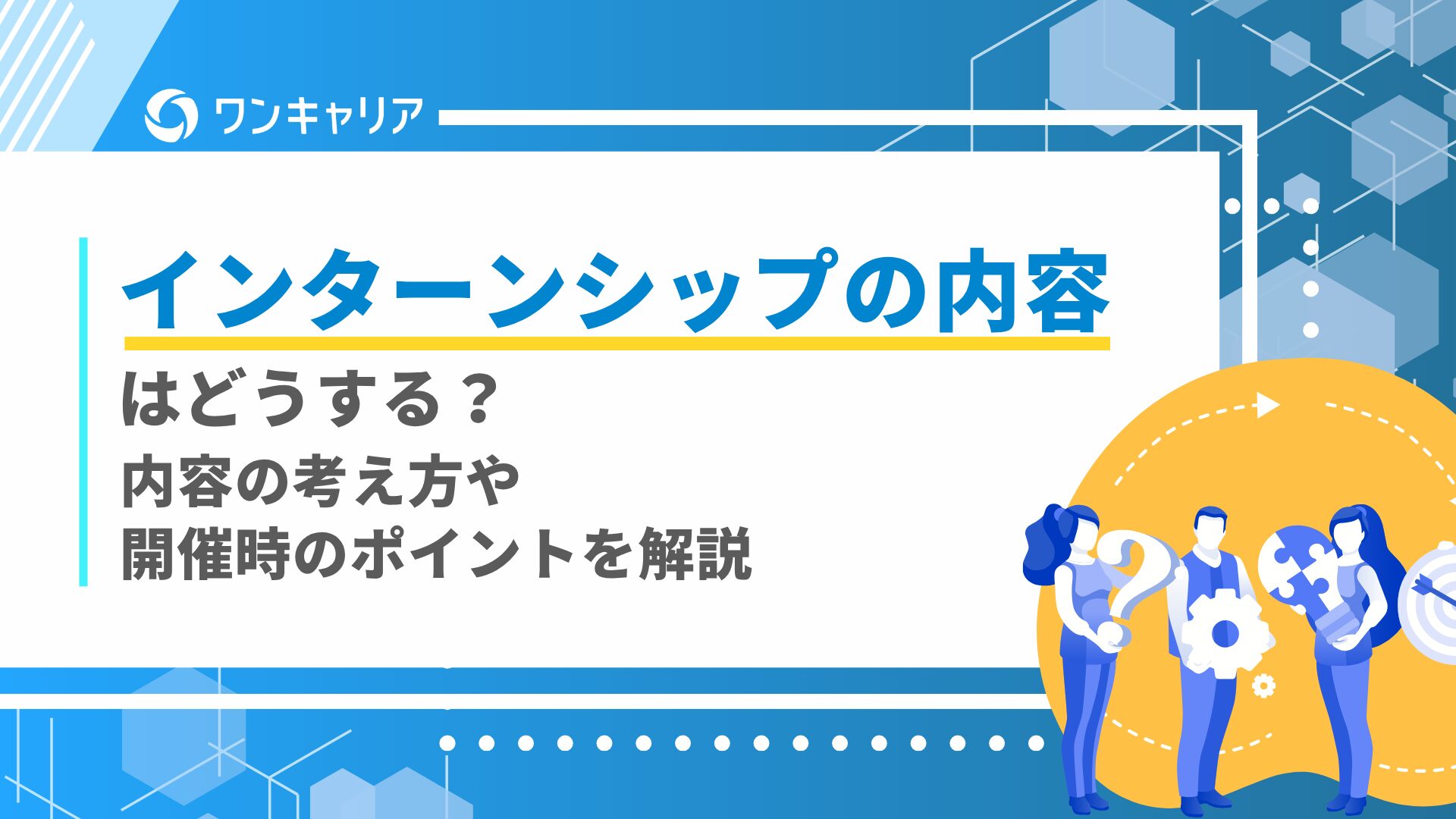目次
主に新卒採用で行われる「座談会」。近年では、社員と内定前の学生が交流する場を積極的に設ける企業が少なくありません。新卒採用で座談会を実施すると、企業や学生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。 ここでは、新卒採用で実施される座談会について解説します。座談会の内容などの基礎知識から、よくある質問例までお伝えします。採用手法の見直しを検討されている人事部門のご担当者様は、ぜひ参考にお読みください。
就活における座談会とは

就職活動における座談会とは、会社説明会や合同企業説明会などのイベントの時間を活用して、企業担当者と学生が交流する機会のことを指します。
会社説明会においては、企業担当者側から情報を発信する一方的なコミュニケーションが目立ちますが、座談会では学生との対話を通して双方向のコミュニケーションをとることが可能です。
学生側としては会社説明会で聞いた内容をもとに、気になる点を企業担当者に直接質問し、疑問を解消できる重要な機会です。
説明会で伝えられる内容は大衆向けに一般化されていることが多く、学生自体の知りたい情報とは軸がズレていることもあります。
直接企業担当者に質問できる機会を持つことで、不安点をクリアにできるほか企業に対しての興味関心にもつながります。
座談会で学生との接点を持ち、定期的に接点を持っていくことで、採用したい人材とのつながりを持つことが可能です。
就活で座談会を開催する目的
これまでは企業側からの情報発信のみにとどまっていましたが、最近では学生自体が企業について理解する機会を就活で求める風潮が広まっています。
学生の売り手市場が拡大していることから、企業主体で学生を選ぶのではなく、学生から選ばれる立場を活かした採用活動が必要になります。
学生との双方向のコミュニケーションをとるためにも、座談会の場を活用して学生との距離を縮めることが大切です。
より詳細な座談会の開催目的を、以下で解説していきます。
学生の自社理解を深める
座談会では、社員が学生により多くの情報を伝えることができます。
説明会ではカバーしきれない細かい質問を拾えるので、学生が自社についてより知る機会になります。
詳細な業務内容、仕事のやりがい、同僚との人間関係まで発信できるでしょう。現場で働く社員だからこそ伝えられるリアルな自社の魅力に触れてもらえるチャンスです。
面接では聞きにくい内容も質問してもらいやすいので、どのような質問に対しても本音で、誠意を持って対応できると学生の信頼を得ることにもつながります。
また学生との対話を通して、自社に興味を持っている学生がどんな価値観を持っているのか、学群や傾向を探ることができます。
今後の採用にあたって、自社の採用に活かせる情報収集も実行可能です。
学生に社風や現場の雰囲気を伝える
学生は座談会を通じて、現場さながらの雰囲気を肌で感じられます。社員との会話を通じて、将来働いている自分の姿をイメージする参加者もいます。そのため、企業側は座談会に適切なメンバーを選定することが重要です。
ベテランから若手まで、学生の模範となるモデル社員を偏りがないようバランス良く参加させると良いでしょう。たとえば、企業理念を体現するベテラン社員、現場の最前線で活躍している若手社員などが適しています。
自社に興味のある学生の囲い込みができる
座談会では学生に対して自社の情報を伝えるだけではなく、自社に興味のある学生の囲い込みができるメリットもあります。
座談会に参加している時点で学生はある程度、自社に対して興味を持っている状態です。
学生が不安に抱えている点や仕事に対して抱えている価値観を対話を通して引き出し、学生に対して自社でアピールできる材料を元にクロージングすることが可能です。
座談会に参加してくれた学生に対しては定期的に連絡を取ることもできるので、採用競合企業に負けないように事前に囲い込みができます。
新卒の早期退職を防止する
座談会を開催すると、学生と企業が認識をすり合わせることで、入社後のミスマッチによる早期退職を防止しやすくなります。多くの企業では、入社直後の新入社員の退職が課題となっています。
「想像していた仕事と違った」「職場の雰囲気が自分に合わない」などが理由の場合、入社前後でギャップが生じてしまっている状態といえるでしょう。座談会の参加社員には、自社の実態を伝えて不安を和らげ、ギャップを埋める役割もあります。
事前に自社の情報を伝えることで、学生の価値観との差を埋めつつ、自社に合う人材の採用につながります。
就活の座談会の一般的な内容
これまで会社説明会のみの開催であった場合、新しく座談会を開催するとなると、具体的なイメージがつかない方も多いのではないでしょうか。
以下では就活の座談会開催にあたり、開催のタイミングや形式など一般的な内容を紹介していきます。
就活の座談会の開催タイミングは「会社説明会後」
座談会の一般的な開催タイミングは、会社説明会後であることがほとんどです。
座談会の目的が、学生とのギャップを埋めること、学生の入社意思を固めることにあるがゆえに、会社説明会の大枠の説明の後が企業側も学生側も双方ともに都合が良いのです。
面接のような堅苦しい雰囲気で行う必要性はないため、説明会後にブースを設けてフランクに対応することが一般的です。
座談会は複数人形式で実施することがほとんど
座談会の開催形式はいくつかありますが、複数人形式で実施することがほとんどです。
一人の社員に対して複数人の学生がテーブルを囲む形で、それぞれが質問していく形式です。
また参加学生が少ないのであれば、学生と1on1形式で相談に乗る方法もあります。
座談会のプログラムは基本学生主体
座談会のプログラム内容は、基本的に学生主体で進むように構成を作りましょう。
各自の自己紹介の時間を取りつつ、質疑応答の時間を多めにとっておくのがベターです。
学生の話しやすい状態を企業側で作りながら、学生の求める情報を話せる時間を用意しましょう。
就活の座談会で学生からよくある質問例

就活の座談会へ向けて、学生から多く寄せられる質問をチェックして、参加社員がスムーズに回答できるよう準備しておきましょう。最後に、よくある質問例をご紹介します。
求める人材像やスキルに関する質問
学生は、説明会や求人情報だけでは得られない、企業側の本音を知りたがっています。求める人材像やスキルに関する質問は、回答が難しい場合も多いので、参加社員に模範回答を共有するなどの対策が必須です。スムーズに答えられないと、イメージダウンや不信感につながるおそれがあります。
【具体的な質問例】
・これまでどのような学生を採用してきましたか?
・どのようなスキルを持つ方が働いていますか?
・採用における選考基準を教えてください
業務内容や商品・サービスに関する質問
座談会では、業務内容や商品・サービスに関して、説明会や採用サイトよりもさらに詳しく質問される可能性があります。自社ついての質問に限らず、同業他社に関連した質問をされるケースもあるため、業界についての情報を広く押さえておくと安心です。
【具体的な質問例】
・○○業界にはどんな課題があるのでしょうか?
・御社の商品には○○社と比べてどういった強みがありますか?
・仕事で大変だと感じるのはどんなときですか?
社風に関する質問
多くの学生にとって、既存社員とフランクに話せる座談会は、企業の社風を知る大切な機会だと考えられています。そのため、座談会では社風に関する質問が多く寄せられる傾向にあります。仕事内容への適性に加えて、学生が組織に定着する上で重要な部分であるため、充実した回答ができるように準備しておきましょう。
【具体的な質問例】
・社員同士で交流する機会はどれくらいありますか?
・〇〇さんは社風のどのような点に魅力を感じていますか?
・御社独自の文化にはどんなものがありますか?
給与や福利厚生など待遇に関する質問
一般的に、給与や福利厚生といた待遇に関する質問は、企業側から消極的に受け取られかねないという理由から、説明会などの場面ではマナーとして遠慮する学生が多くいます。一方、座談会やOBOG訪問では個人的に聞かれやすい質問であるため、模範解答を共有しておくようおすすめします。
【具体的な質問例】
・〇〇さんはどの福利厚生制度をよく利用していますか?
・〇〇の資格取得を支援する制度はありますか?
・有給休暇の取得率を教えてください
就活の座談会をスムーズに進める4つのポイント

就活の座談会をスムーズに進める上で大切な、4つのポイントを解説します。自社の採用活動で座談会を実施するなら、以下の工夫に取り組み、貴重な会を成功へと導きましょう。
座談会のテーマを設定する
初めに座談会の目的や、学生に伝えたい内容を明確にすることが重要です。たとえば「自社の魅力を知ってもらう」「業務内容を深く理解してもらう」「自社で働くイメージを持ってもらう」といったテーマが挙げられます。採用担当者は、学生が座談会に求めることを把握し、有意義なアピールの場にするよう意識しましょう。
開催のタイミングを見極める
座談会を実施するタイミングは、採用選考のイベント後が望ましいでしょう。基本的に、企業説明会・インターンシップ・集団面接・内定者フォロー面談の後などに実施するのが一般的です。これにより、自社への関心が高まった学生を、適切なタイミングでフォローしやすくなります。
学生がリラックスできる雰囲気を作る
座談会では学生の本音を引き出すために、リラックスした雰囲気を作ることもポイントです。座談会に参加する側の学生は緊張しやすいため、軽食を食べながら、カフェ音楽をかけながら、など和やかな雰囲気によって緊張を解いて、社員との会話が弾みやすい状態を目指しましょう。コミュニケーションが充実すると、企業研究での自社への理解度が深まるほか、志望度向上の効果も期待できます。
質問例と模範解答を参加社員に共有する
多くの学生が興味を持つ情報の回答はあらかじめ用意しておくのがコツです。学生から寄せられる質問内容は、ある程度定型化しています。なかでも仕事のやりがい、職場の雰囲気、上司の人物像などに関する質問は定番だといえます。事前に準備することで、社員がしっかりと意見を伝え、学生の要望に応えやすくなるでしょう。模範回答の共有は、参加社員の負担を軽減することにもつながります。
就活の座談会を活用して採用競合よりも有利に!

今回は、新卒採用で実施される座談会について解説しました。学生にとって有意義な座談会を開催して、自社の採用活動を有利に進めましょう。
新卒採用の施策を実施するなら、多くの学生が集まる「ワンキャリア」がおすすめです。学生データベースは国内最大級で、新卒採用に役立つ多彩なサービスが用意されています。
ぜひ座談会をはじめとした新卒採用の施策でお役立てください。