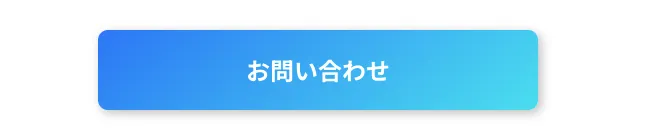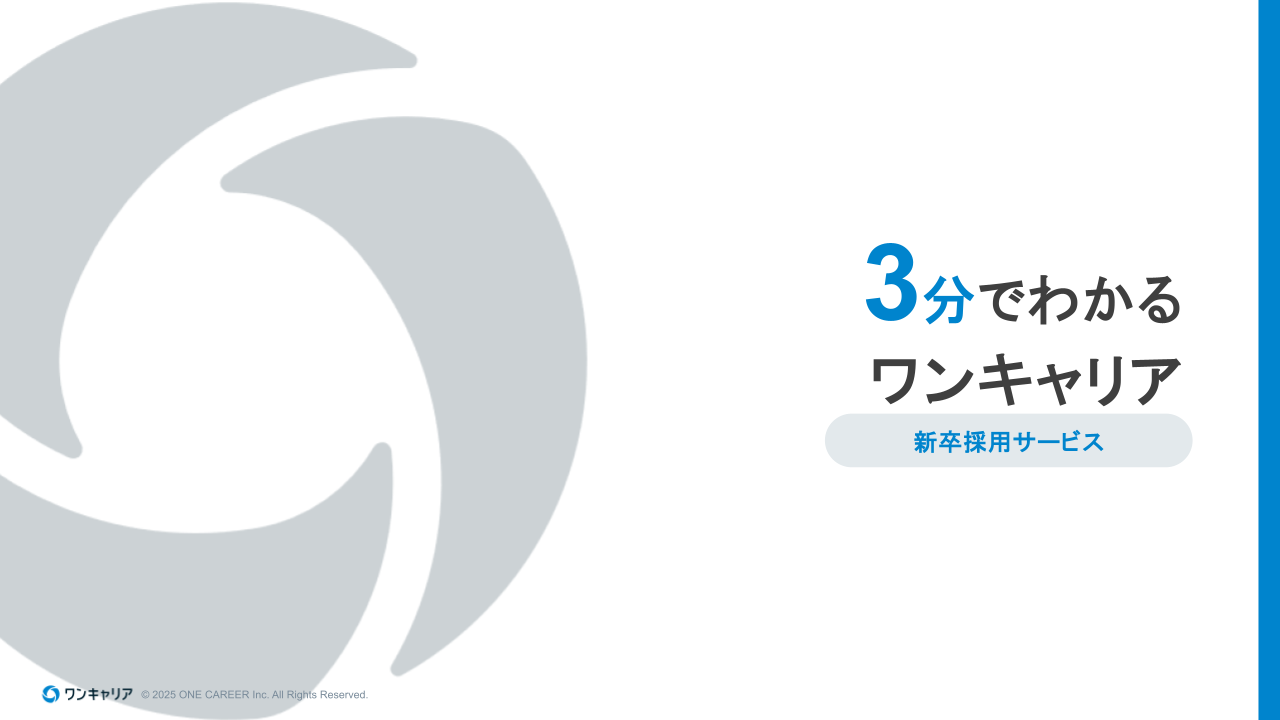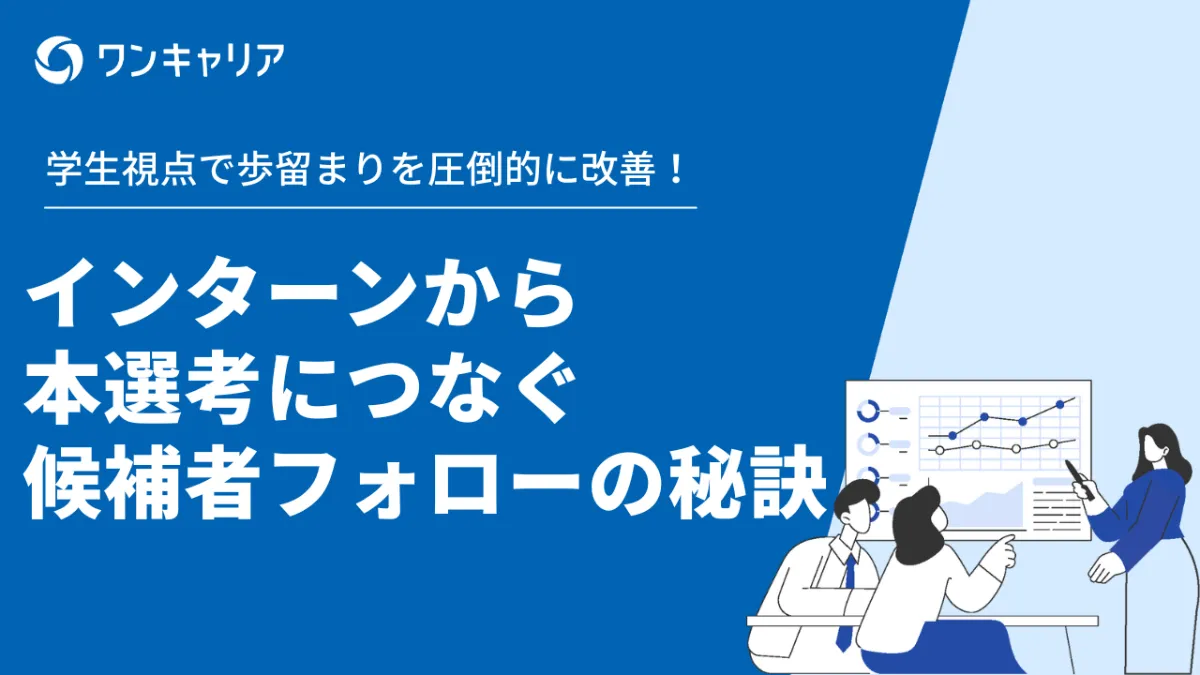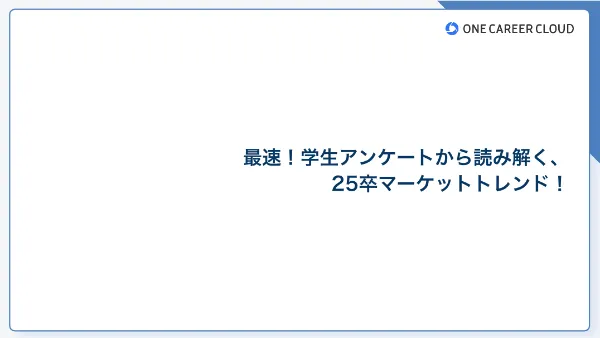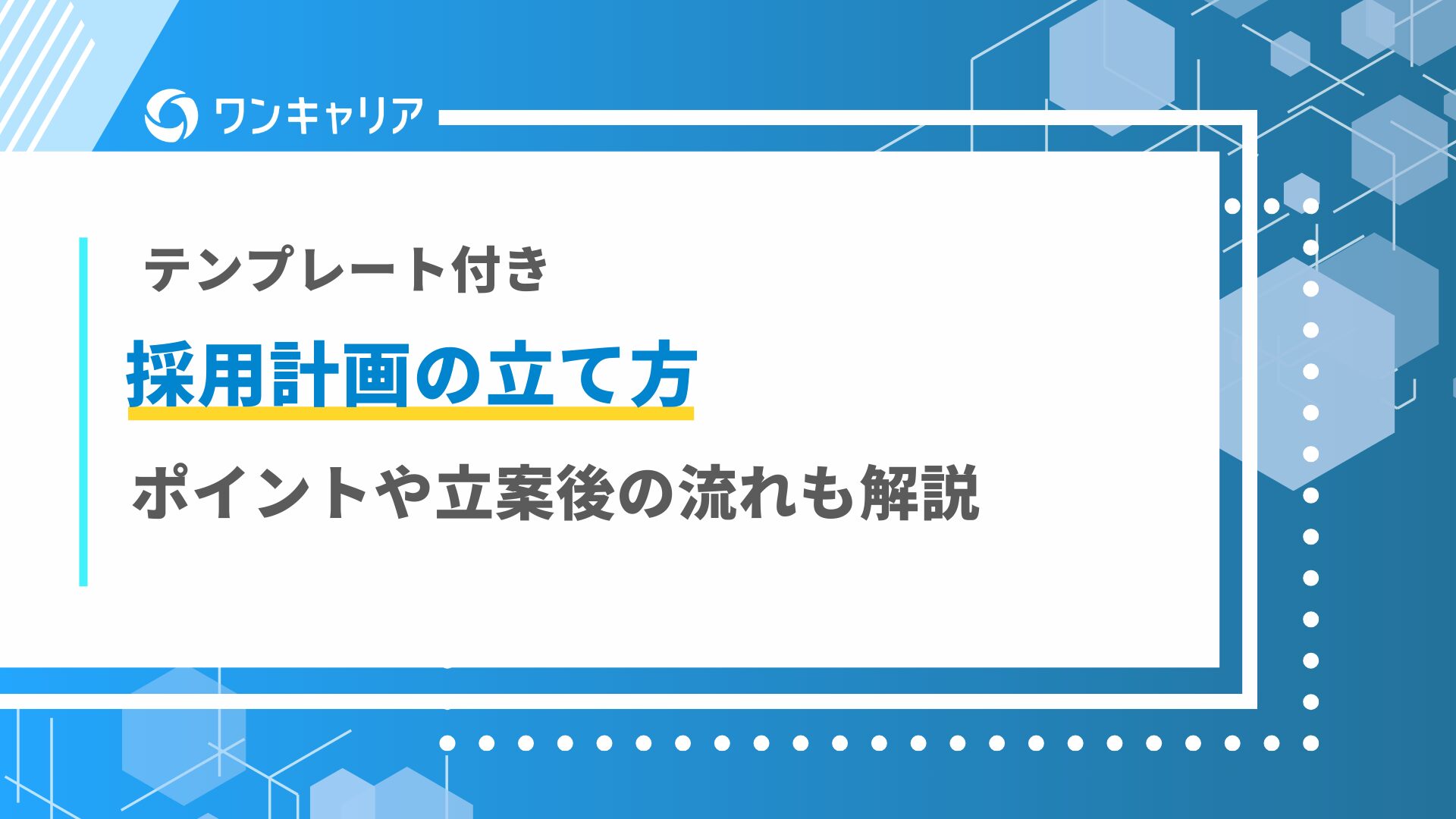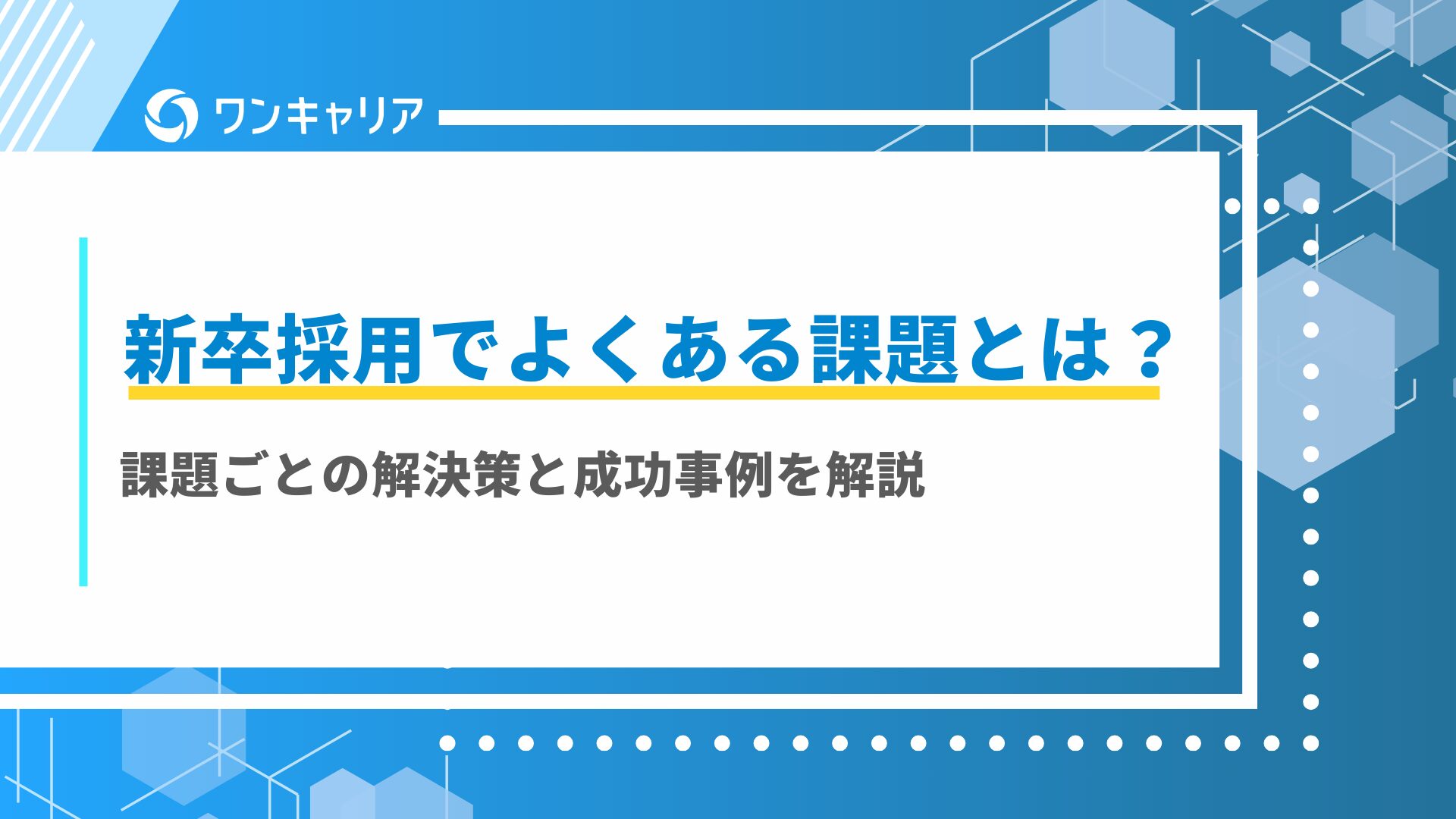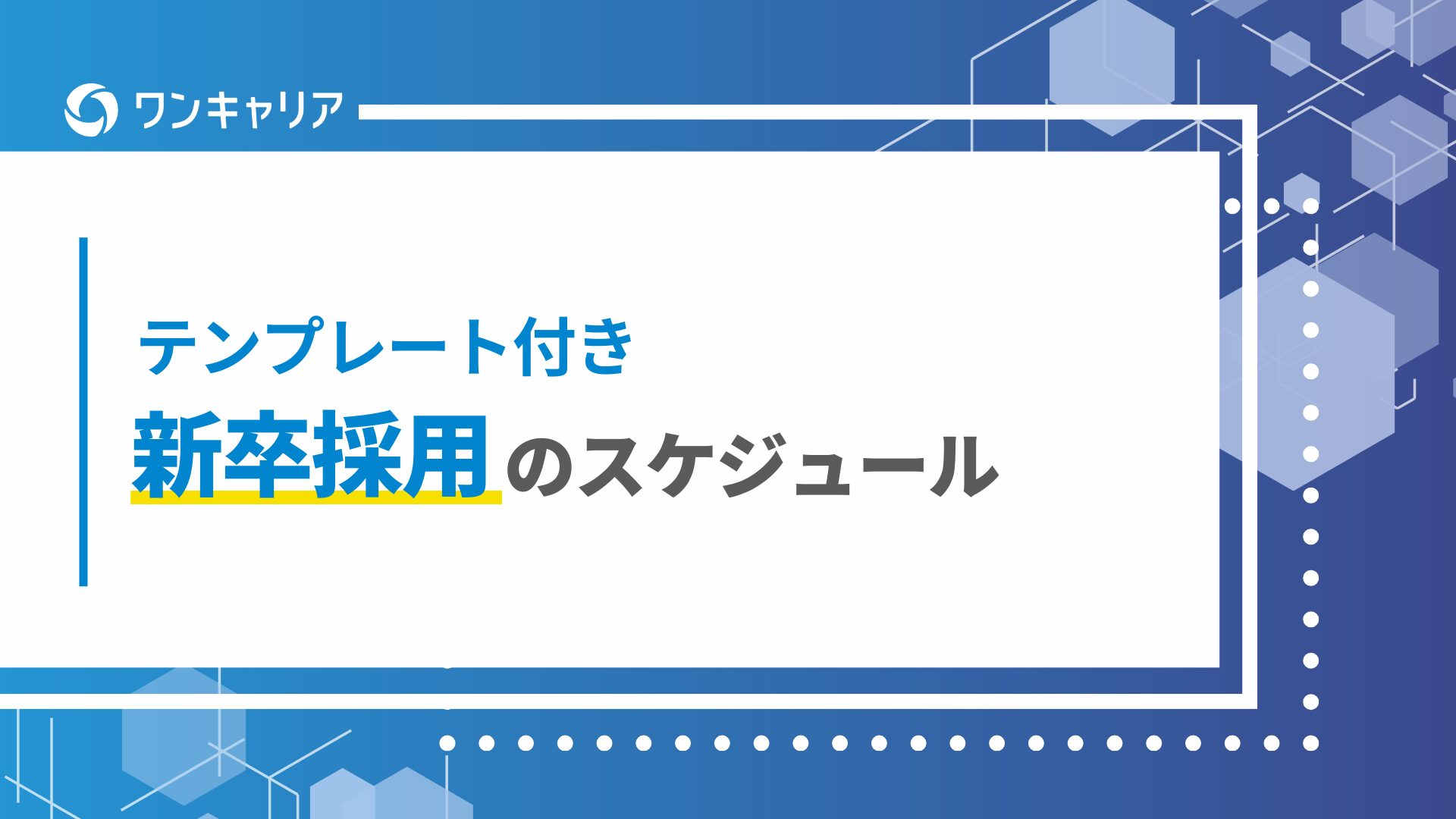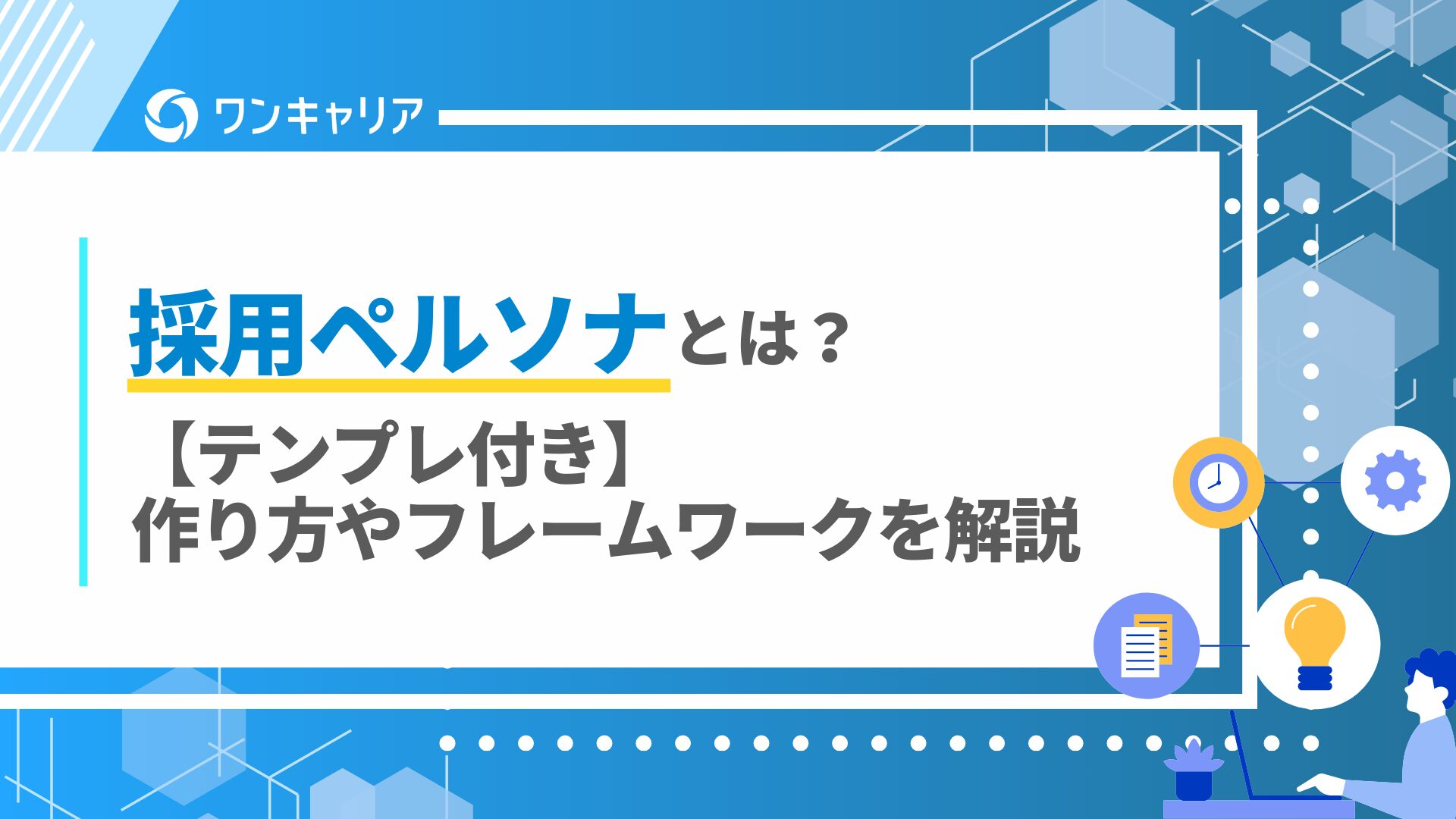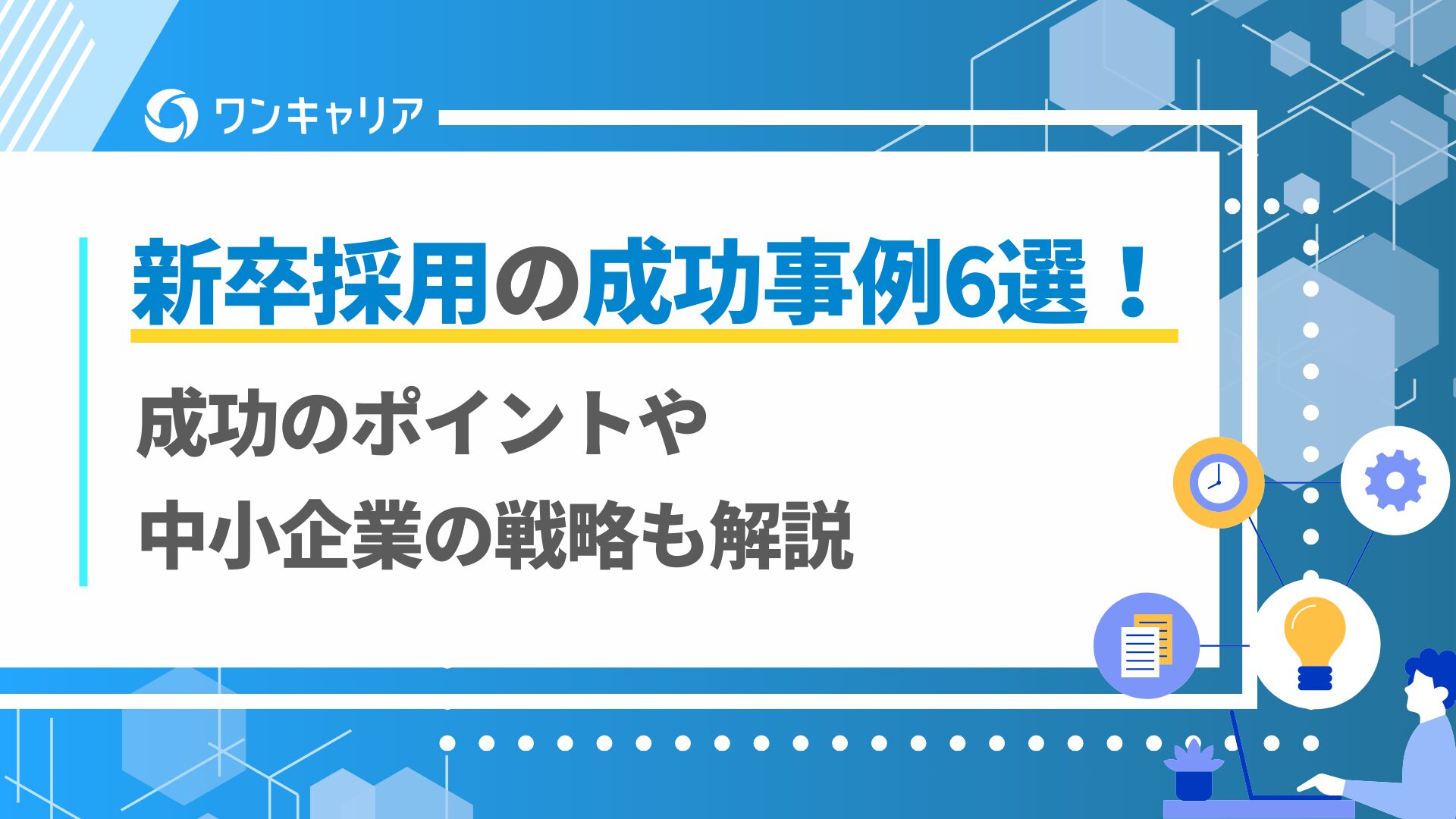目次
内定辞退率とは内定承諾者のうち、応募者の本人都合で入社を辞退される割合のことを指します。 最近では学生の売り手市場が続いており、内定を出したとしても学生都合による内定辞退が続いています。 そのため各企業では内定辞退率が上昇傾向にあり、各担当者が数値改善に頭を悩ませています。 この記事では改善に必要な内定辞退率の平均値から、人事担当が知るべき低下の原因・改善方法のポイントを解説しています。 数値改善に悩まれている人事担当の方は、是非参考にしてみてください。
内定辞退率に関する基礎知識

ここでは、内定辞退率に関する基礎知識を理解しましょう。内定辞退率の定義や、それが企業に与える影響について説明します。
内定辞退率の定義
内定辞退率とは、企業が内定を出した求職者の人数に対して、内定を辞退した人数の割合です。応募者は内定の通知を受け取っても、憲法22条で「職業選択の自由」が保障されているため、内定辞退の選択をしても法的にも問題はありません。しかし、企業側から見ると、コストをかけてこぎつけた内定の辞退が続けば、経営体力が低下するため、適切な対策が必要です。
内定辞退率と市場の関係性
就職みらい研究所の調査によると、2023年卒の新卒者の内定辞退率は57.8%(2022年7月1日時点)で2021年の同時期よりも2.8%増加しました。
少子高齢化に伴う労働人口の減少により、売り手市場が続いており、それに伴って内定辞退率は増加しやすい傾向にあります。応募者側から見ると、企業を選択する幅が広がるためです。そのため、志望度の低い企業にもとりあえず応募し、他社の選考次第で内定を辞退するケースも起こり得るのです。
企業の内定辞退率が増加すると起こり得ること
年々、企業の内定辞退率が増加していますが、それによって企業はダメージを受けます。主に以下の2点です。
採用にかかったコストが消失する
新卒採用には多くのコストがかかります。例えば、求人メディアへの掲載費や採用WebサイトやPR動画などの製作費、説明会やインターンシップなどの開催費用、数回に渡る面接などです。就職みらい研究所が発表した「就職白書2020」によると、2019年度の新卒者1人あたりの採用単価は93.6万円といわれています。内定辞退によって、その金額に近いコストが消失してしまうのです。
予定していた数の社員を雇用できない
内定によって入社が最終的に確定した訳ではありませんが、企業側としては内定辞退により、確保したい人材が失われることになります。また、同じタイミングで入社予定だった人が内定辞退すると、周りの人にも良くない影響を与える可能性もあります。例えば、同期が減ってモチベーションの低下に繋がるケースも考えられます。
内定辞退が発生する理由

内定辞退が発生する理由は、企業側と学生側双方にあります。多いのは、より志望度の高い企業から内定をもらったため辞退するという学生側の都合であり、この点に関しては企業が対策することは困難です。一方、内定辞退を誘引する原因は企業側にあるケースも考えられます。
雇用条件でミスマッチが生じた
内定辞退が発生する企業側の1つ目の理由は、雇用条件のミスマッチです。選考過程で雇用条件を明確に伝えていない(伝えたつもりの)場合に起こりやすいケースです。また、募集要項と実態が異なっており不満に繋がることもあります。
面接官や人事担当者に悪い印象を持った
2つ目の理由として、選考の過程で内定辞退したい気持ちが強くなることが考えられます。応募者は面接官を通じて、良くも悪くもその企業の社風や雰囲気、カルチャーを感じ取ります。面接官や人事担当者は会社の顔といってもよい存在なのです。それにもかかわらず、失礼な質問が続いたり、雑な対応が取られたりすると不信感が募り、最終的に内定辞退に繋がることがあります。
入社後の姿を想像して漠然とした不安を抱いた
3つ目の理由として、応募者が入社後の姿を想像して漠然とした不安を抱くケースです。特に内定承諾後から入社まで期間が空くときに起こり得ます。これは学生側の問題だからやむを得ないと考えるべきではありません。内定承諾後に人事担当者が定期的にコンタクトを取ったり、情報発信したりすることで不安を軽減できたはずだからです。
内定辞退率を改善する方法

ここでは、内定辞退率を改善する方法について説明します。すでに触れた通り、定期的なコミュニケーションと内定者へのフォローが何よりも重要です。内定者に寄り添い、ネットやSNS上のクチコミを参照するなどして内定辞退されている理由を把握する必要があります。
面接の場で応募者が質問しやすい雰囲気を作る
勤務条件のミスマッチを防ぐためには、面接の場で応募者が気軽に質問できる雰囲気を作ることが大切です。一般的に応募者は面接において、あれこれ条件に関して質問することを躊躇します。しかし、面接を疑問を解消する場として活用してもらえれば、内定辞退率は改善するでしょう。
採用担当者が常に相談できる場を作る
応募者は内定承諾後に新たな不安や疑問が浮かんでくることも多いようです。そんなときに漠然とした不安をすぐに解消できる場を設けましょう。採用担当者が常に応募者とコンタクトを保ち、「何かあったらすぐに相談できる」状態を維持するようにしましょう。
内定者同士でコミュニケーションを図る場を設ける
内定後に応募者同士が直接会ってコミュニケーションを図る場を設けましょう。直接会うのが難しければ、オンライン上でイベントを設けたり、SNSなどを通じて繋がる機会を設けたりするのも1つの方法です。内定者が感じる不安や疑問は共通しているため、自分の気持ちや考えを頻繁にやりとりできるツールがあれば、内定辞退率の改善に繋がるはずです。
社員や役員と話ができる機会を作る
面接官や人事担当者が内定者にとって企業を知るための窓口になるのは確かです。しかし、それだけでは自分が入社する予定の企業について知りえない情報もたくさんあります。他の社員や役員とコミュニケーションを図れる機会があれば、さらに多面的に情報が得られます。また、役員とコミュニケーションを取ることで、自分が企業にとって欠かせない存在であり、期待されている役割があると実感する機会にもなるはずです。
コミュニケーションの量と質を上げることで、内定辞退率は改善する

内定辞退率の主な原因はコミュニケーションの量と質が低いことです。応募者の視点に立って、相手が必要とする情報を適切なタイミングで提供することで、内定辞退率の改善を見込めるはずです。
ワンキャリアでは、採用プロセスの改善やミスマッチ防止に繋がるサービスを提供しています。内定辞退率に悩む担当者の方はぜひお気軽にお問い合せください。