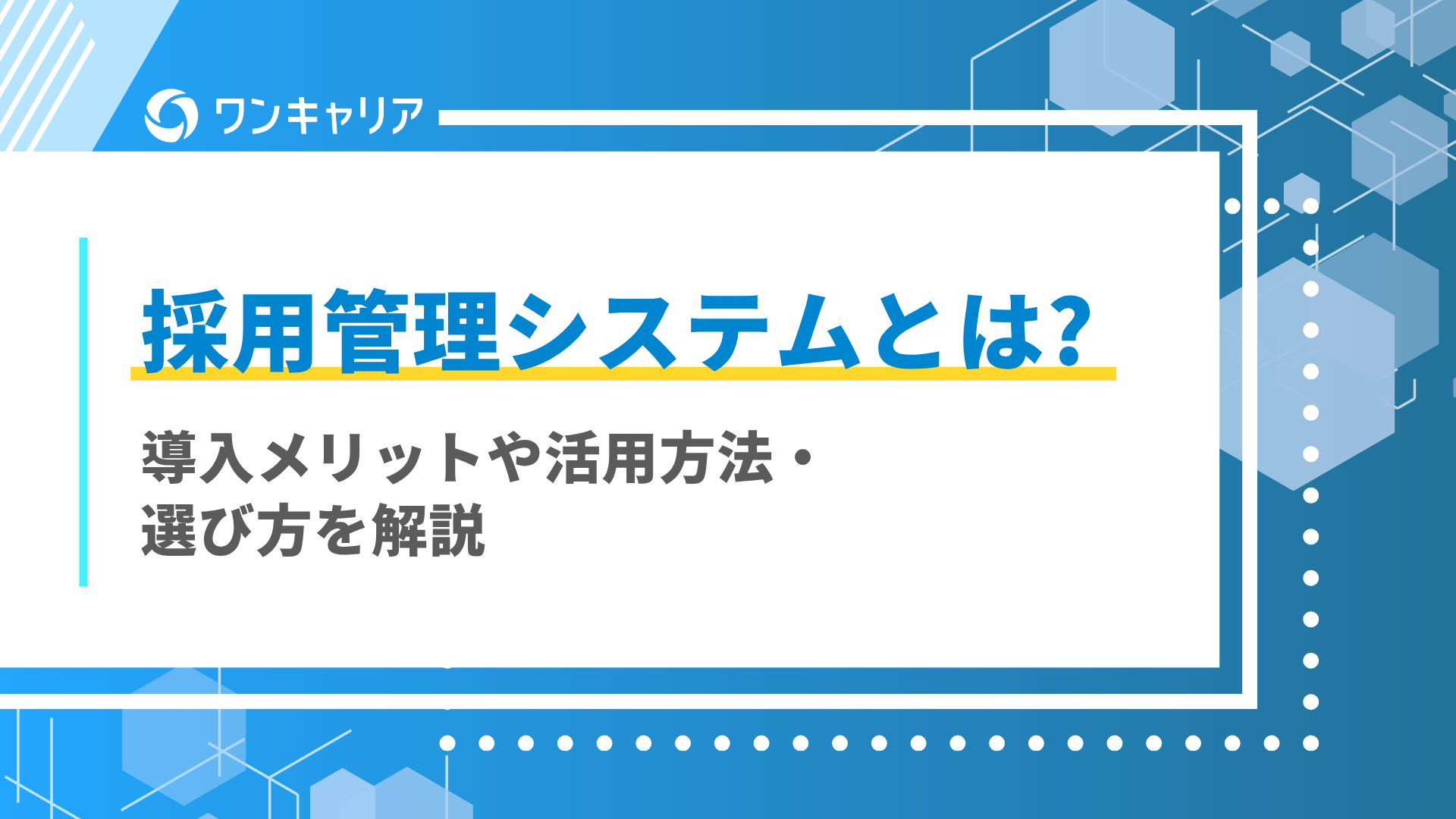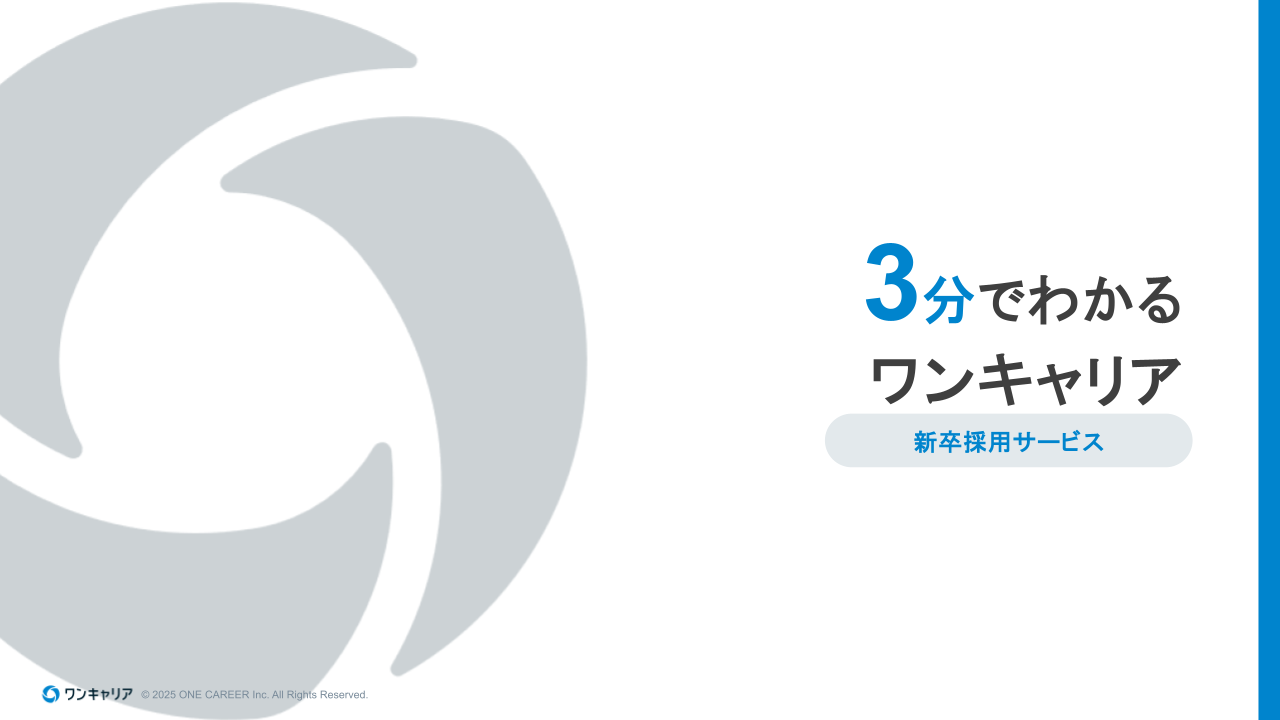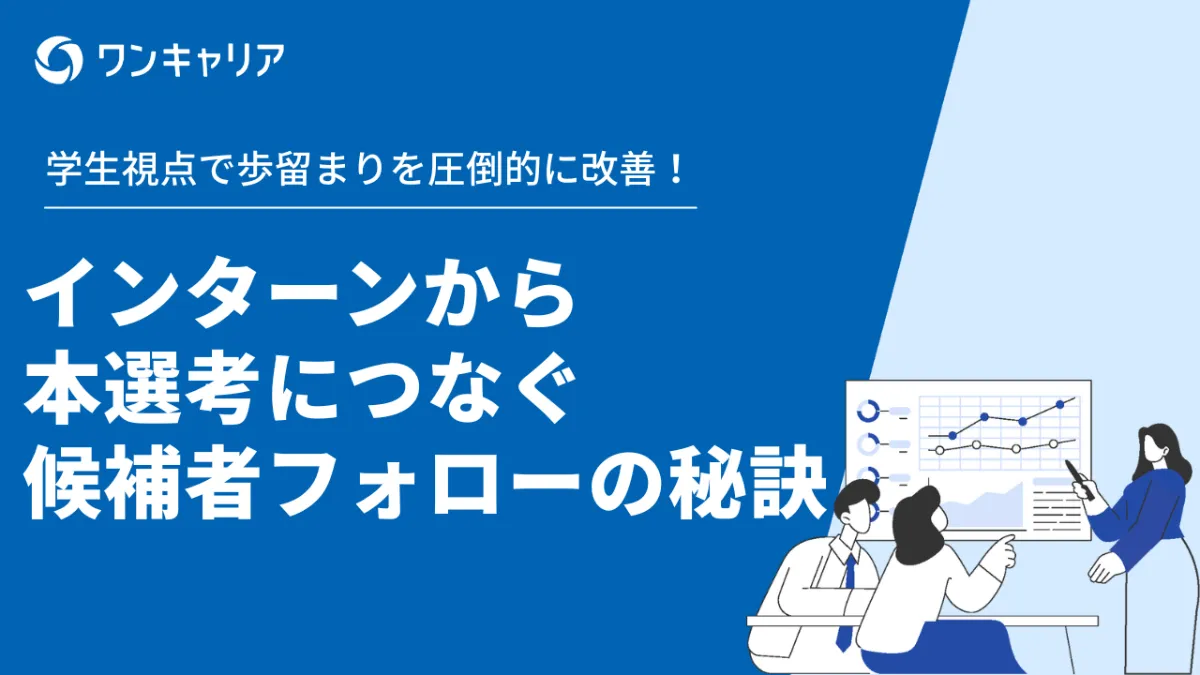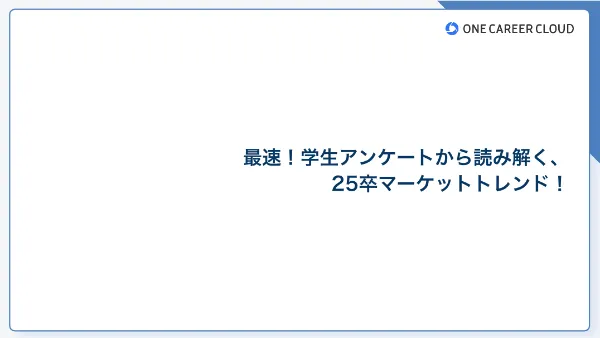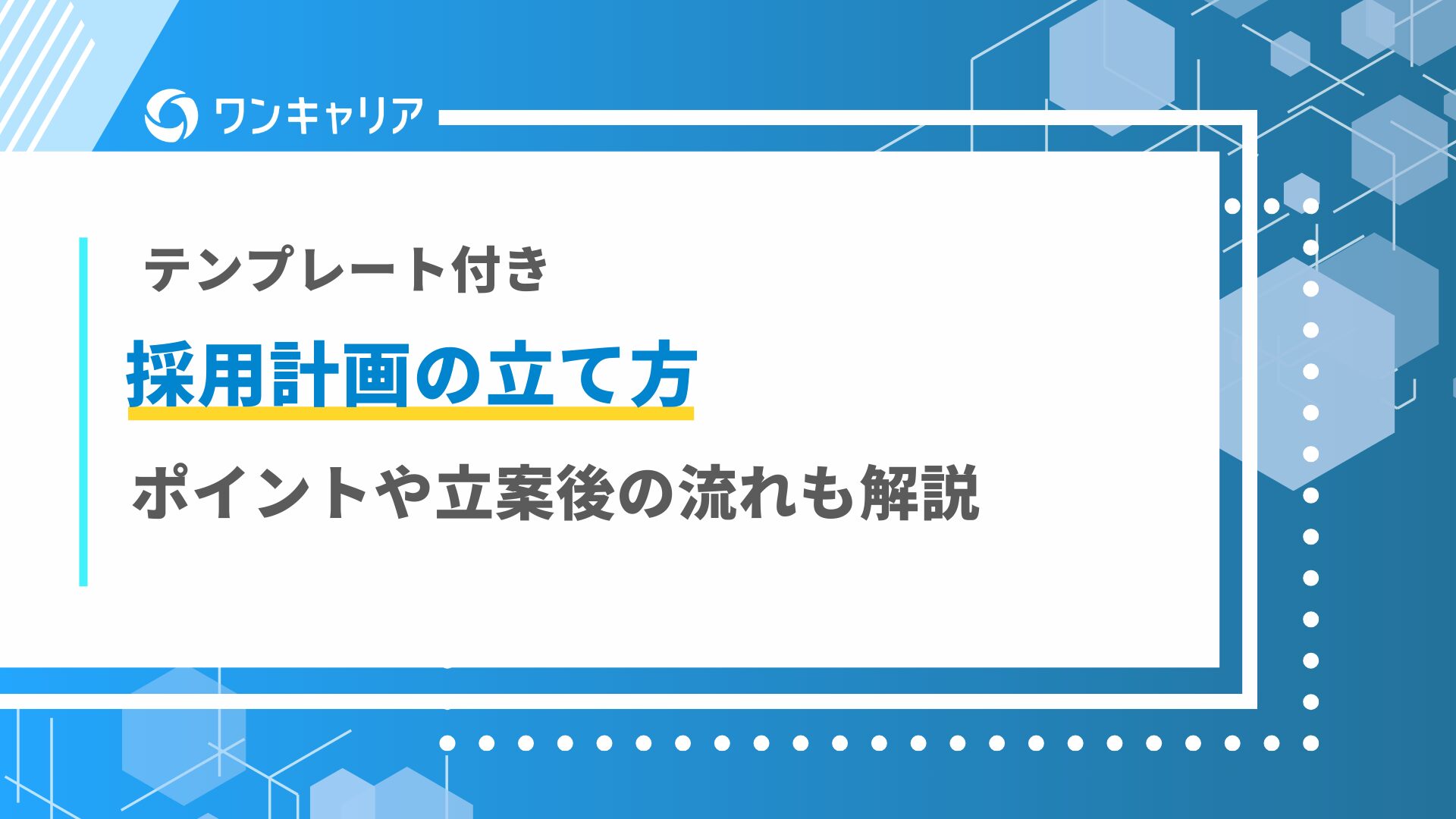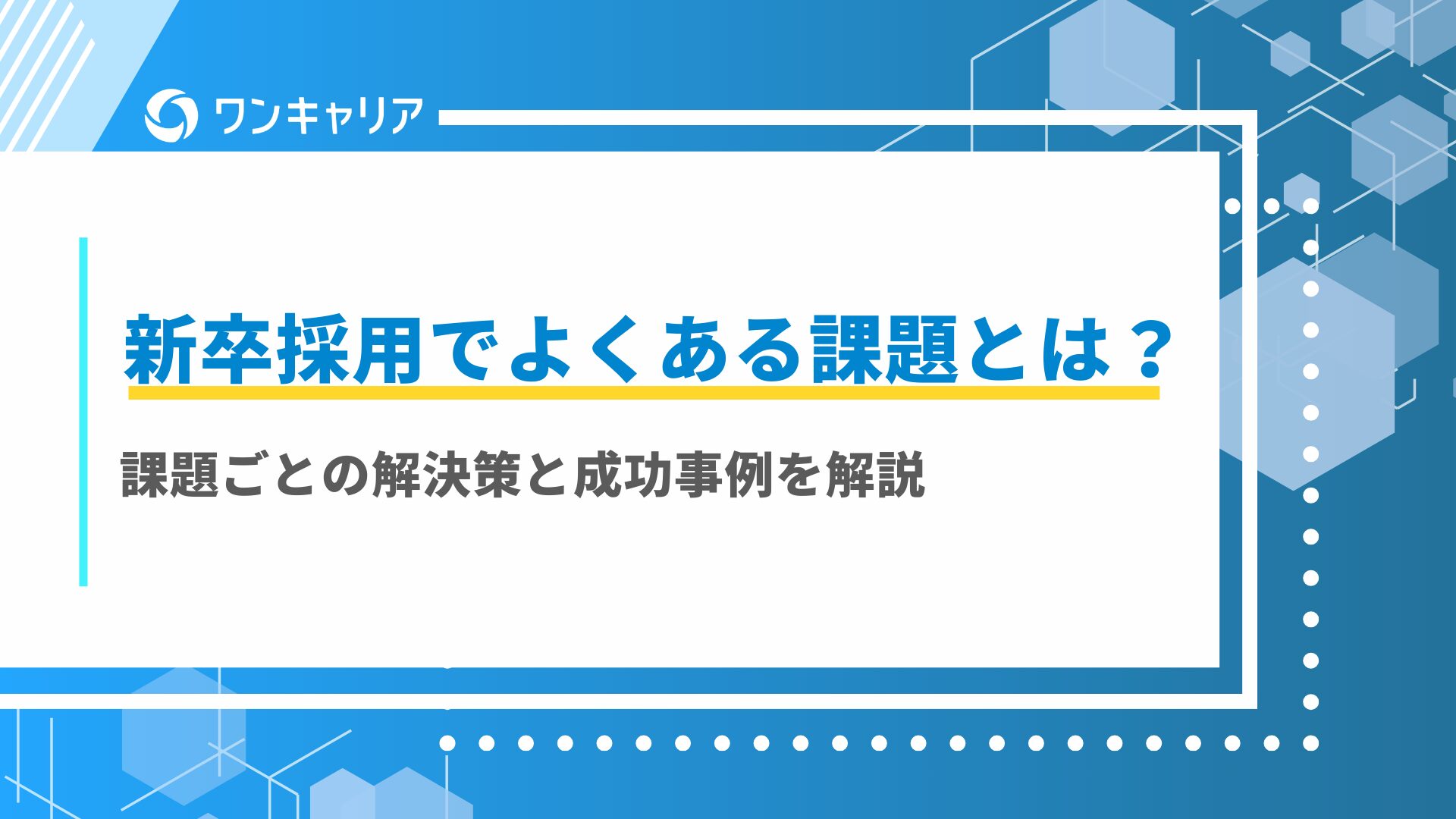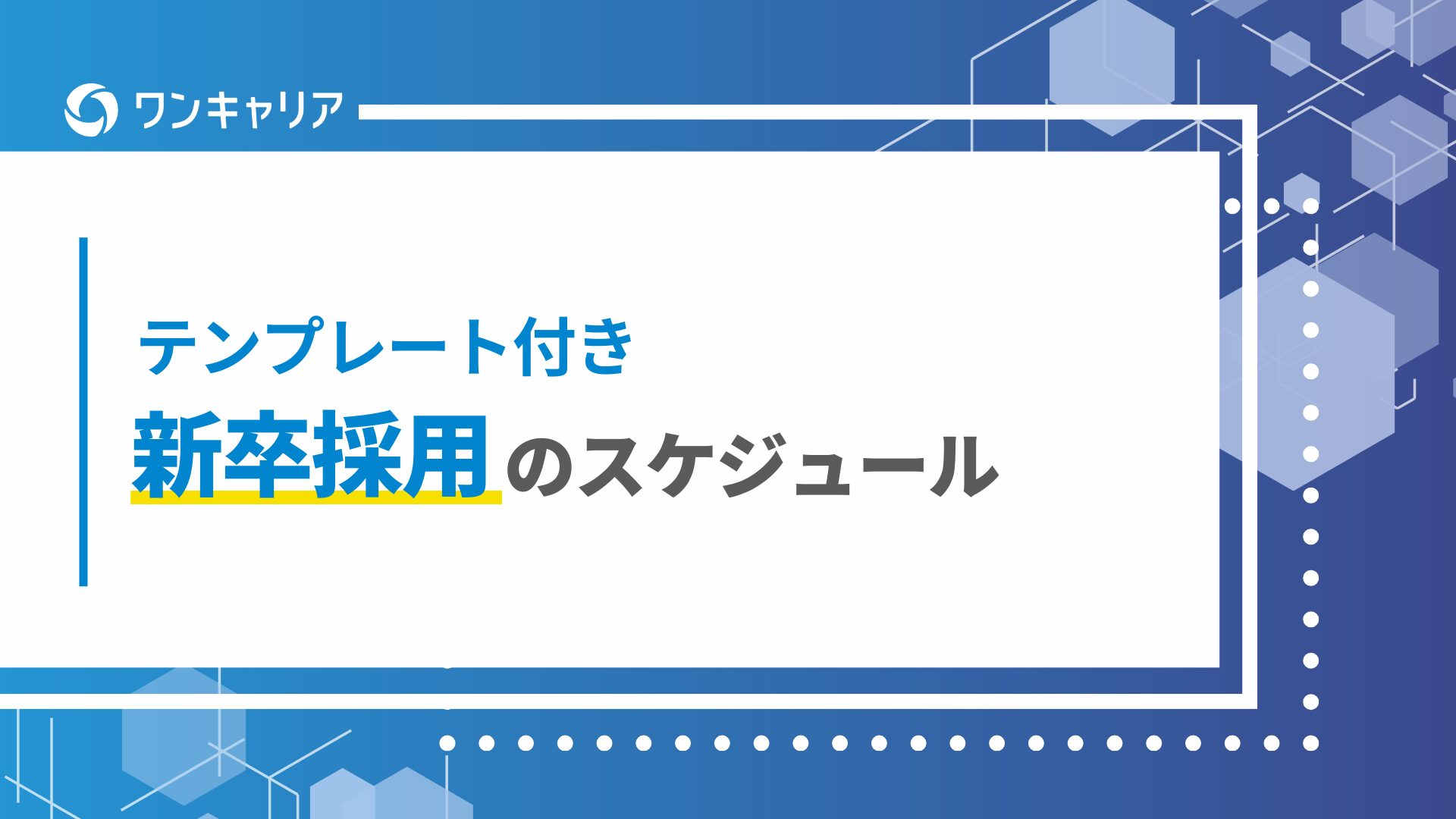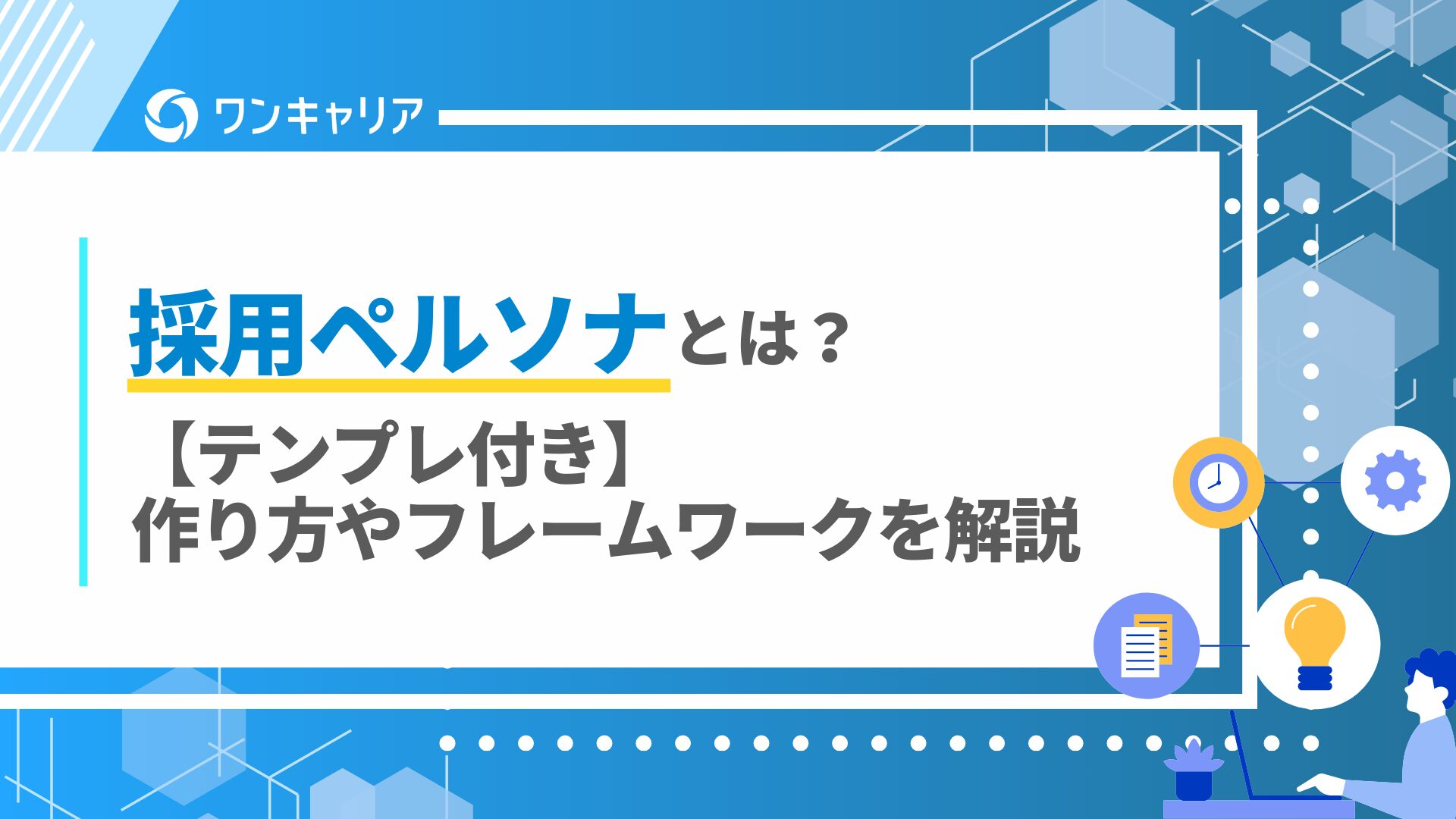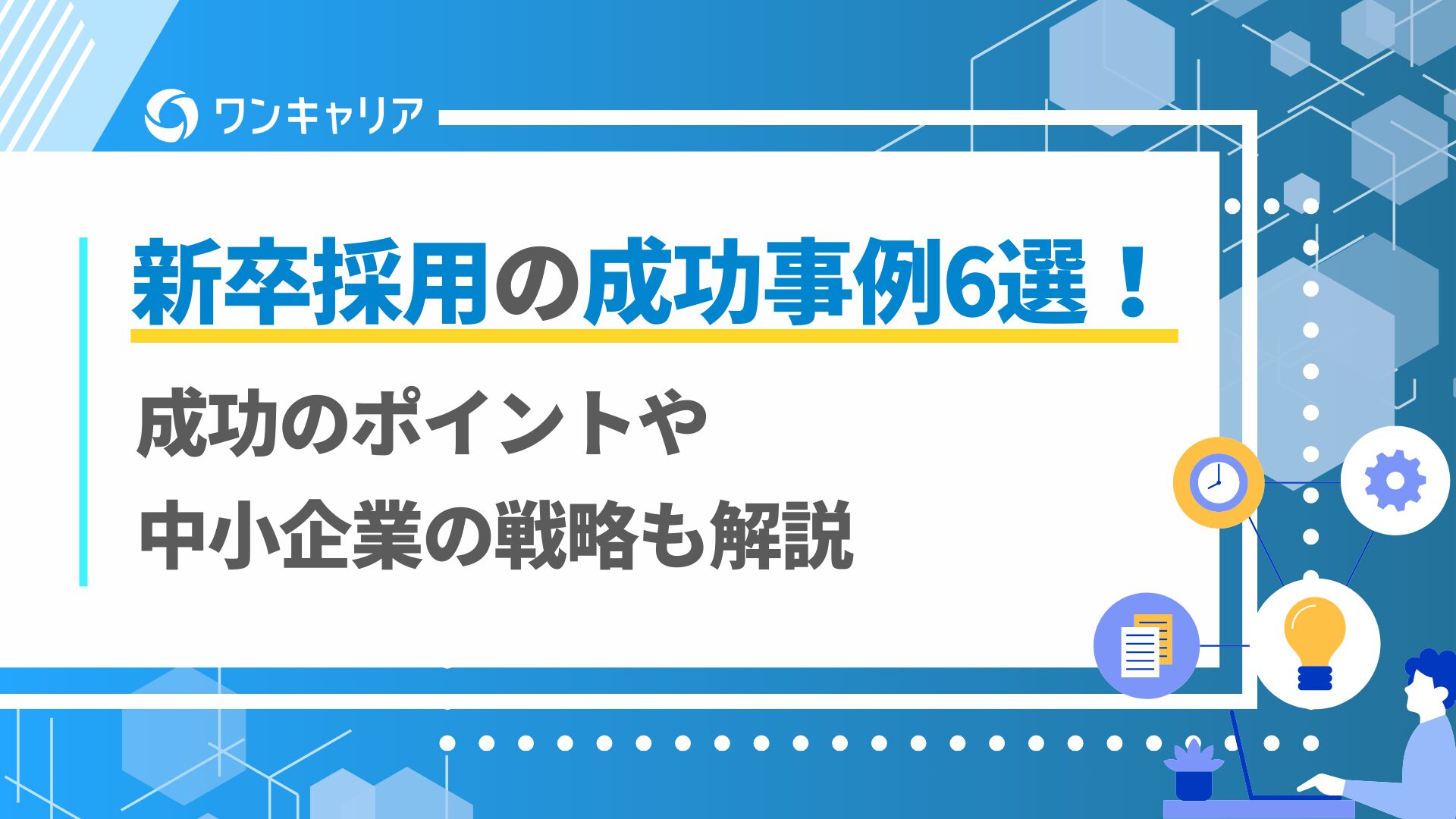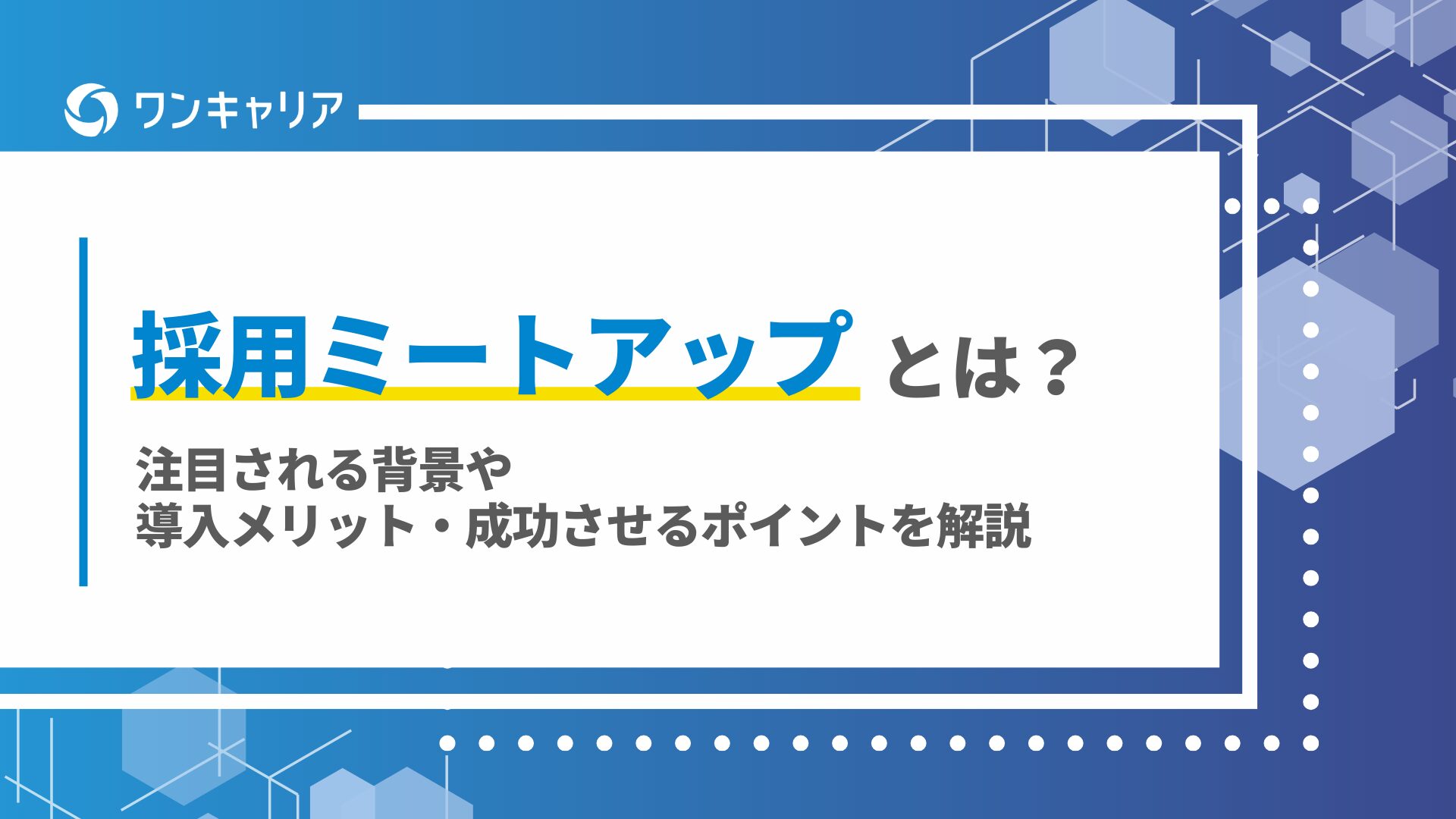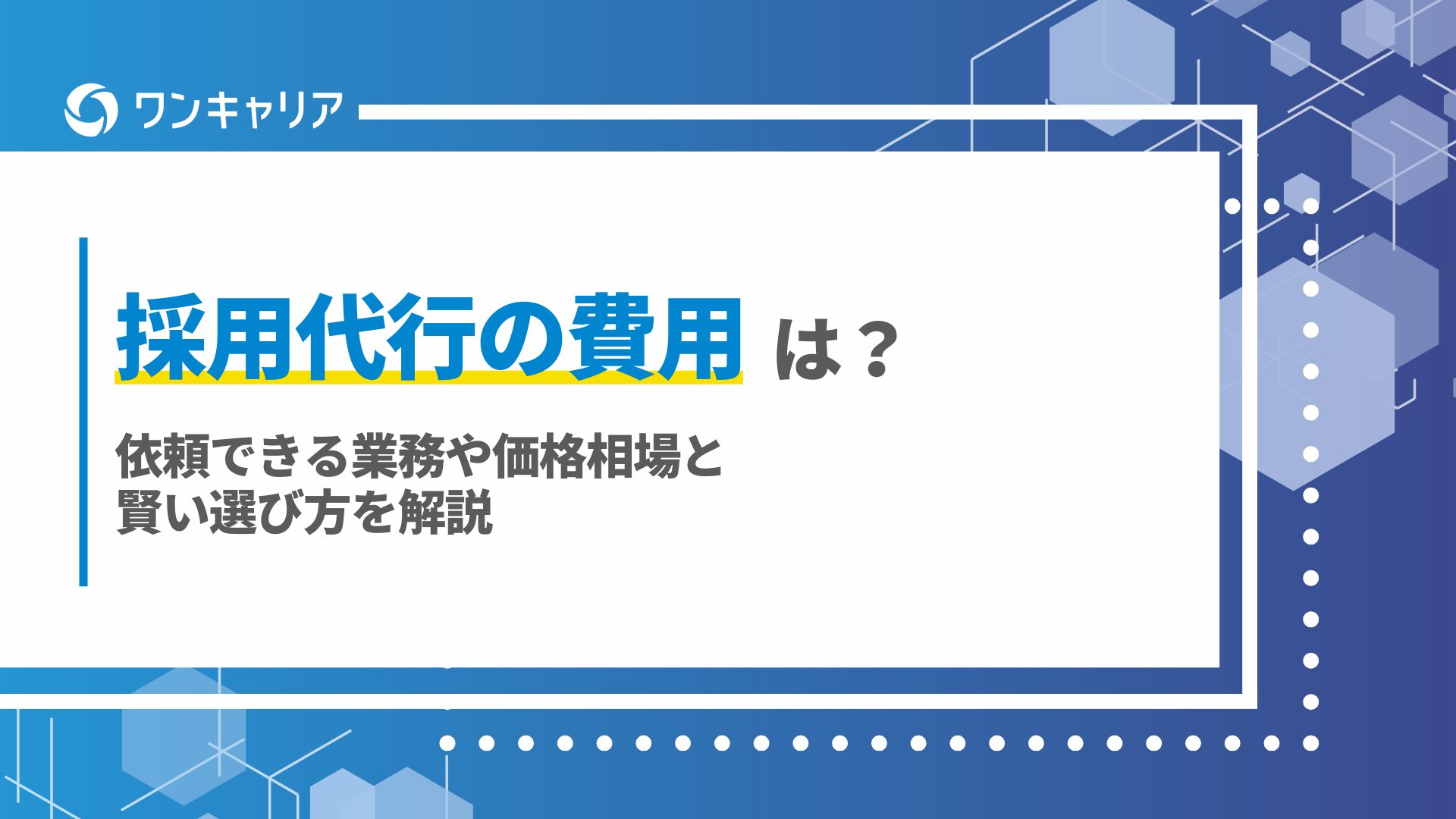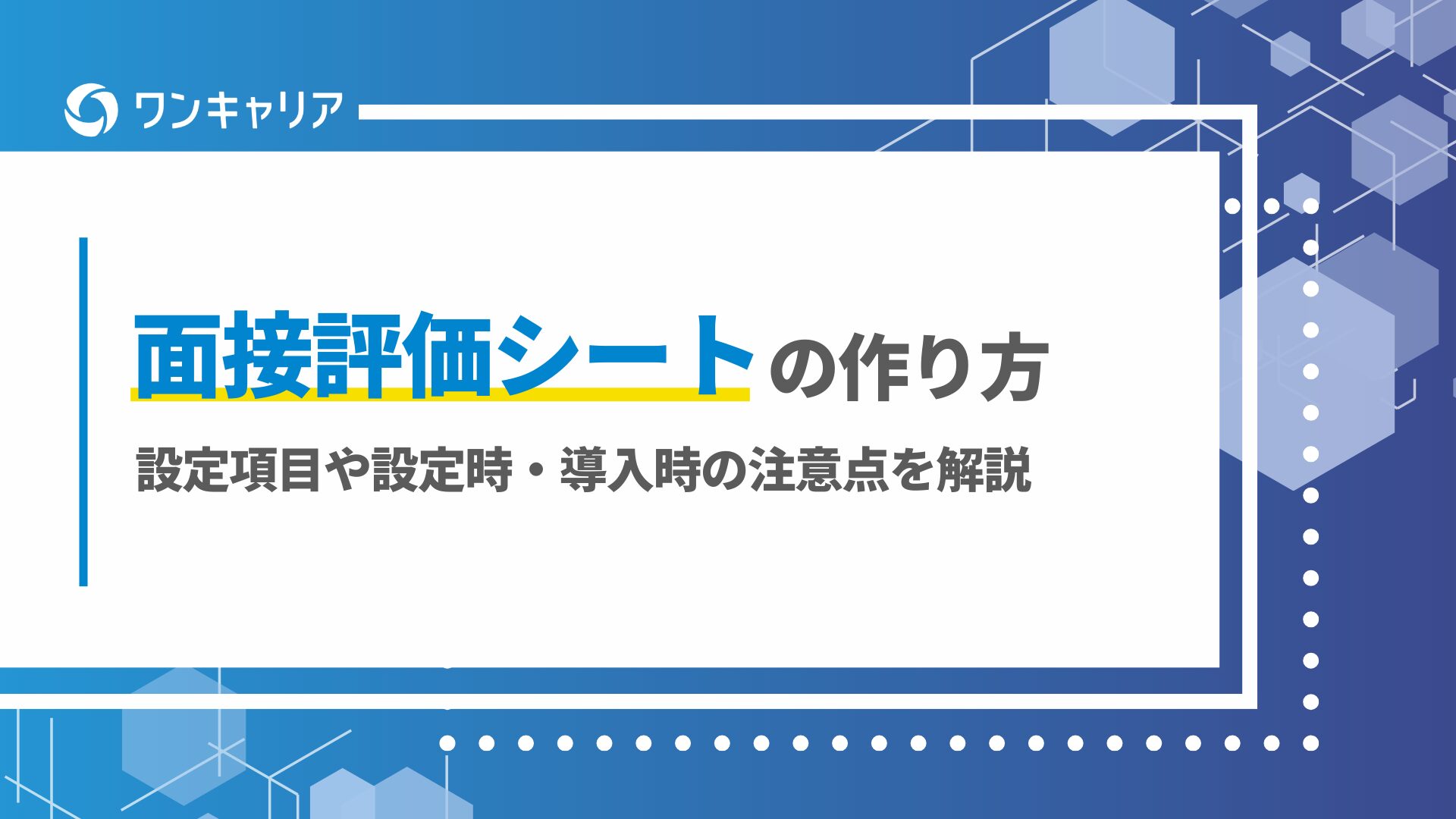目次
新卒採用は1年間のなかで採用人数が多いこともあり、手作業では採用管理がうまくいかない企業もあるでしょう。 システムを自社で管理していても、設定にミスがあると応募者に迷惑がかかることもあり、できるだけミスなく効率的な方法を模索したいと考えている人事担当の方も多いはずです。 最近では採用のフローごとに一元管理できる採用管理システムが各社から登場しています。 これから導入するためには、どんなメリットがあるのかも把握しておきたいですよね。 この記事では採用管理システムを導入するメリットから、活用方法、選び方まで徹底的に解説していきます。
採用管理システム(ATS)とは?
採用管理システムとは、採用業務にかかわるデータを一元管理し、システム上で効率化できるツールのことを指します。
応募者の管理はもちろんのこと、自社で実施している採用計画に沿った選考ステータスごとに採用状況を整理できます。
これまで手作業で管理していた選考を、一つのツールで管理できるだけではなく各種連絡手段と連携して連絡漏れを防ぐことも可能です。
また各歩留まりの数値も管理しやすく、どの選考フローで課題が生じているのか、数値が悪化しているのかも判断できます。
企業で課題になりやすい業務の属人化もシステムを活用することで、担当者間で業務内容を共有できるのもポイントです。
採用管理システム(ATS)を企業で導入するメリット
採用管理システムを企業で導入することには、多くのメリットがあります。
人事担当の皆さんとしても実際に導入を検討するには、上申のためにメリットを整理する必要がありますよね。
以下のメリットを参考に、自社の採用課題や人事業務の改善に役立てられるかをチェックしてみてください。
応募者の管理を一元化できる
まず、応募者の管理を一元化できる点が挙げられます。
従来の紙ベースやスプレッドシートによる管理では、情報の散逸や重複が生じやすくなりますが、採用管理システムを使えば、すべての応募者情報を一つのプラットフォームで管理できます。
関数やファイルの整理である程度の重複を防ぐことは可能ですが、文字列が異なったり同一のルールで運用できないと、漏れやミスが生じることもあります。
共通でログインできるシステムを活用することで、管理を一元化し、必要な情報を迅速に検索・参照できるためミスを減らしつつ選考の効率も向上できます。
連絡を一括送信できるので連絡漏れがない
採用管理システムを活用することで、学生や応募者に対して連絡を一括送信できるので連絡漏れのミスを減らせます。
作成しているリストを元にメールを送信することはできるものの、何らかの理由で送付リストの対象者が漏れてしまうこともあります。
次の選考ステータスの案内をするにも関わらず、送付漏れが起きてしまうと応募者へ不信感を与えるだけではなく採用したい人材を逃してしまう可能性も十分にあります。
求人募集サイトの構築が簡単
さらに、求人募集サイトの構築が簡単に行えます。
採用管理システムには、求人情報を簡単に作成し、公開するための機能が備わっていることが多く、企業のウェブサイトや各種求人ポータルへの掲載がスムーズに行えます。
求人情報を改善したり、システムとの連携が簡単に進むため、自社内の工数を削減することが可能です。
学生の選考ステータス管理が簡単
最後に、学生の選考ステータス管理が簡単である点も大きなメリットです。
各候補者の選考状況をリアルタイムで更新し、担当者間で共有することで、選考の進捗を正確に把握できます。
選考状況をビジュアルで一括で確認できるため、ステータスを常にチェックしやすい体制が整備可能です。
就活関連のイベント・セミナーを設定しやすい
採用管理システムを活用することで、就活関連のイベント・セミナーを設定しやすいメリットもあります。
新卒の選考早期化が進んでいる今、学生との接点をいかに早く持つかが重視されています。
しかし現状の選考フローに加えて就活関連のイベントを組むとなると、採用担当者の負担が重くなります。
採用管理システムには選考の管理をスムーズに進めるためだけではなく、イベントの設定や参加者の管理をスムーズに対応するシステムも紐づいています。
就活関連のイベント・セミナーを今後拡大していく予定であれば、活用するメリットは大きいといえるでしょう。
採用管理システム(ATS)を選ぶポイント
採用管理システムを選ぶ際には、企業のニーズに合った適切なシステムを選定することが重要です。
以下に、採用管理システムを選ぶ際のポイントを詳しく説明します。
料金体系が自社の予算内に収まっているか
採用管理システムの導入にあたっては、まず料金体系が自社の予算に合っているかを確認することが重要です。
システムには初期費用、月額料金、機能ごとの追加料金など、さまざまな費用が発生する場合があります。
企業の予算に応じて、必要な機能を備えた最適なプランを選びましょう。
また、長期的な利用を考慮したコストパフォーマンスも重要です。
実際に活用して、見合った評価が得られているかをモニタリングして、コストパフォーマンスが高いかもチェックしておきましょう。
データ分析機能が充実しているか
採用管理システムを選ぶ際には、システム自体にデータ分析機能が充実しているかを確認しましょう。
採用管理システムにおけるデータ分析機能の充実度を確認することは、採用プロセスの改善に直結します。
応募者数や選考通過率、内定承諾率などのデータを可視化し、分析することで、採用戦略の改善点を明確にすることが可能です。
各歩留まりの進捗状況や昨対比の数値を比較することで、次年度の選考活動の改善に役立てられます。
主に以下の機能をチェックしておくといいでしょう。
・採用にかかったコスト
・学生の行動変化
・選考過程の進捗率
・採用サイトのアクセス数
操作しやすいか
採用管理システムは、採用担当者が日常的に使用するツールです。
そのため、操作性が良く、直感的に使えることが重要です。
複雑な操作が必要なシステムは、導入後のトレーニングやサポートが必要になるため、業務効率を下げる可能性があります。
デモ版やトライアルを利用して、実際の使用感を確認することをお勧めします。
既存の利用媒体との互換性があるか
企業が既に使用している他のシステムやツールとの互換性も重要なポイントです。
例えば、既存の人事管理システムやメールシステム、カレンダーアプリなどと連携できるかどうかを確認することで、情報の一元管理が可能になり、業務効率が向上します。
既存利用媒体との互換性が悪いと、導入するまでに工数がかかり逆に効率が悪くなる可能性もあります。
採用管理で一部別のシステムを利用している場合は、、各種採用サイトと互換性を重視しておくといいでしょう。
情報流出の危険性がないか
採用管理システムには、応募者の個人情報や企業の機密情報が多く含まれます。
そのため、情報セキュリティは非常に重要です。システムがどのようなセキュリティ対策を講じているか、データの暗号化やアクセス制御の仕組みがしっかりしているかを確認する必要があります。
また、システム提供会社の信頼性や過去のセキュリティインシデントの有無についても調査しておくと安心です。
採用管理システム上では学生や応募者の個人情報が入っているため、流出すると企業の信用問題にかかわります。
採用管理システム(ATS)を採用活動で活用する方法
採用管理システムを効果的に活用することで、採用活動の効率と精度を大幅に向上させることができます。
以下に、採用管理システムを活用する具体的な方法を説明します。
求人案件や求職者方法を担当者間でチェックできる体制にする
採用管理システムを活用することで、求人案件や求職者情報を担当者間でリアルタイムに共有できます。
これにより、各担当者は最新の情報に基づいて判断を下すことができ、選考フローを担当者間でも透明性を持って対応できます。
システム内でコメントやフィードバックを共有する機能を活用し、チーム全体で情報を一元管理する体制を整えましょう。
選考状況を細かく記載し情報を共有する
候補者の選考状況を詳細に記録し、担当者間で共有することは非常に重要です。
採用管理システムを使えば、候補者ごとに選考ステージや評価、面接結果などを簡単に記録できます。
これにより、選考の進捗を正確に把握し、次のステップに迅速に進むことが可能になります。
また、情報共有が円滑に行われることで、選考の一貫性を保つことができます。
導入前にトライアルを使用する
採用管理システムの導入前に、トライアルを利用して実際の操作感を確認することをお勧めします。
トライアル期間中に、システムの機能や使い勝手を実際に試すことで、自社のニーズに合ったシステムであるかを見極めることができます。
また、トライアルを通じて、導入後の業務フローをシミュレーションし、必要な調整を行うことができます。
アンケート機能を活用して学生の声を集める
採用管理システムには、アンケート機能を備えているものが多くあります。
この機能を活用することで、選考プロセスを通じて学生からフィードバックを集めることができます。
学生の声を反映することで、選考プロセスや企業の魅力をさらに向上させることができます。
また、フィードバックを分析することで、採用活動の改善点を見つけることが可能です。
採用管理システム(ATS)を導入して新卒採用の効率化を進めよう
採用管理システムを活用することで、人事側でも採用フローの透明化が可能です。
メールの送信からステータス管理まで一元管理できるだけではなく、属人化しやすい作業もルール化しやすいメリットがあります。
管理体制の構築の工数などデメリットはありますが、メリットと勘案して自社内で検討してみましょう。