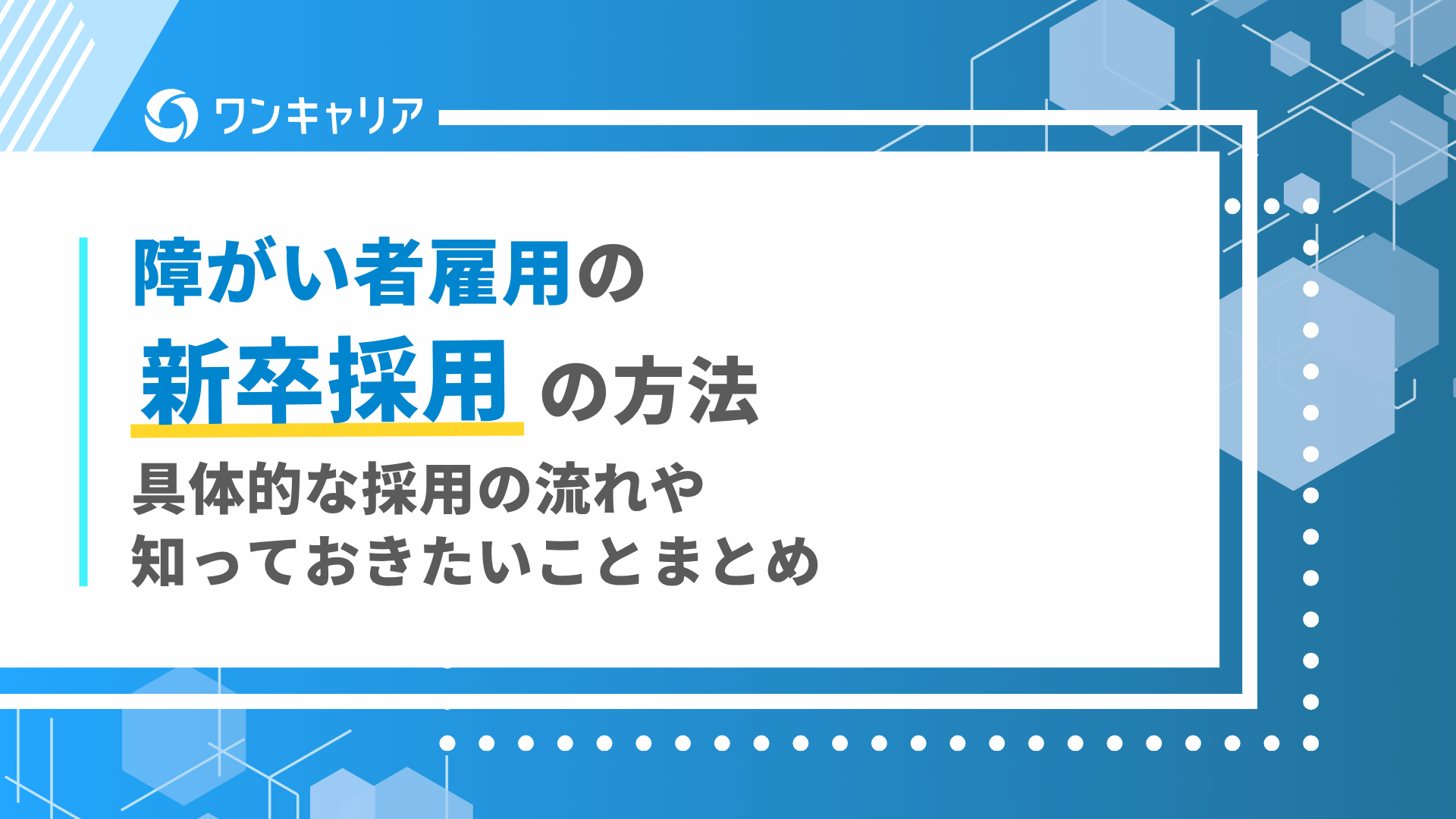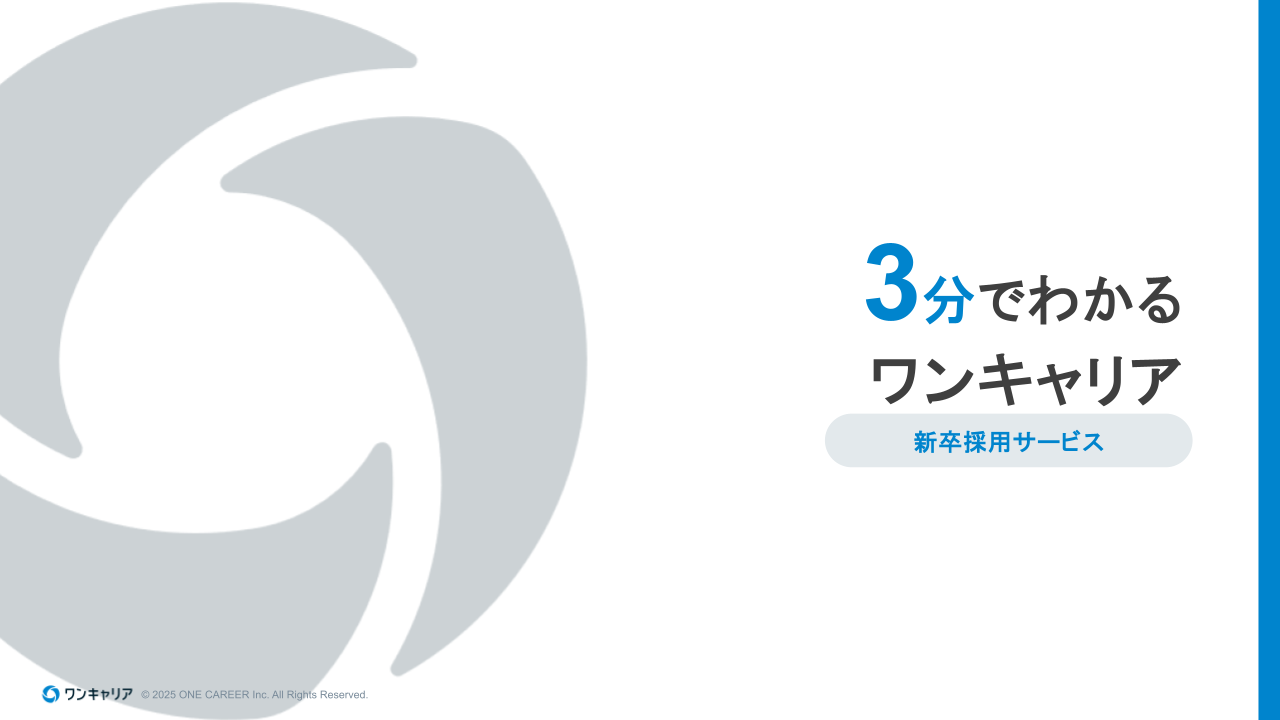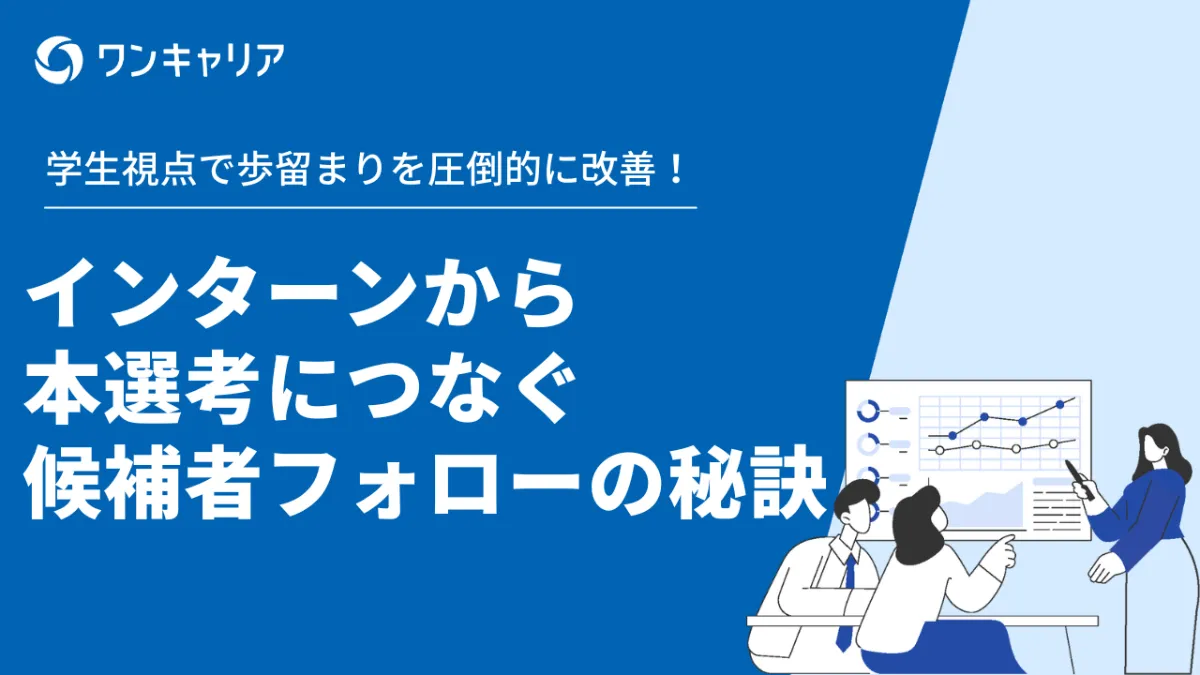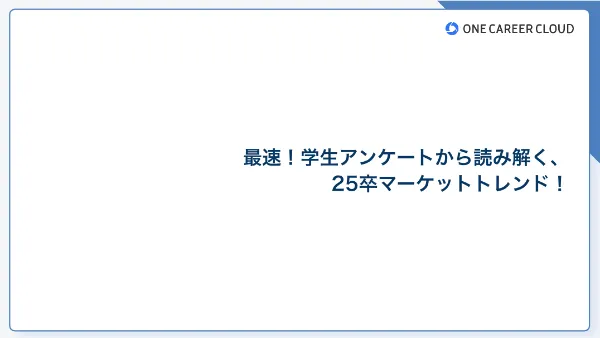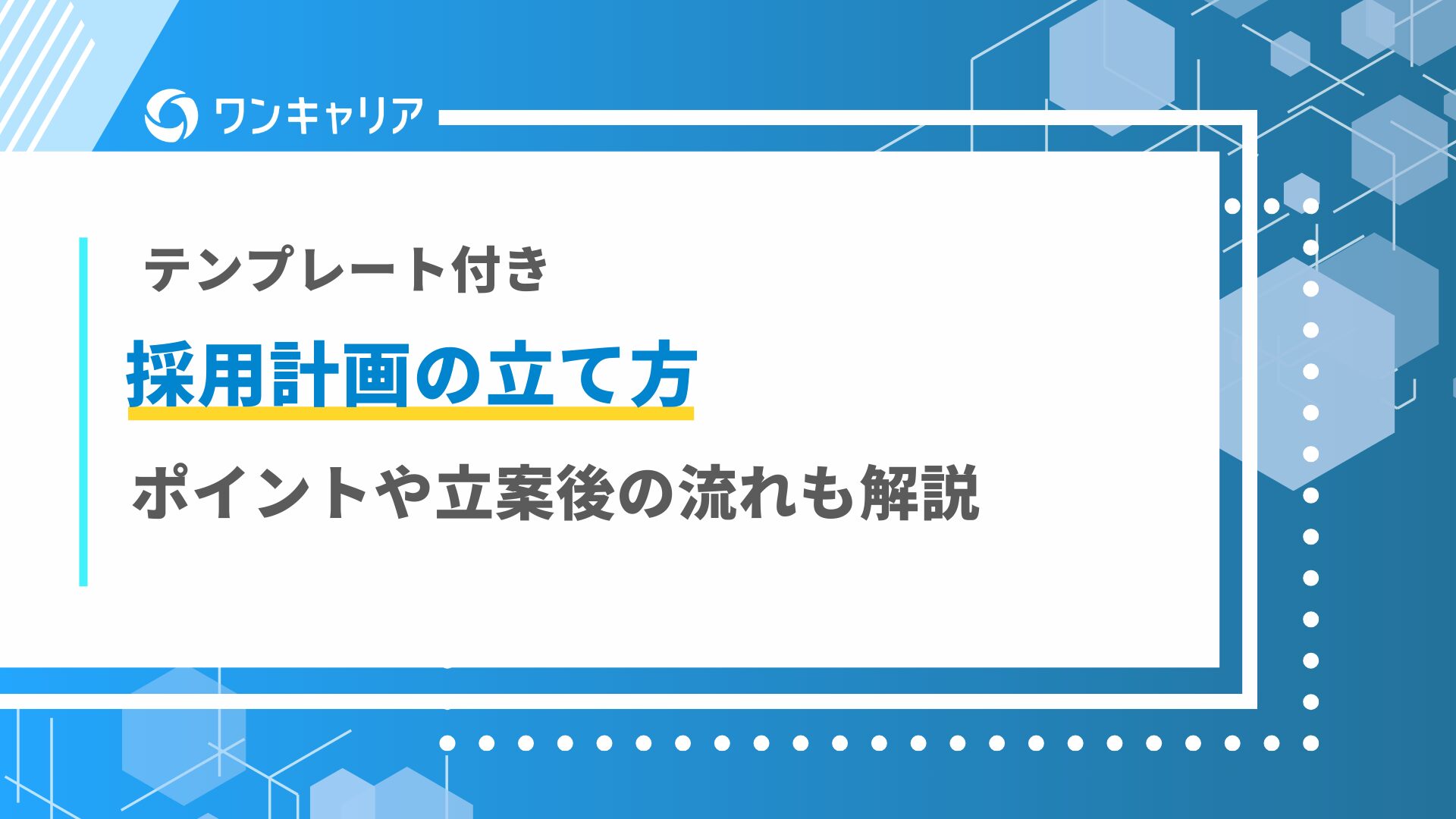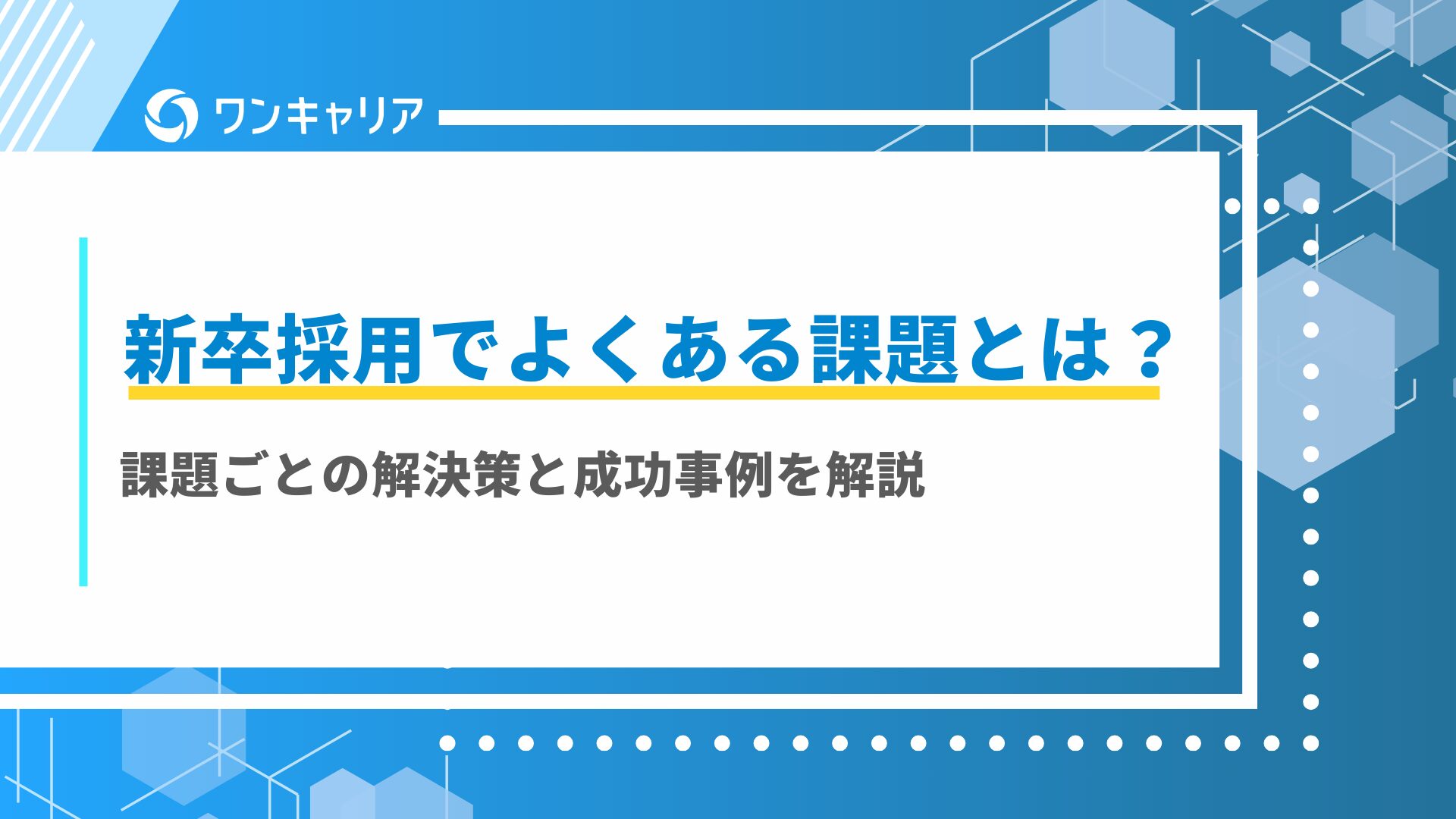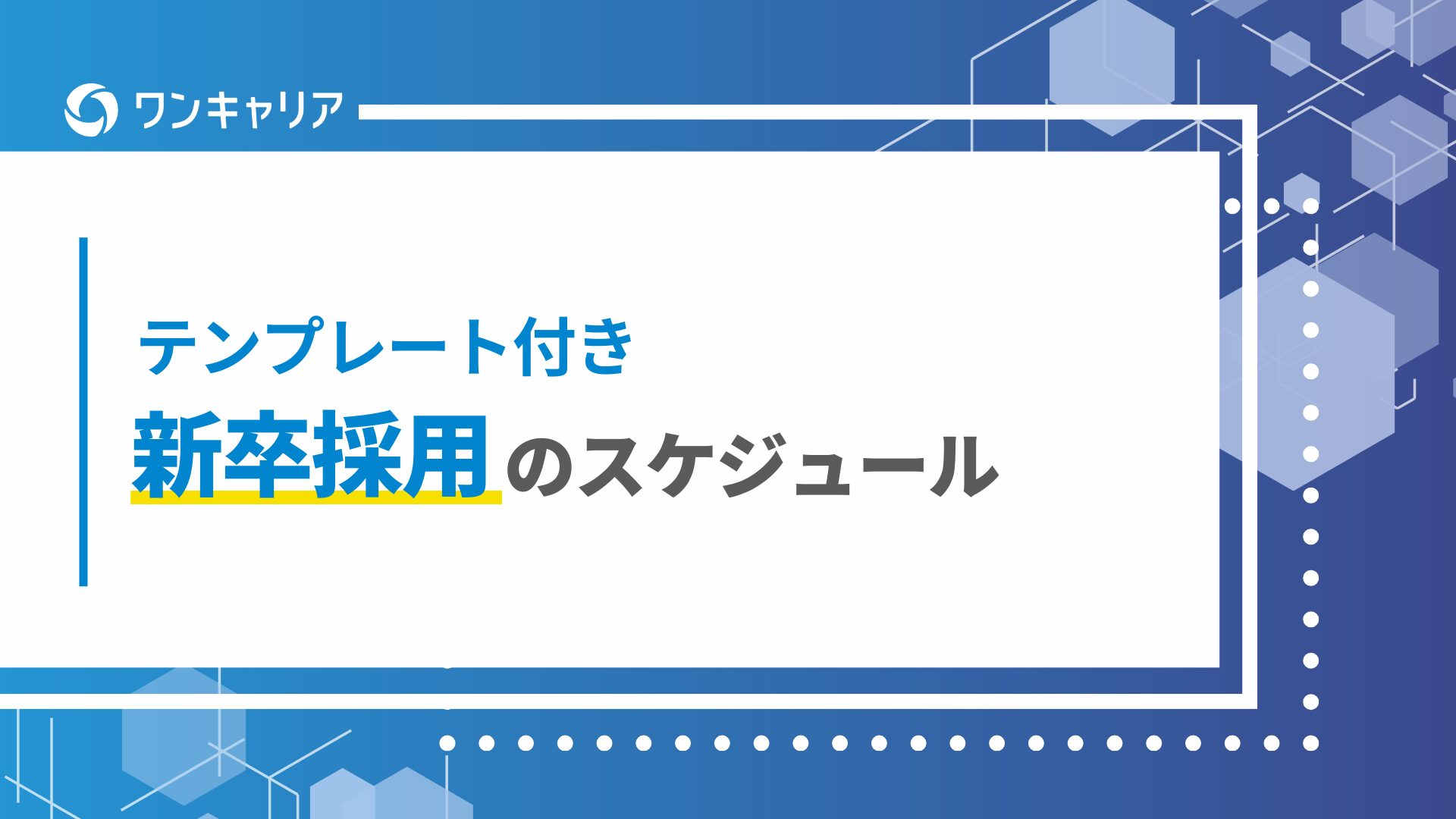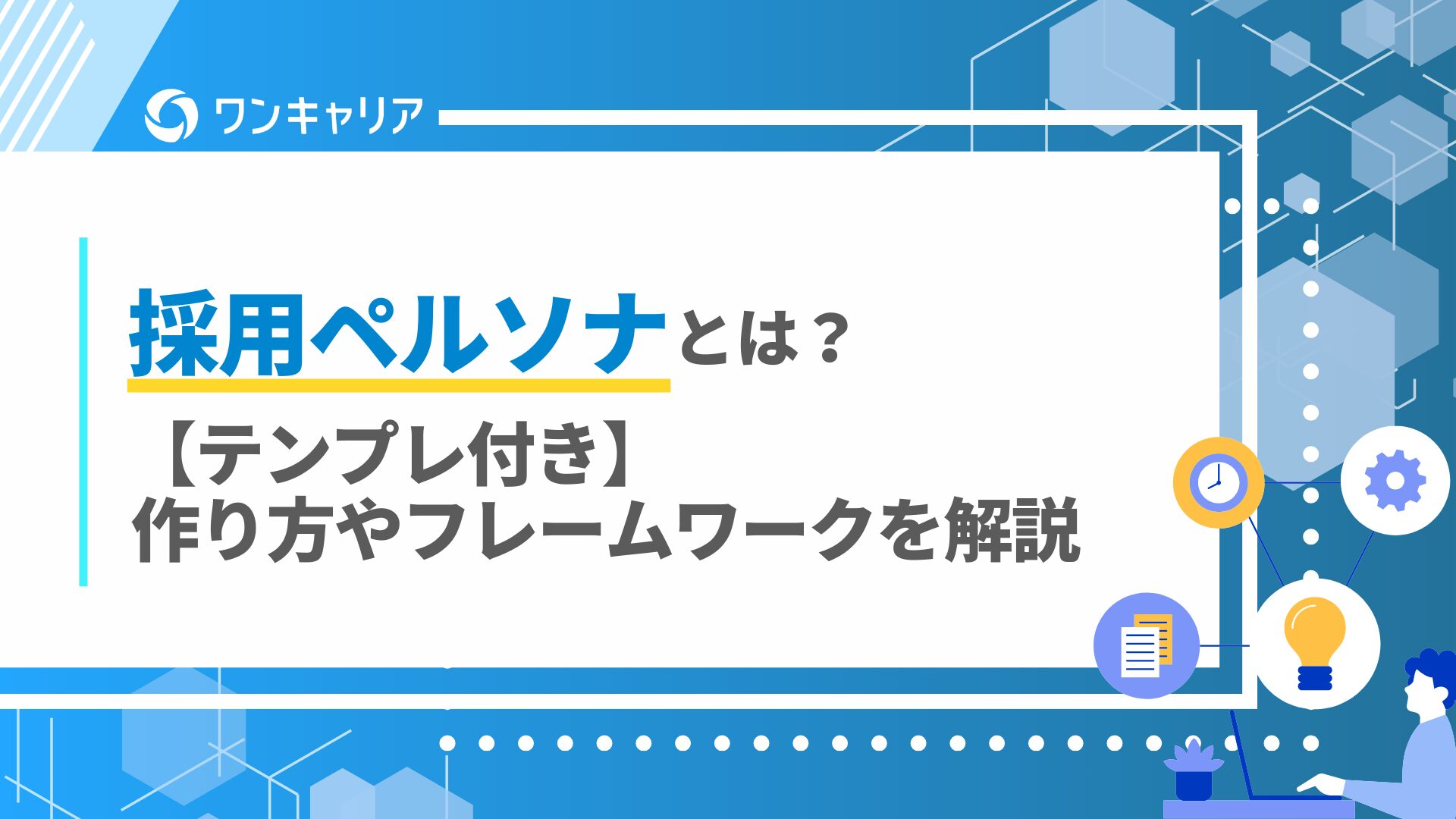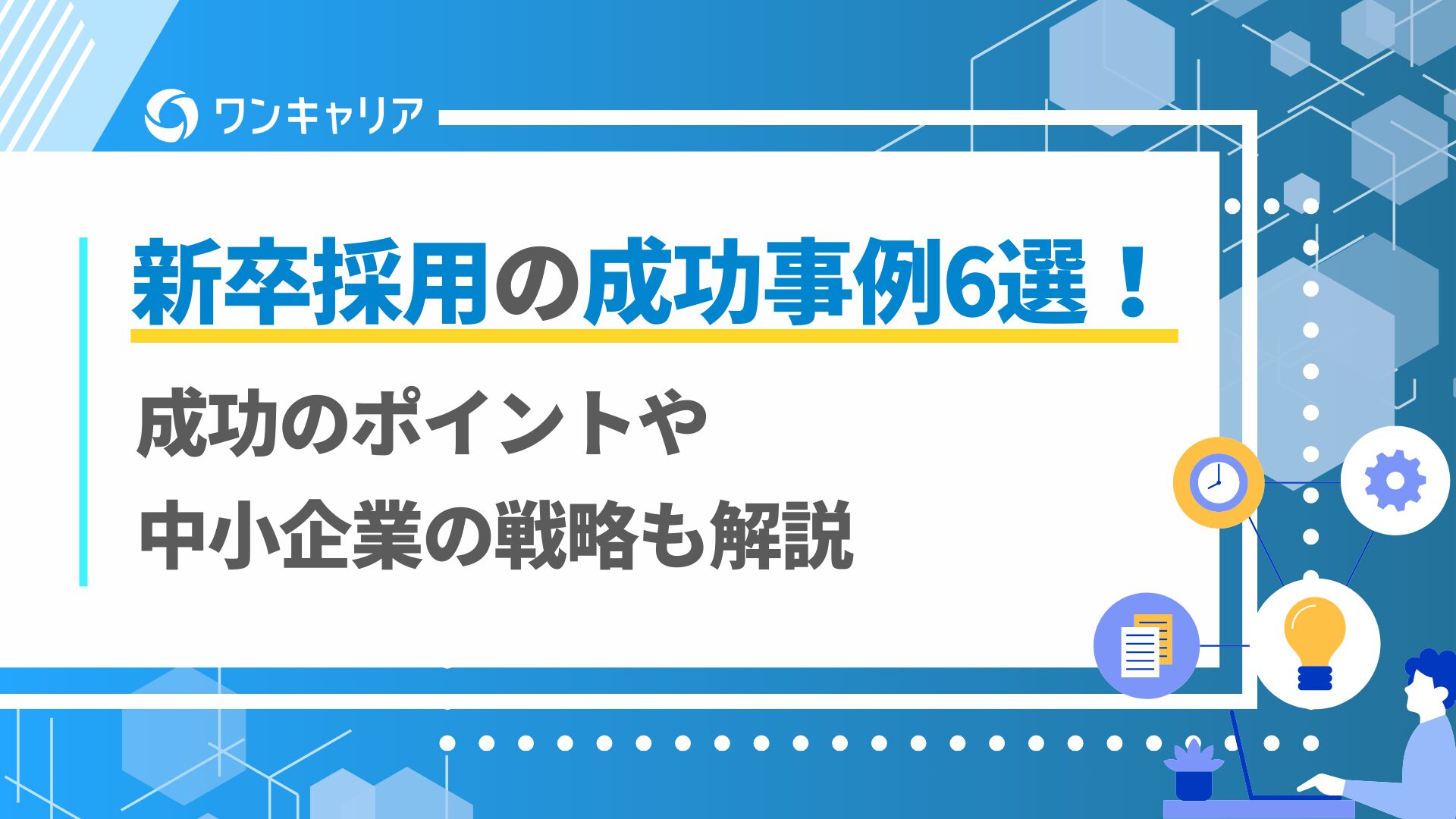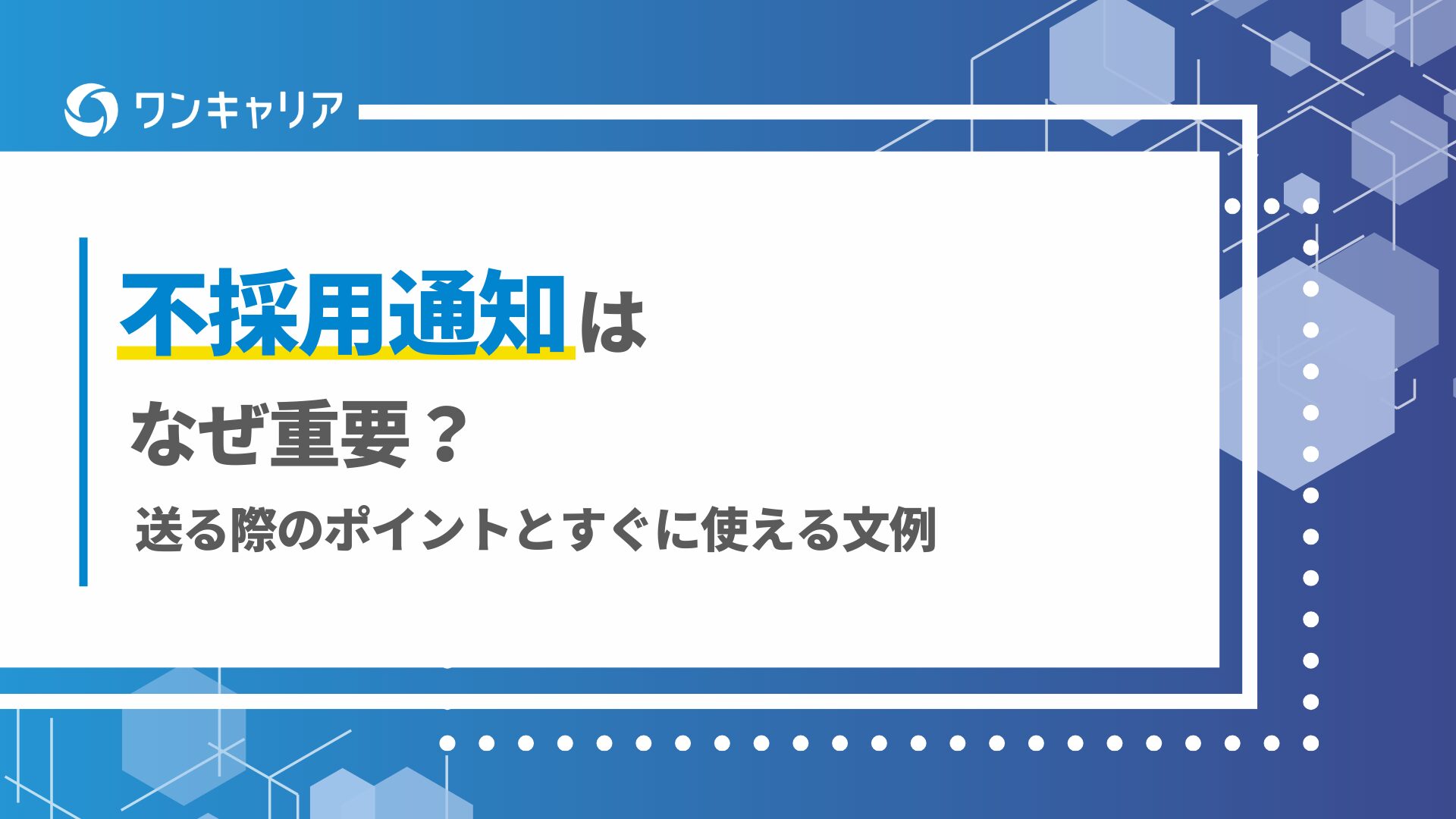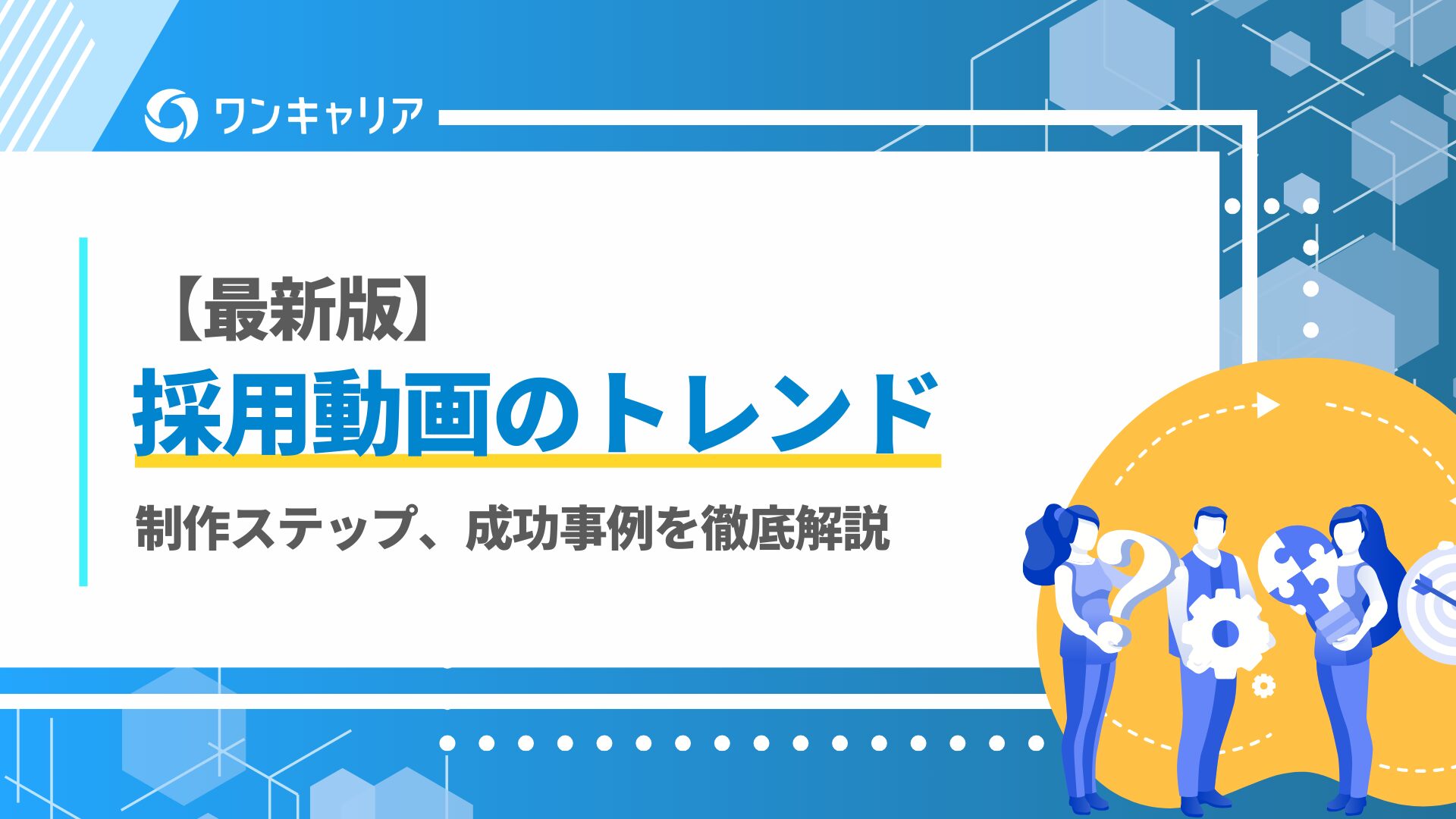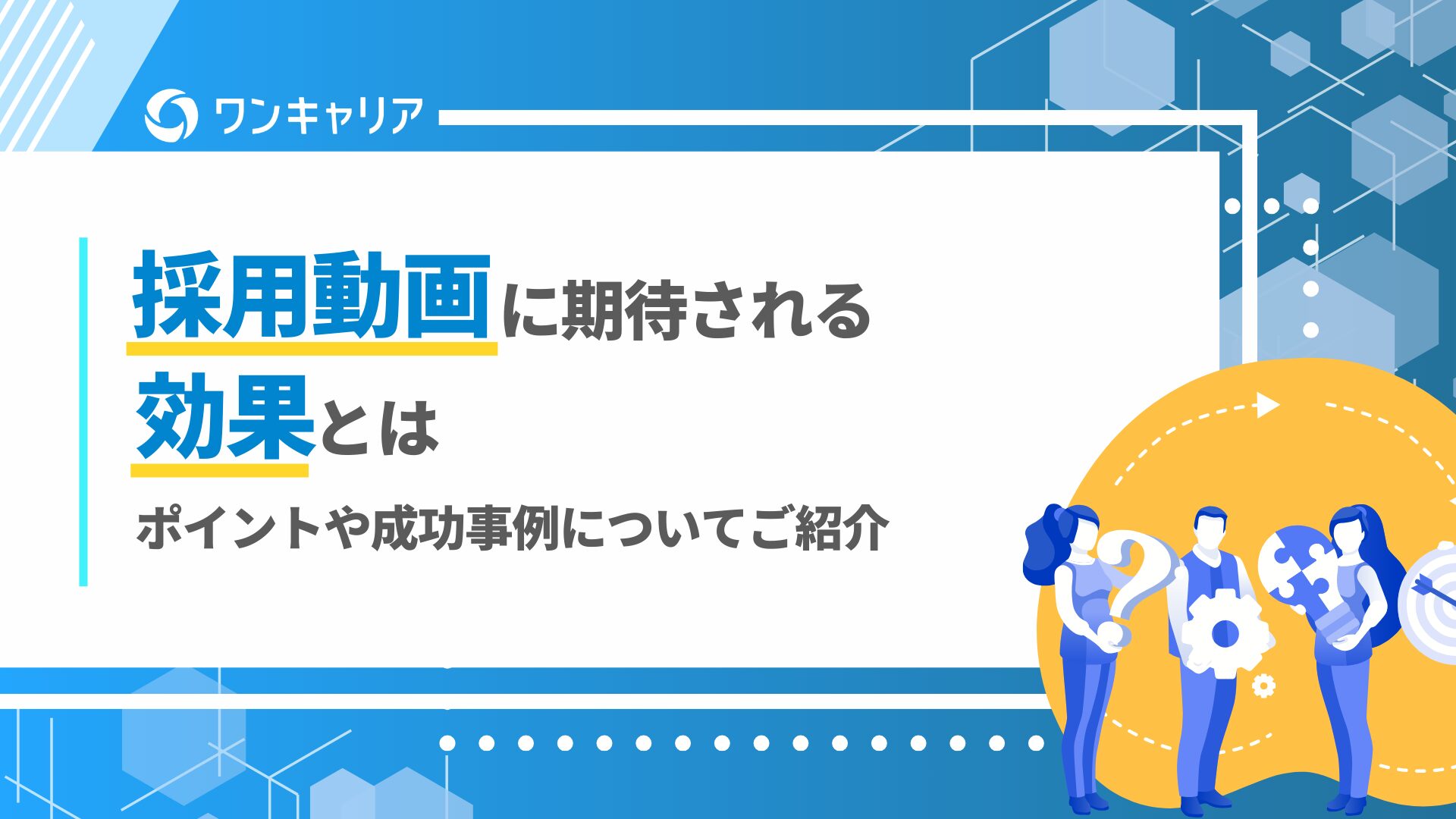目次
障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられたことを踏まえ、新卒での障害者雇用を進める企業が増えています。 実際に雇用する際には、合理的な配慮を踏まえたり、ほかの新卒生と異なる基準を設けたりする必要があります。 この記事では障がい者雇用での新卒採用の方法から具体的な採用の流れまで解説していきます。
障がい者雇用に関する前提知識
直近で障がい者雇用の制度が変更になったことや、世の中の変化もあることから、障がい者雇用に関する前提知識はある程度把握しておくべきです。
障がい者雇用に関する前提知識を以下で紹介していきます。
企業の障がい者法定雇用率が引き上げられた
これまで障がい者の民間の法定雇用率は2.3%でしたが、令和5年度では2.5%、令和8年度には2.7%まで段階的に引き上げられることが決定しています。
この制度は従業員数に応じた割合の人数を雇用する必要があり、違反した場合ハローワークから行政指導を受けることになります。
すべての民間企業に適用されるわけではなく、43.5人以上の従業員を雇用している企業が対象になります。
条件を満たしている企業が障がい者法定雇用率を下回った場合、不足分一人につき月額5万円の納付金を支払うことになりますので注意が必要です。
参考:厚生労働省公式HP
就職活動のスケジュールは一般の新卒と同様
障がい者雇用で、就職活動のスケジュールは一般の大学生と同様です。
障害のある学生の中でも一般募集枠で採用に参加しているケースもあり、別の選考スケジュールで進行することは少ないです。
選考スケジュールを障がい者雇用枠の学生に向けて別途採用スケジュールを立てず、従来の就職活動のスケジュールと同様に進行可能です。
障がい者雇用の実施状況
障がい者雇用の実施状況は、企業の規模や業種によって異なりますが、全体としては徐々に改善されつつあります。
多くの企業が障がい者の雇用に積極的に取り組んでおり、特に大企業では法定雇用率を上回る雇用を実現している例も見られます。
しかし、中小企業では、法定雇用率を達成することが難しいケースも少なくありません。
障がい者を受け入れるための職場環境の整備や、適切な職務の提供が課題となっています。
政府や自治体は、企業が障がい者を雇用しやすくするための支援策を講じており、企業はこれらの支援を活用しながら、障がい者雇用の促進に努める必要があります。
障がい者雇用における新卒採用の流れ
障がい者雇用における新卒採用は、さまざまな人材を自社で迎え入れる一つの手段です。
障がい者の新卒採用は一般的な新卒採用と似ている部分もありますが、特に障がい者に対する配慮が求められる点が特徴です。
以下に、具体的な流れを説明します。
採用計画を策定
まず、企業は障がい者雇用に関する明確な採用計画を策定します。
この計画には、採用する人数、対象となる障がいの種類、配属予定の部署や職種などを含めます。
また、採用の目的や期待する役割を明確にし、社内での理解を深めます。採用計画は、企業の方針や事業戦略に基づき、現実的かつ実行可能なものとすることが重要です。
障がい者雇用枠の募集を開始
採用計画が整ったら、次に障がい者雇用枠の募集を開始します。
この段階では、求人情報をわかりやすく明示し、障がい者が安心して応募できる環境を整えることが大切です。
求人情報には、職務内容、求めるスキル、配慮が必要な事項などを具体的に記載します。
また、障がい者雇用に特化した求人媒体や支援機関と連携することで、より多くの候補者にアプローチできます。
選考・面接を行う
募集を開始した後は、応募者の選考と面接を行います。
障がい者の特性やニーズを理解し、公平かつ公正な評価を心がけます。
面接時には、応募者がリラックスして話せるような雰囲気を作り、必要に応じて合理的配慮を提供します。
例えば、面接時間や場所の調整、コミュニケーション方法の工夫などが考えられます。
選考基準は、障がいの有無に関わらず、職務遂行能力を重視することが重要です。
内定後受け入れ準備を進める
内定が決まったら、受け入れ準備を進めます。
この段階では、障がい者がスムーズに職場に適応できるよう、必要な配慮やサポート体制を整えます。
具体的には、職場環境の整備、配属先の従業員への障がい理解の促進、必要な合理的配慮の確認などがあります。
また、内定者とのコミュニケーションを密にし、入社前に不安を解消するためのサポートを行います。
これにより、新入社員が安心して業務を開始できるようになります。
新卒採用における障がい者雇用と一般雇用の違い
新卒採用における障がい者雇用と一般雇用の違いは、主に採用プロセスや職場環境における配慮にあります。
障がい者雇用では、個々の障がい特性に応じた合理的配慮の提供が求められ、企業はより柔軟な対応が必要です。
以下に、具体的な違いを説明します。
合理的配慮が必要なケースがある
障がい者雇用では、応募者や新入社員が能力を最大限に発揮できるよう、合理的配慮を提供することが重要です。
合理的配慮とは、障がい者が他の従業員と同等に働く機会を得られるようにするための調整や変更を指します。
具体的には、面接時のサポート、職場のバリアフリー化、業務内容の調整、勤務時間の柔軟化などが含まれます。
これにより、障がい者が安心して働ける環境を整えることが可能になります。
支援機関との連携が必要
障がい者雇用を成功させるためには、支援機関との連携が不可欠です。
ハローワークや障がい者就業・生活支援センター、特別支援学校などの支援機関と協力することで、適切な人材の紹介や採用プロセスのサポートを受けることができます。
これらの機関は、障がい者の特性に応じた職場環境の整備や、企業が直面する課題に対するアドバイスを提供してくれるため、積極的に活用することが推奨されます。
社内や配属先への情報共有の重要性が高い
障がい者を新たに迎え入れる際には、社内や配属先への情報共有が重要です。
障がい者が働きやすい環境を整えるためには、同僚や上司がその特性や必要な配慮について理解しておくことが不可欠です。
情報共有は、プライバシーに配慮しつつ、業務に影響を及ぼす可能性のある情報に限定して行います。
これにより、職場全体が協力して障がい者をサポートする体制を築くことができます。
情報共有は、企業の文化や価値観を反映した形で行い、全従業員が障がい者雇用の意義を理解することが求められます。
障がい者雇用の新卒採用で確認するべき事項
障がい者雇用の新卒採用においては、採用プロセスの中でいくつかの重要な事項を確認することが求められます。
これにより、採用された障がい者が職場で安心して働ける環境を整えることができます。
以下に、確認すべき主な事項を説明します。
発生する症状
まず、候補者が抱える障がいの特性や、仕事に影響を及ぼす可能性のある症状について確認します。
具体的には、どのような状況で症状が発生するのか、どの程度の頻度で発生するのか、業務にどのような影響があるのかを理解することが重要です。
これにより、職場での適切な配慮や対応策を考えることができます。
服薬の状況
次に、候補者が服薬している場合、その状況について確認します。
服薬が業務に影響を与える可能性があるかどうか、服薬のタイミングや副作用があるかどうかを把握することで、仕事中の配慮が必要かどうかを判断します。
例えば、服薬のために定期的な休憩が必要であれば、それを考慮した勤務計画を立てることが求められます。
通院の状況
候補者が定期的に通院している場合、その頻度や時間帯についても確認が必要です。
通院が業務時間に影響を及ぼす場合、柔軟な勤務時間の設定や、通院に伴う業務の調整が必要となることがあります。
これにより、候補者が健康を維持しながら安心して働ける環境を提供することができます。
必要とする合理的配慮
最後に、候補者が職場で必要とする合理的配慮について確認します。
合理的配慮とは、障がい者が職務を遂行する上で必要とする環境の調整やサポートを指します。
具体的には、職場環境のバリアフリー化、特別な機器やソフトウェアの提供、業務内容の調整、コミュニケーション方法の工夫などが含まれます。
これらの配慮を事前に確認することで、入社後のスムーズな職場適応を支援します。
障がい者雇用の新卒採用で押さえるべきポイント
障がい者雇用の新卒採用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
これらのポイントを理解し、実践することで、企業は多様な人材を受け入れ、活用することができる環境を整えることができます。
母集団形成の方法を押さえる
母集団形成は、採用活動の第一歩となる重要なプロセスです。
障がい者雇用の場合、特定の支援機関や学校、職業訓練施設との連携を強化することで、適切な人材のプールを形成できます。
また、インターネットやSNSを活用した情報発信、障がい者向けの就職イベントへの参加も効果的です。
これにより、企業の採用活動を広く周知し、障がいを持つ求職者との接点を増やすことができます。
自社に適した採用手法を選ぶ
採用手法は、企業の特性や求める人材像に応じて柔軟に選択することが重要です。
一般的な筆記試験や面接だけでなく、実技試験やグループディスカッション、インターンシップ制度など、多様な手法を検討し、候補者の能力や適性を多角的に評価できるようにします。
また、障がい者の特性に配慮した面接形式や評価基準を設定することも重要です。
職場見学の機会を設ける
職場見学は、候補者が実際の業務環境や職場の雰囲気を直接感じ取ることができる貴重な機会です。
見学を通じて、候補者は自分がその職場で働く姿を具体的にイメージでき、企業も候補者の適応性を確認することができます。
見学時には、業務内容の説明や社員との交流の場を設けることで、学生がより職場に対する理解を深められます。
自社理解を深めることで選考に進んでくれる可能性も高くなります。
内定後も定期的にコミュニケーションをとる
内定後から入社までの期間は、候補者にとって不安が大きい時期です。
この期間に定期的なコミュニケーションを取ることで、候補者の不安を軽減し、入社後のスムーズな定着を促進します。
具体的には、メールや電話でのフォローアップ、オリエンテーションや事前研修の実施などが考えられます。
必要に応じて支援機関や専門家へ相談する
障がい者雇用においては、企業が単独で対応するのが難しいケースもあります。
そのような場合には、支援機関や専門家の助言を受けることが重要です。
これにより、適切な配慮の提供や職場環境の改善が可能となり、障がい者が安心して働ける職場を実現することができます。
障がい者雇用の新卒採用の条件を把握して手続きを進めよう
障がい者雇用の新卒採用を成功させるには、法令や制度を理解し、具体的な採用計画を立て、職場環境を整備します。
内定後は定期的なフォローアップを行い、必要に応じて専門家や支援機関と連携しましょう。
選考過程を整えてぜひ採用の幅を拡大してみてください。