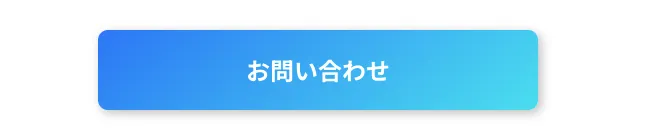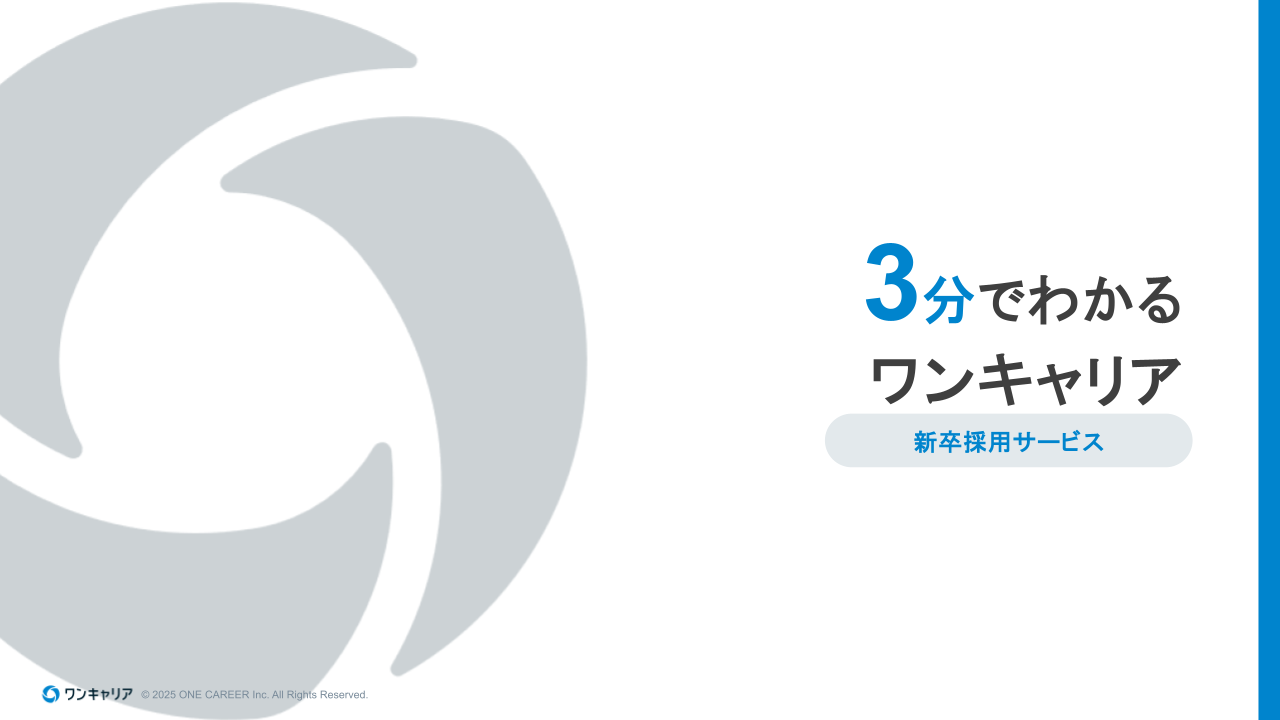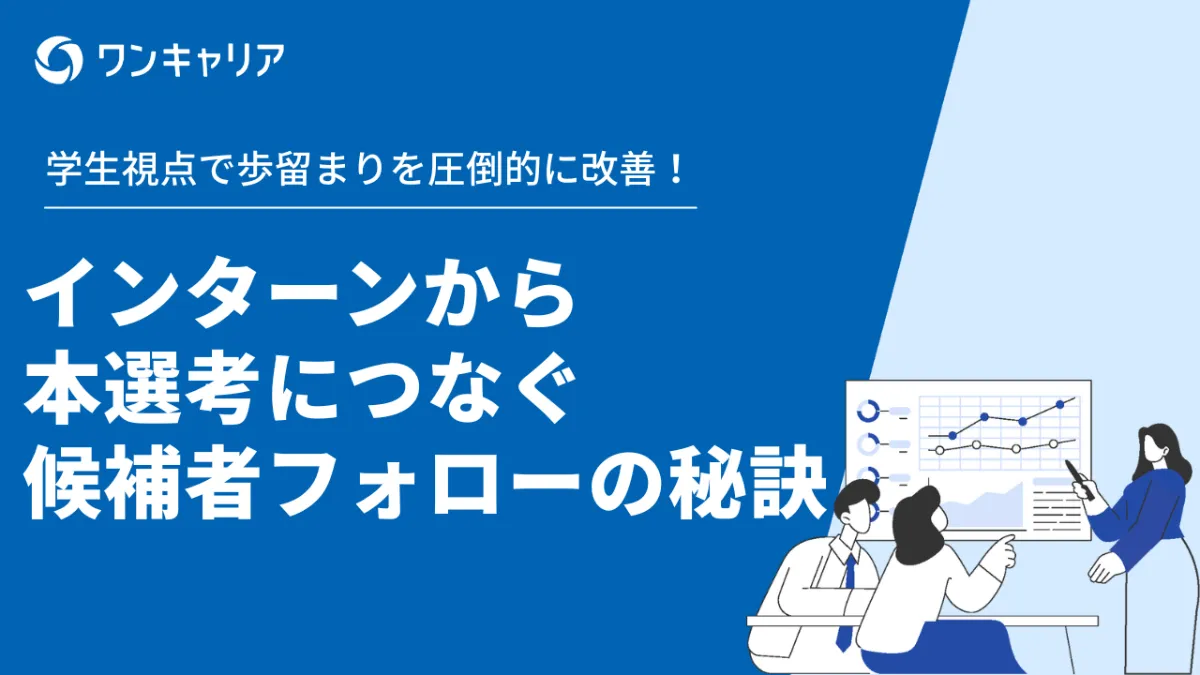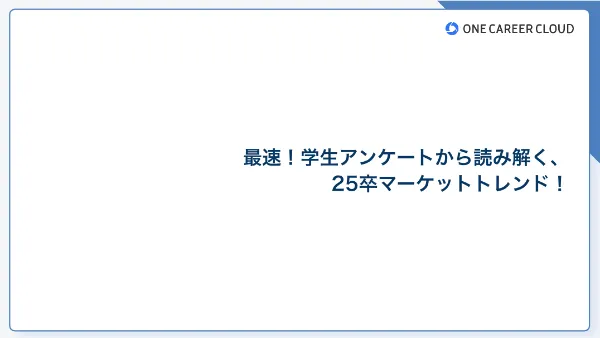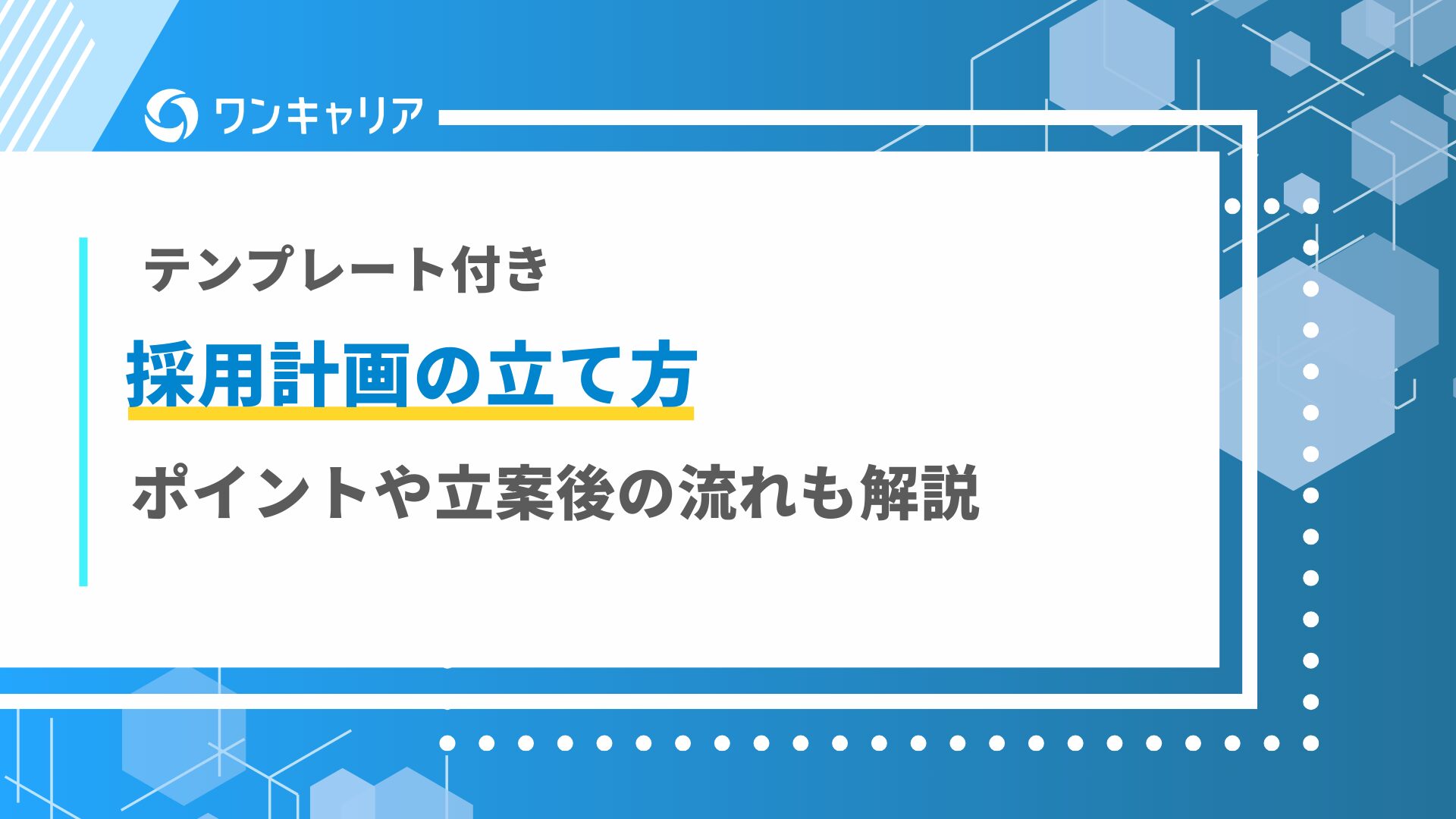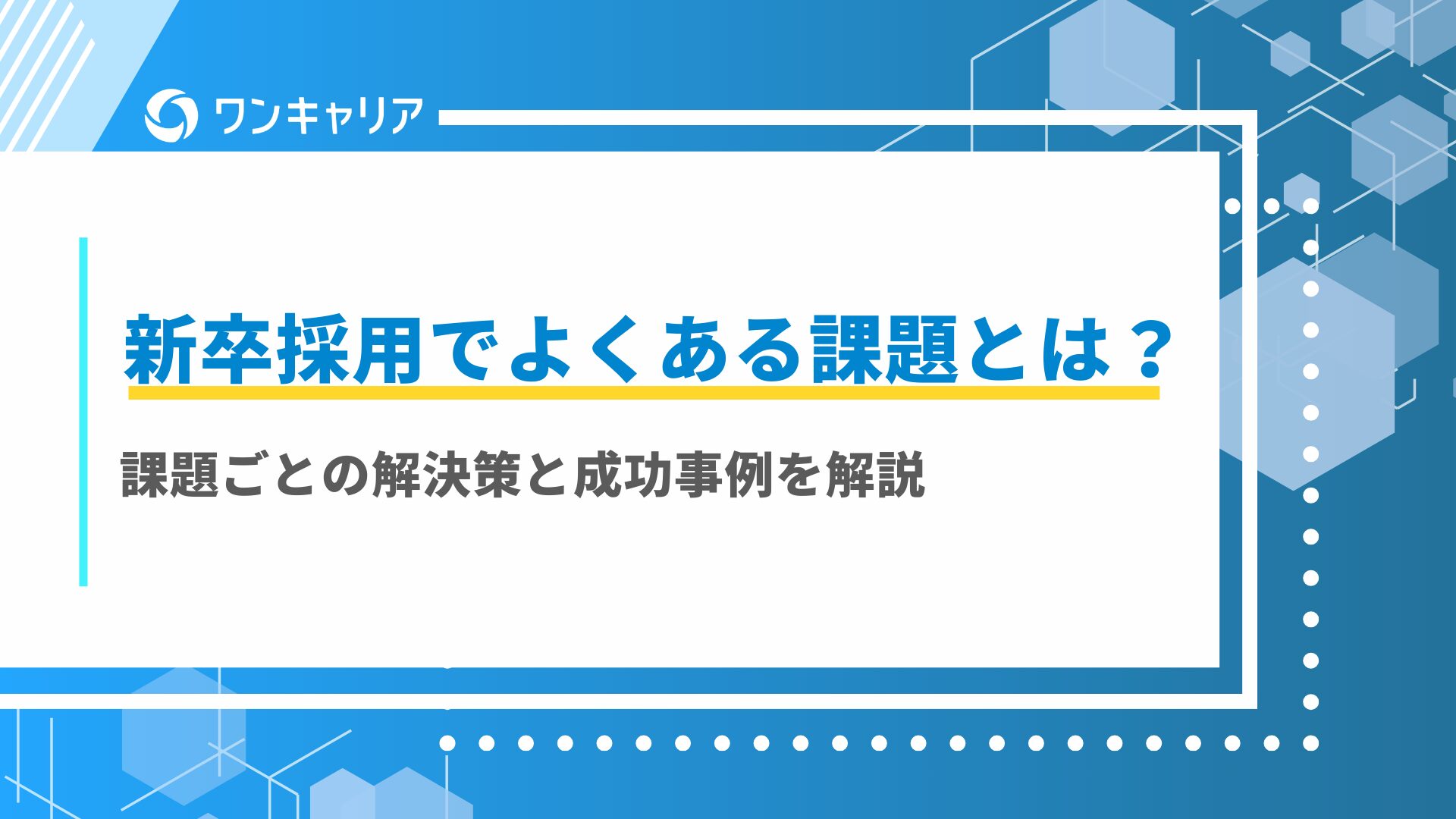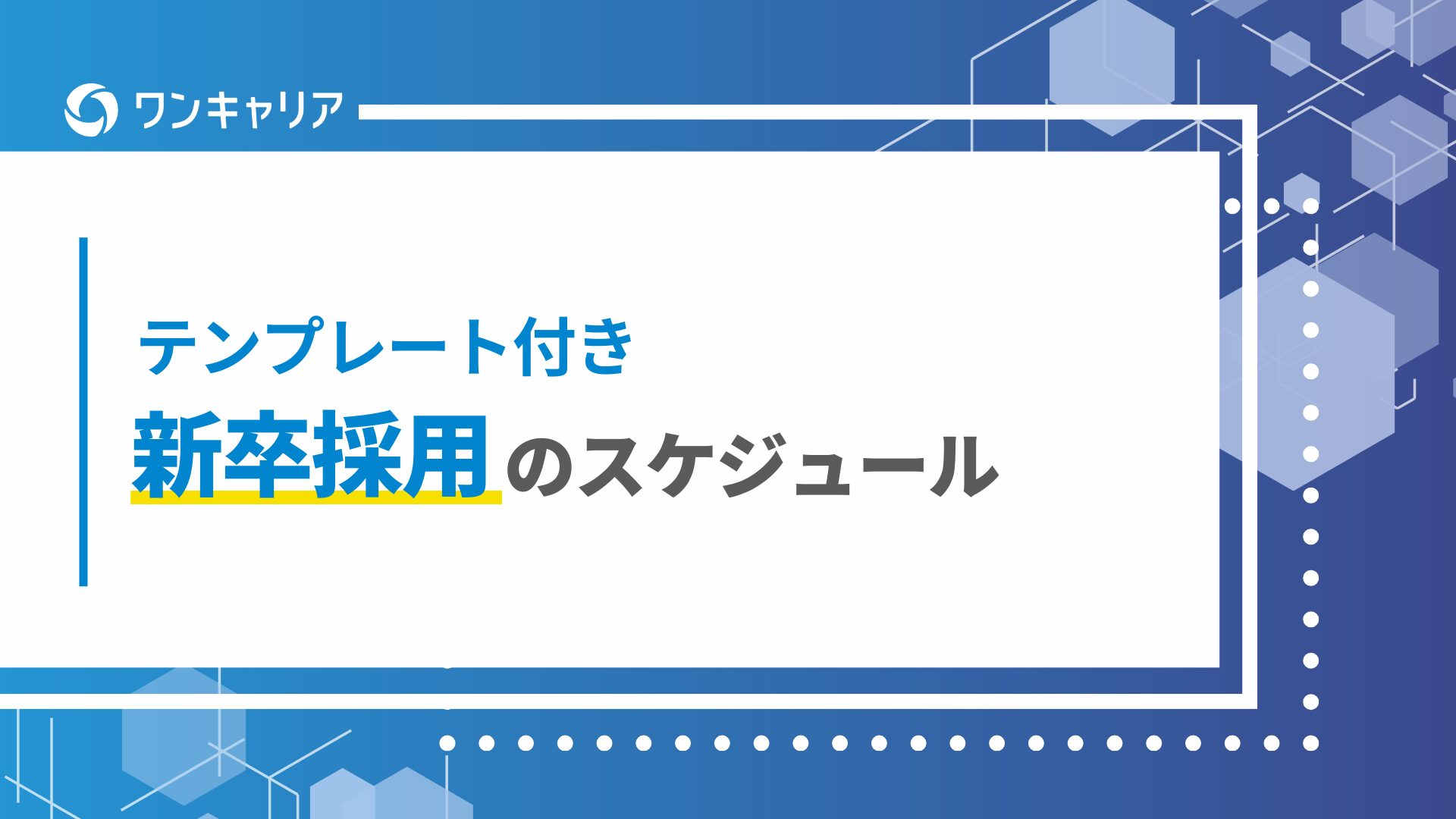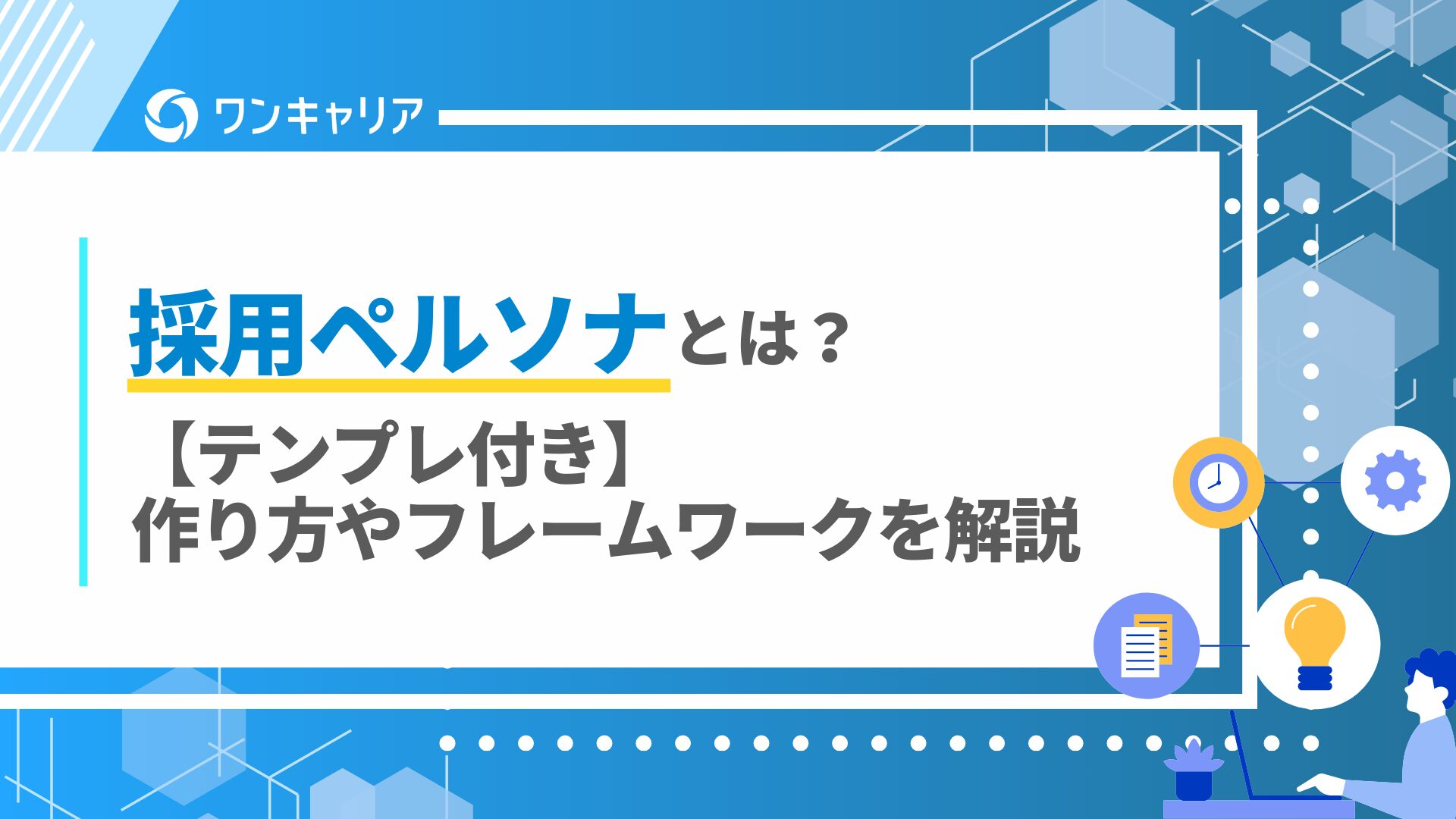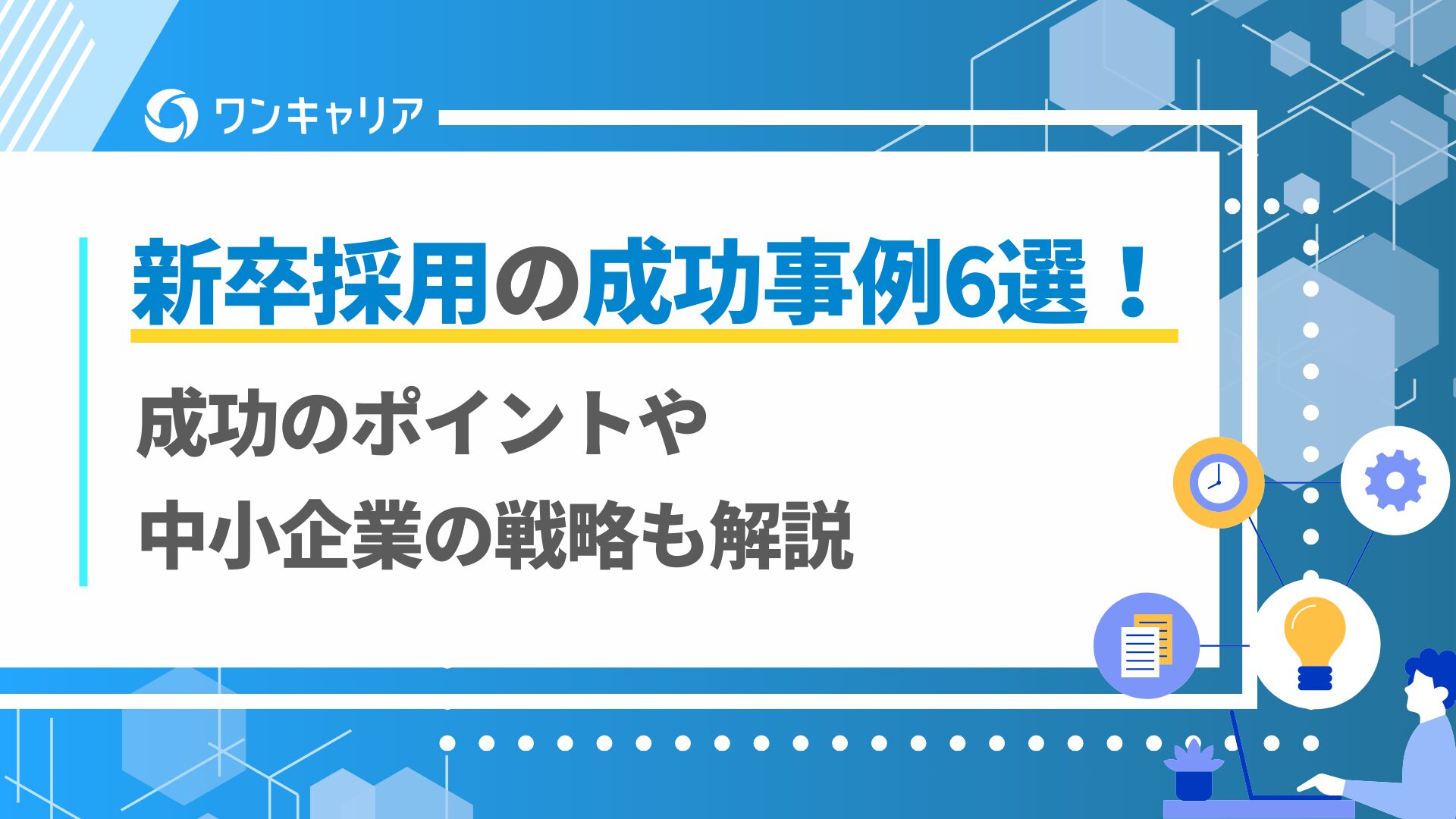目次
競争が激化する新卒採用市場で成果を上げるために、ダイレクトリクルーティングやSNS採用など、企業から学生へアプローチする攻めの採用手法に注目が集まっています。しかし、ただ従来の採用方法から乗り換えるだけでは、自社が求める人材へリーチするのは難しいでしょう。そこで重要になるのが新卒採用戦略です。本記事では、新卒採用の戦略を見直すべき理由や立案のメリット、ポイントについて解説します。
新卒の採用戦略を見直すべき理由

新卒の採用戦略立案の重要性が高まっています。採用が激化・早期化するなか、企業は就活生から選ばれる立場にあるためです。
また、求める人物像(ペルソナ)が明確になっていないと、採用後にミスマッチが生じて離職するおそれもあります。こちらでは、新卒の採用戦略を見直すべき理由をお伝えします。
学生優位の売り手市場が続いているため
現在の採用市場は、労働人口の減少により人手不足が加速しており、売り手(学生)が有利な傾向にあります。求人は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で一時落ち込んだものの、大手企業を中心に回復しつつあります。ただし、一部大企業における採用市場は買い手有利で応募が集まっている一方で、中小企業には人が流れてこない状況です。*
このような事態を乗り切るには、採用戦略の策定を通して新卒採用の方向性を確認し、必要とする人材へ適切にアプローチすることが求められます。
※第38回ワークス大卒求人倍率調査(2022 年卒)
https://www.works-i.com/research/works-report/item/210427_kyujin.pdf
採用ルールが廃止されスケジュールが変化する可能性があるため
経団連は、自身による2021年卒以降の「就活ルール」を廃止しました。就活ルールとは、採用活動の日程などをルール化したものです。
就職活動が学生生活や学業を妨げないように、経団連が定めてきました。売り手市場が進むとスケジュールが早期化し問題となる可能性があるため、青田買いを抑制する目的で改定を繰り返してきた経緯があります。
経団連から引き継いだ政府は当面、これまでの採用スケジュールを踏襲すると発表しました。2023年度の採用スケジュールは3月広報解禁、6月選考解禁、10月内定解禁予定となっています。しかし、以降の採用スケジュールについては改めて見直されることとなりました。
今後の日程ルールは依然として不透明のため、新卒採用戦略を最適化して採用マーケティングやブランディングに活かす必要があります。
新卒採用戦略を立案するメリット

戦略的に人材採用を進めると、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。続いては、新卒採用戦略を立案するメリットを3つご紹介します。
母集団の形成で採用の確度を高められる
新卒採用戦略を最適化することで、自社の特徴や魅力、仕事内容などの情報を正確に伝えられるため、ニーズにマッチした母集団を形成しやすくなります。募集に対して十分な数の応募がない場合や自社が求める人材が候補者として現れない場合は、まず採用戦略を見直しましょう。
採用の成功は、安定した母集団形成が前提です。採用ターゲットである学生を多く集めることで、優秀な人材を採用できる可能性が高まります。新卒採用の戦略を立案する際は、目標内定数だけでなく、選考人数の目標を定めることが大切です。
採用スケジュールの最適化で内定辞退を抑えられる
新卒採用戦略の立案は、内定辞退者数の削減にも役立ちます。他社の採用スケジュールや学生の動向を把握することで、自社のスケジュールを最適化できるためです。内定者へのフォロー体制や入社後の環境整備を明確にでき、採用後の不安から内定辞退に至るケースも防止しやすくなります。特に優秀な人材は、競合他社から複数の内定をもらう可能性が高いため、対策は必須です。
また、内定辞退率を下げることができれば、求人媒体にかかる費用や面接官・人事担当者の人件費などの採用コストを削減できます。新たな人材を探す工数も必要なくなるため、採用担当者や人事部は、採用戦略の見直しや人材育成などに注力しやすくなります。
入社後のミスマッチによる離職を防げる
新卒採用戦略を見直すことで、自社が求める人材のイメージを明文化できるため、入社後のミスマッチを減らし、離職率の改善につながります。自社が求める人材かどうかの見極めや、学生のニーズに対する実現可能性の判断がしやすくなるでしょう。
新卒採用戦略を立案する際のポイント

最後に、新卒採用戦略を策定する際のポイントをご紹介します。自社の採用戦略を見直す場合は、以下の4つの視点を押さえておきましょう。
新卒の採用手法を段階別に見直す
母集団形成
母集団形成のフェーズでは、求職者との接触機会を増やし、入社意欲を高めて応募者を獲得するための施策を実施する必要があります。定量的な指標に基づき自社の弱みや課題をチェックし、適切な施策を再設定しましょう。指標の例にはエントリー数や説明会予約数・参加数、書類提出数、1次選考参加者数などがあります。
新卒求人・スカウトにお悩みの場合は、「ワンキャリア」がおすすめです。ワンキャリアは、月間訪問数150万人以上(2021年12⽉末時点での実績)の求人サイトを運営するサービスです。国内最大級の学生データベース(2022年卒の学生の2人に1人が利用)を活用したスカウトサービスを提供しており、登録学生に対して直接スカウトを送信できる攻めの採用活動ができます。
また、データに基づく採用計画を実現できる点も強みです。競合や自社、学生の動向をワンストップで比較・分析し、スムーズな意思決定につなげられます。
選考・面接
選考・面接は学生の見極めだけでなく、学生を自社に惹きつける場として活用できるよう見直すと良いでしょう。会社説明会から最終合格への移行率が低い場合は、自社の採用基準が高い可能性があります。
内定出し
内定はタイミングと条件が揃うことで承諾につながります。見直しが必要な部分の例としては、内定出しのタイミングやシチュエーション、他社の選考状況と志望度合い、承諾期限のスケジュールなどが挙げられます。
内定者フォロー
内定者フォローのステップでは、内定後のエンゲージメントを高める施策を検討しましょう。具体的には懇親会や研修の実施、フォローツールの導入、コミュニケーションボードの活用などの方法が効果的です。
また、現状のフォロー体制を見直す必要もあるでしょう。接触頻度や採用担当者およびアテンドする社員の適正、多様なコンテンツの提供などを見直し、内定者が改めて自社で働きたいと思える工夫をすることが重要です。
新卒の採用目的を明確化する
新卒採用戦略を立てる際は、自社にとって新卒採用がなぜ必要なのかを振り返ることも大切です。新卒採用の解像度が上がり、目的に沿った施策を実行できるようになります。目的を明確にしておくことで、新卒・中途採用に限らず、会社に必要な人材かを中長期的な経営戦略目線で把握しやすくなるメリットもあります。
求める人物像を最適化する
新卒採用戦略では、自社が求める人物像について具体的に見直し、最適化を行う必要があります。事業の拡大や創出において必要な人材を社内に確保し、事業計画や目標を達成するためです。入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
採用ブランディングを見直す
求める人材像に刺さるメッセージを作るためには、自社の採用ブランディングを見直し、改善することが大切です。自社の強みやアピールポイントが効果的に伝わることで、応募数および認知度向上につながります。
新卒採用の戦略を立案して自社に必要な人材を効率的に確保しよう!

今回は、新卒採用の戦略の見直しが求められている理由や立案のメリット、ポイントについてお伝えしました。採用戦略の策定は、今後の新卒採用を成功させるために欠かせない準備です。
採用フローにおける自社の弱みや改善点を整理し、採用方法を最適化することで自社に必要な人材を効率的に確保しましょう。