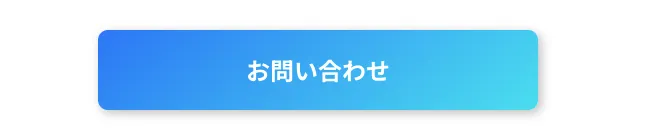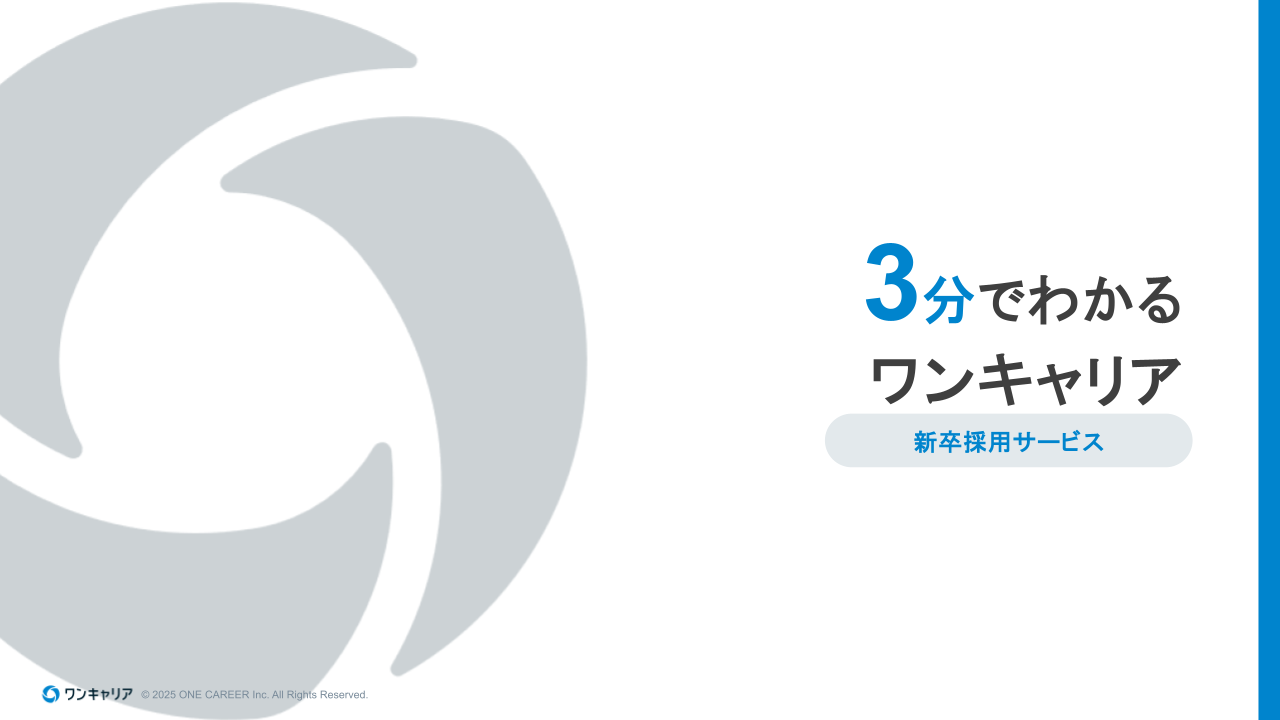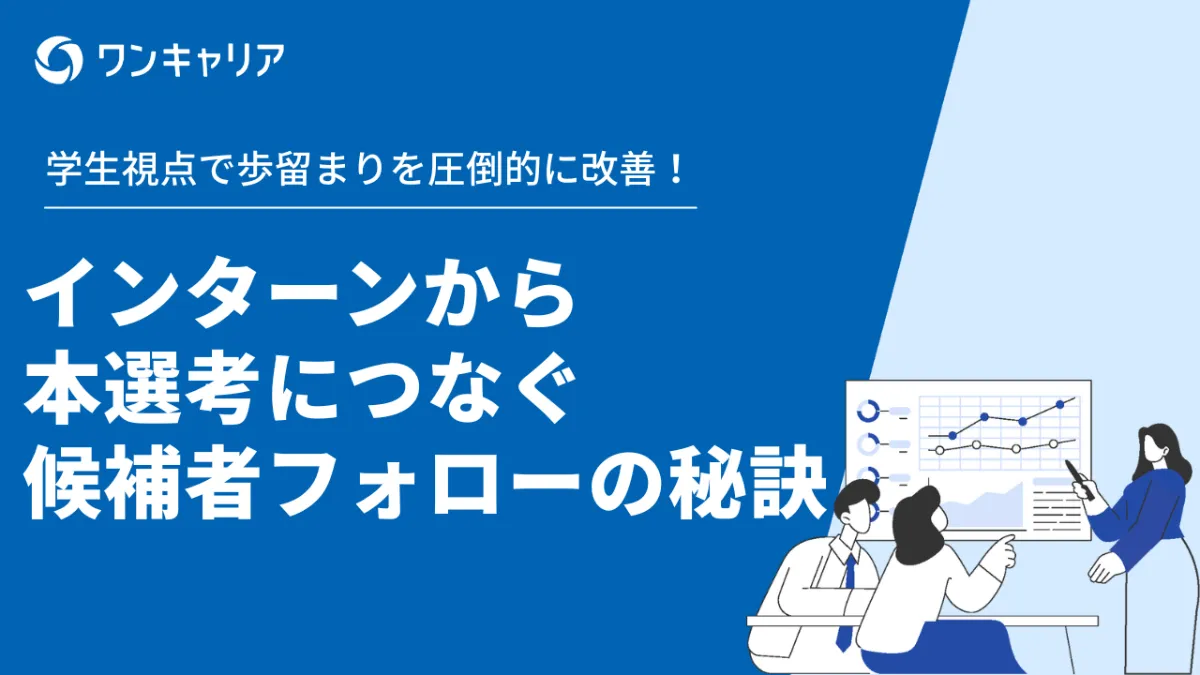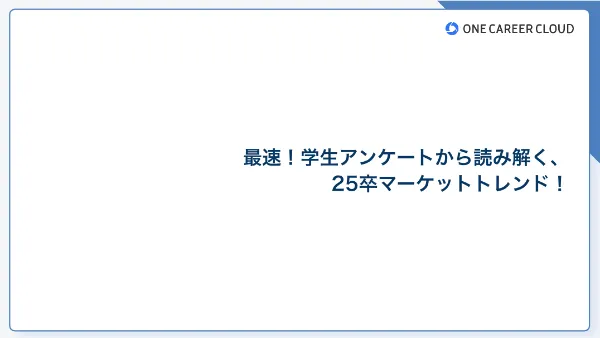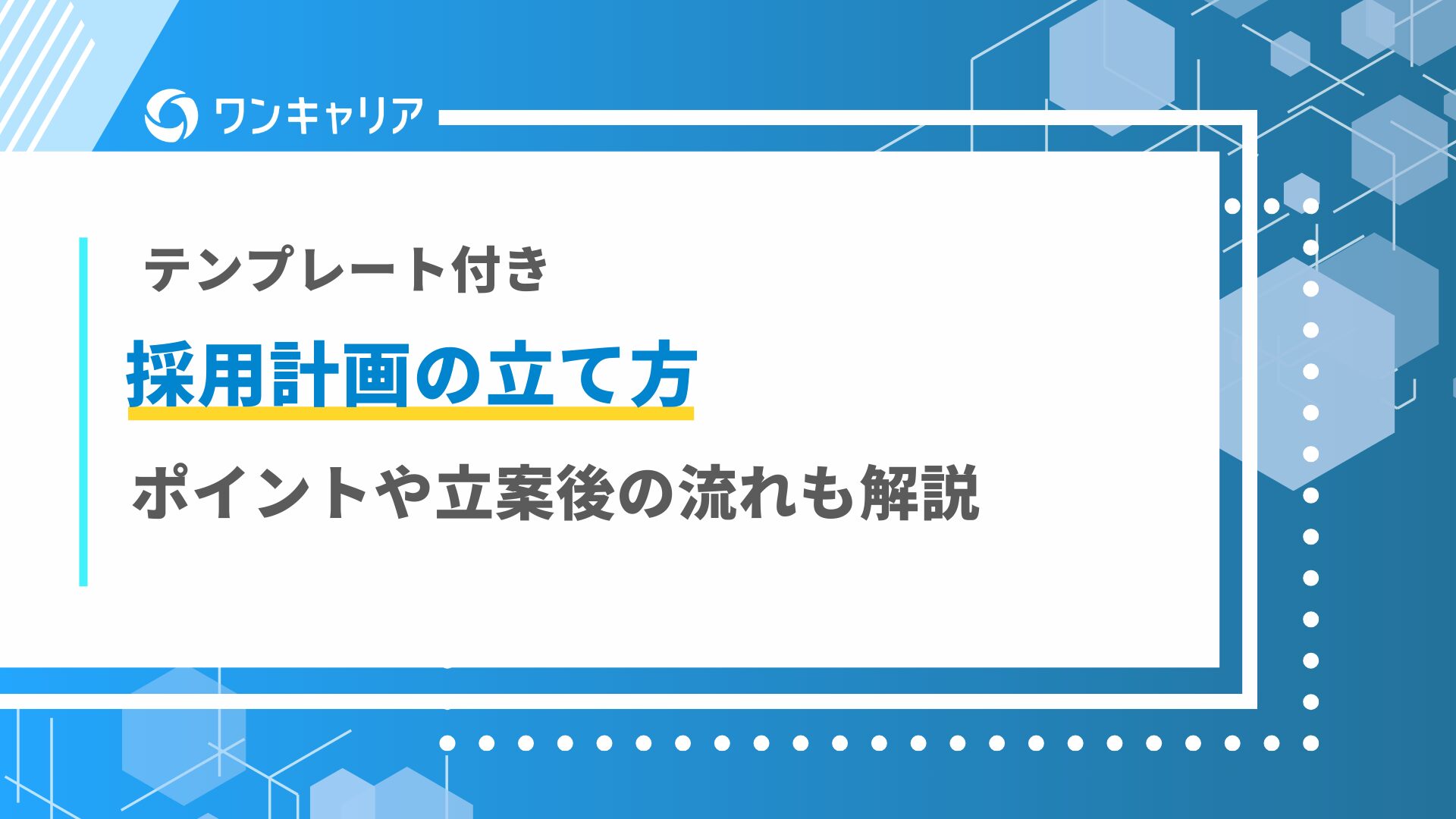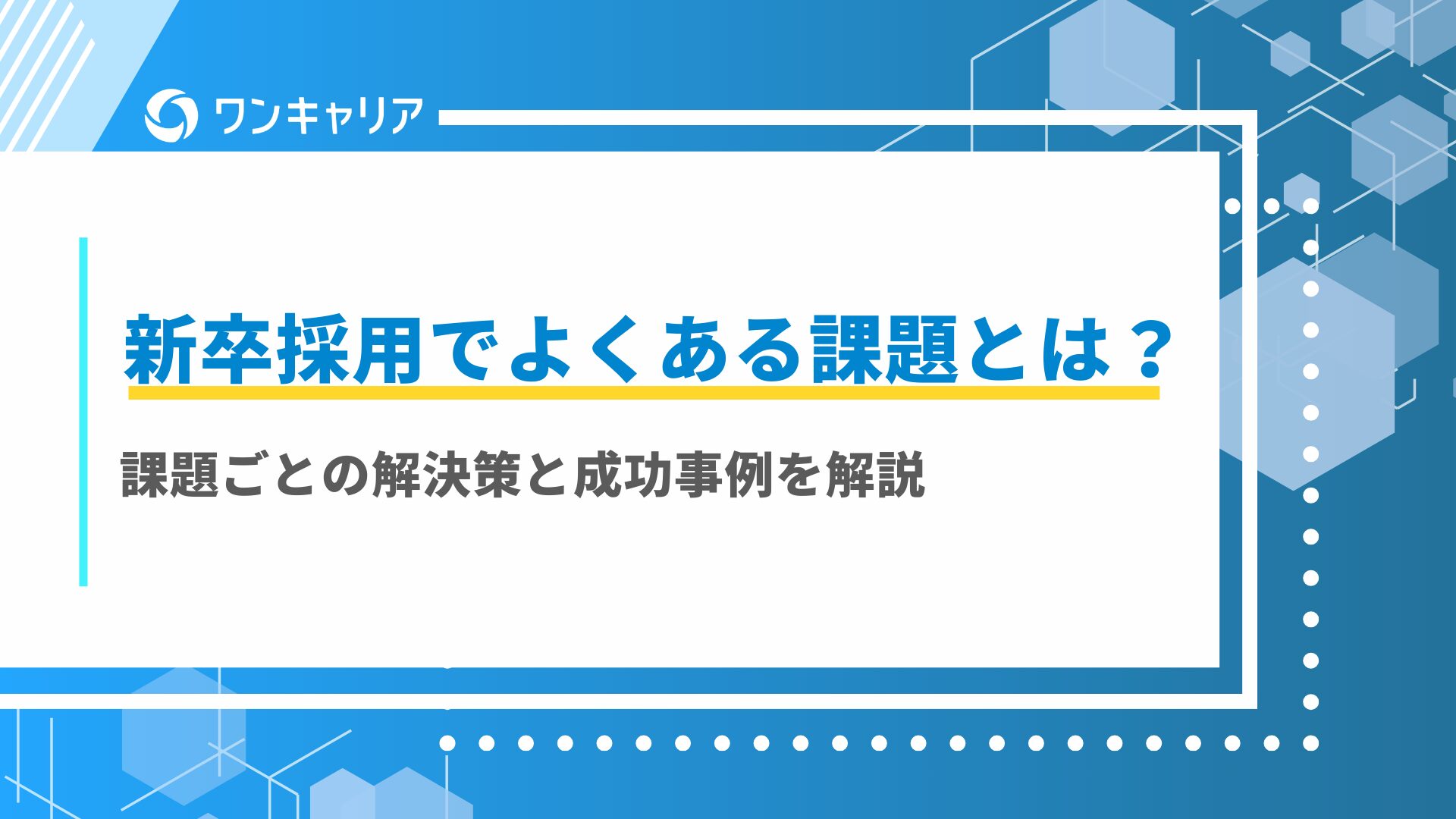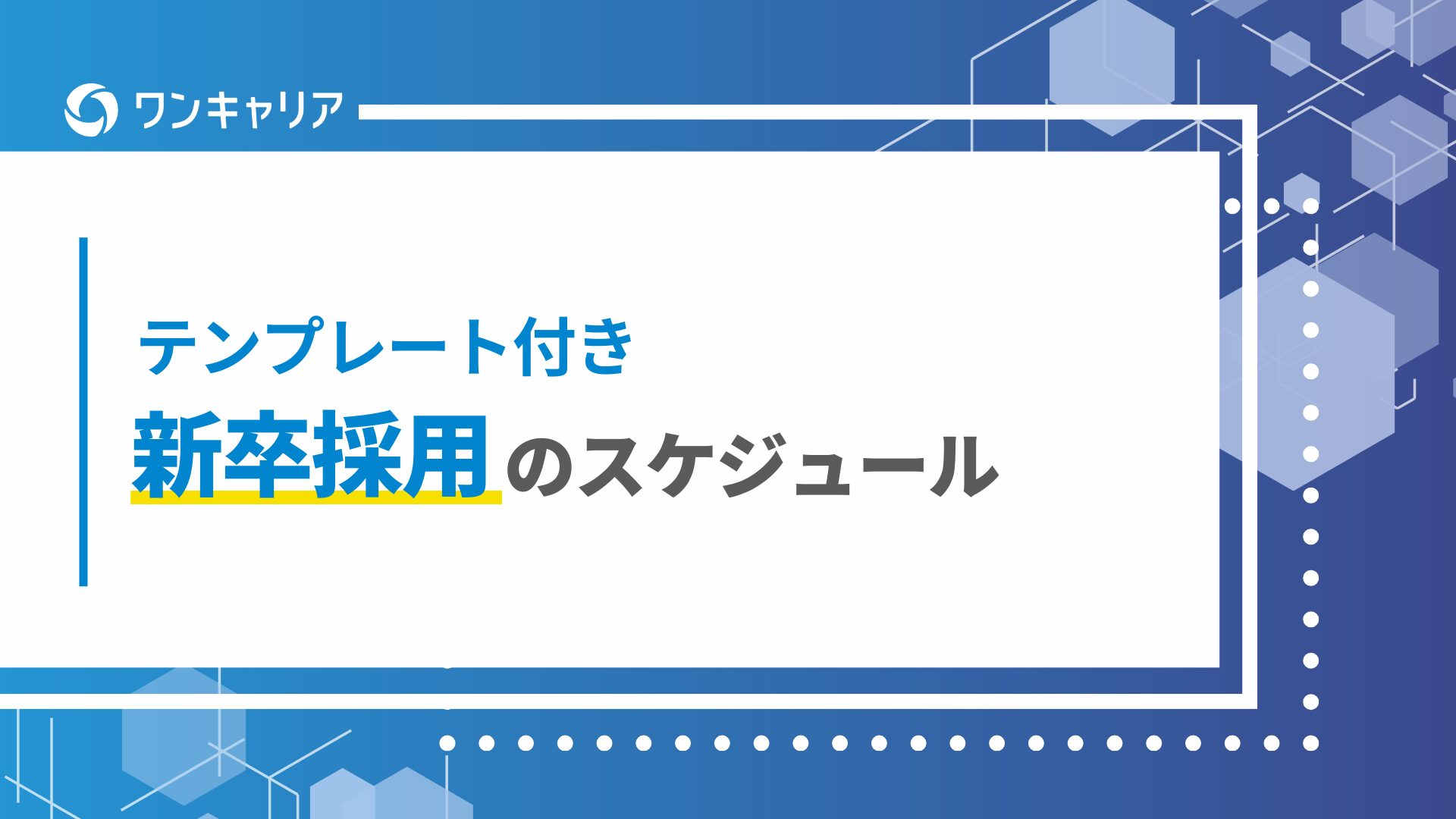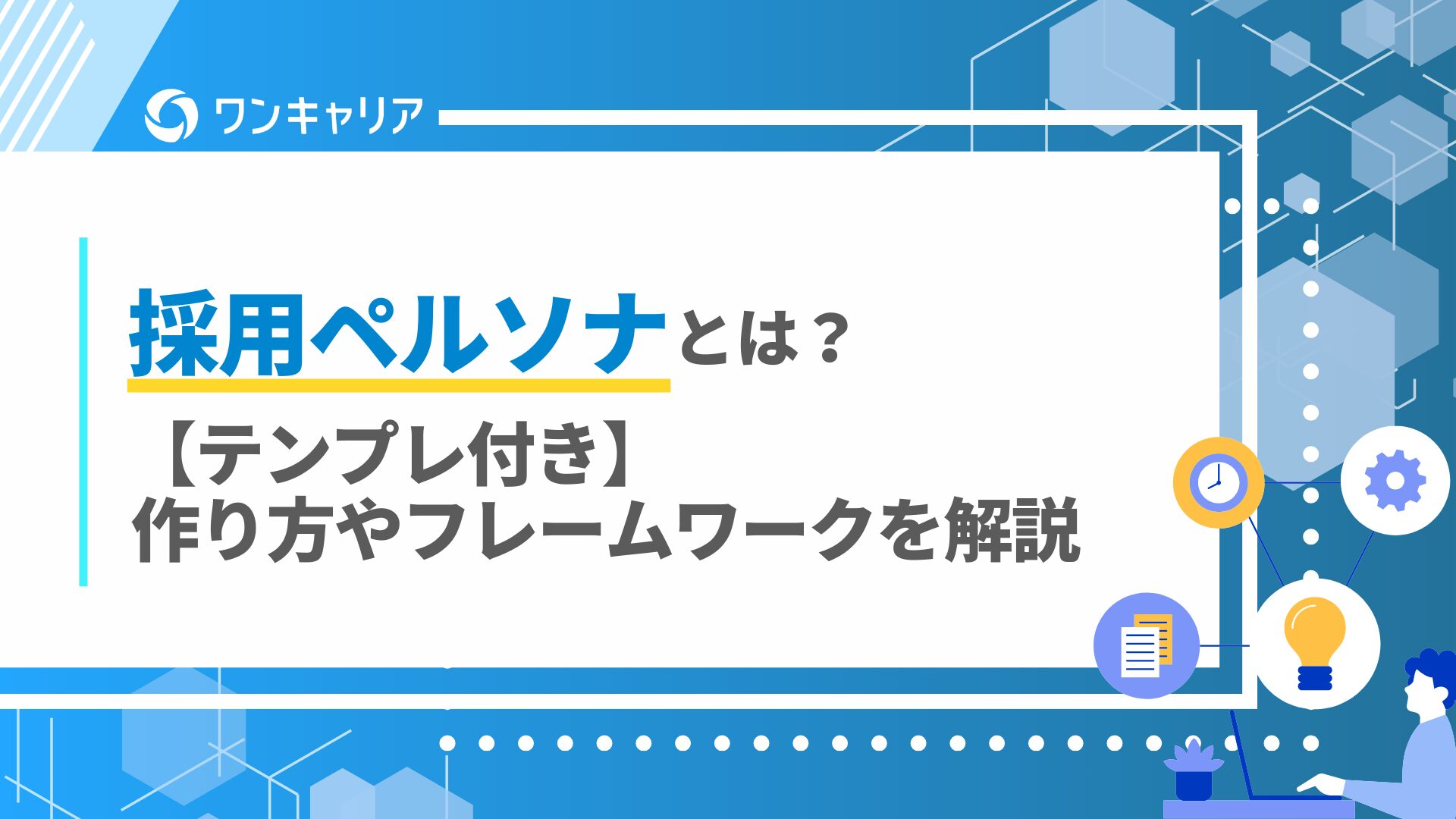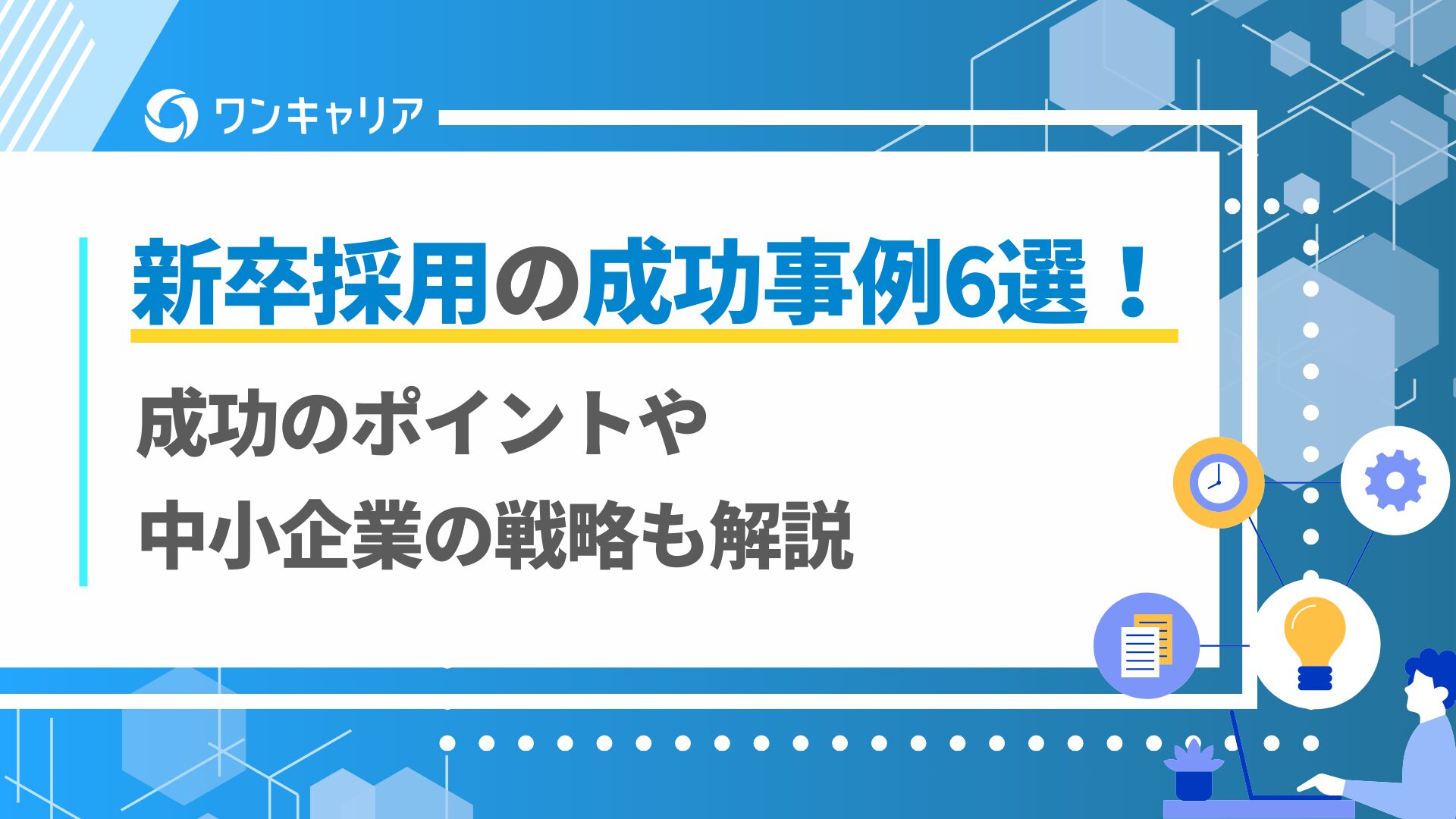目次
新卒社員の離職を防いで社員の定着を図るには、採用活動の段階から理想とのギャップを感じさせる採用のミスマッチを減らすなど、入念な施策が必要です。人材流出は企業にとって痛手となり、既存社員の士気にも影響を与えかねません。この記事では、新卒社員の平均離職率と辞めていく理由、離職率の高さが企業に与える影響を解説し、優秀な社員に長く働いてもらうためのポイントを紹介します。社員の定着率向上に向けてぜひ参考にしてください。
日本の新卒社員の平均離職率と辞める主な理由

高卒や大卒などの新人が入社後3年以内に会社を辞めていく割合はおよそ3割に達します。採用活動を通じてせっかく入社してもらった若者が短期間で辞めていくのは会社にとっての損失であり、改善すべき課題です。まず離職率の定義と計算方法に加え、入社後3年以内の離職率の推移や離職理由について紹介していきます。
離職率の定義と計算方法
離職率は以下の計算式の通り、ある時点で働いていた社員のうち、一定期間内に退職した人の割合を指します。
離職率 = 一定期間内での離職人数 ÷ 起算日の従業員数 × 100(%)
一般的に一定期間内とは期初から期末までの1年間を指し、この間にどれだけの人が辞めたのか、その割合を表します。ただ、離職率の定義は法律で定められているわけではなく、算出目的に応じて分子や分母は変わることになります。
例えば「新卒の入社後3年以内」と期間を定義し、新入社員の定着率を見ることにも使われます。
新卒の入社後3年以内の離職率は?
高校や大学を卒業して就職した人の離職状況について厚生労働省がまとめた調査によると、平成31年3月に新卒入社した人の入社後3年以内の離職率は、新規高校卒就職者が35.9%、新規大学卒就職者が31.5%でした。新卒採用した社員の3割程度は就職してから3年以内に離職しているのです。事業所規模が小さい中小企業ほど離職率は高くなる傾向があります。
・業界別の新卒の離職率
新卒の離職率は業種別、職種別で大きく異なります。厚生労働省がまとめた調査で対象となった17産業(その他を除く)のうち、入社後3年以内の離職率が最も高いのは「宿泊業・飲食サービス業」、逆に最も低いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」でした。
・新卒社員の入社後3年以内離職率の推移
新規学卒者のうち約3割も入社後3年以内に辞めていくと聞くと高い割合だと感じるかもしれません。ただ、これは最近の傾向ではなく、むしろ平成10年代の方が高めに推移していました。たとえば平成12年3月の新規高卒就職者の3年以内離職率は50.3%に達し、新規大学卒就職者は36.5%でした。残業時間の削減や休日取得の促進など、働き方を見直す動きが進んできた結果、離職率はなだらかながら減少傾向にあるのです。
※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001005624.pdf
新卒社員の離職理由とは
新卒社員はどのような理由で早期退職していくのでしょうか。新入社員に限らず入職と離職の推移についてまとめた厚生労働省の令和3年雇用動向調査によると、25歳未満の男女が転職前の仕事を辞めた要因は以下の3項目が上位でした。
「職場の人間関係が好ましくなかった」
「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」
「給料等収入が少なかった」
高校新卒や大学新卒だけを対象にした調査ではありませんが、若者の退職理由はポジティブな内容より、人間関係や労働条件の悪さ、収入の低さといったネガティブな内容の数値が高くなっています。
※出典:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/gaikyou.pdf
新卒社員の離職率の高さが企業に与える影響

新卒社員の離職率の高さが企業に与える影響やリスクを解説します。人材育成に力を入れ、働き方改革も進み、若者もやりがいをもって働ける会社であれば、新人社員が辞めていく理由は大きく減るでしょう。新卒者の離職者数が多い企業は、何かしらの問題を抱えているとみられ、イメージダウンは避けられなくなります。
採用コストや教育研修費が無駄になる
会社が社員を採用するには、求人誌への掲載費や採用管理ツールの使用料、採用担当者の人件費など、さまざまなコストが発生しています。入社後の新人教育コストや福利厚生費なども必要です。新卒社員が早期離職者となると、採用段階から新卒社員にかけてきたコストが無駄になります。離職率の高さは、企業収益や経営体力を低下させることにもつながるのです。
職場から人材が欠けてしまうことで必要になる欠員補充のため、採用に関わる費用や手間が発生することも負担をさらに大きくします。
企業イメージが低下する
さらに離職率低下がマイナスの悪影響となるのは、世間から見た自社の印象を悪化させることです。同業他社と比べて離職率が高い企業の場合、就職活動中の学生から労働条件の悪さを疑われかねません。ワークライフバランスが図られているかどうか、職場の雰囲気は悪くないかといったことへの関心は高いものがあります。企業規模が小さいほど人手不足の影響が大きくなるため、より注意が必要です。
離職率をその判断基準の1つとしている学生もいるため、離職率の高さは応募者確保の妨げとなります。近年は多くの学生がSNSで発信するようになっています。企業の悪い噂も拡散されやすくなっており、イメージダウンにつながる要素には注意したいところです。社内で働く人のモチベーションの低下にもつながりかねません。
新たな人材を採用するまで既存社員の負担が増える
離職率の上昇は、就活生だけでなく、既に働いている労働者にも悪影響を与えます。新たな人材が採用されるまで同僚の穴を埋めなければならず、業務量が増えるからです。人手不足が続く中での欠員補充は簡単ではありません。
少子高齢化で労働者が減少し、売り手市場になっています。人材確保を急ぐ必要から採用業務を担う人事部担当の仕事が増えます。既存社員の業務負担も増え、残業の増加や休日の減少などで労働条件が悪化すれば、さらなる離職につながりかねません。
新卒社員の離職率を低下させる4つの方法

新人の早期退職を避けることは、せっかくの採用活動を無駄にしないため、また、企業イメージのダウンや、既存社員の労働条件悪化を避けるためにも重要になります。ここでは新卒社員の離職率を低下させる方法を紹介します。
仕事内容などのミスマッチを減らす
新卒社員の離職率を下げるには、採用におけるミスマッチを減らす必要があります。仕事内容、労働条件、給与水準などが期待していたものと違ったと新卒社員が認識するほど、落胆が大きく、離職につながる可能性があるからです。
面接時や内定後の説明会など、入社前の時点で求職者とのコミュニケーションをしっかり図り、相互理解を深めることが大切です。入社後の姿について良いイメージだけ伝えるのでは、現実とのギャップが大きくなる可能性があります。具体的に例を示すと、残業が欠かせない多忙な時期もあることや、営業で高いノルマに挑戦するタイミングがありうるなど、仕事の厳しい面もしっかり伝えることが大切です。
伝えるべきデメリットは共有した上で、求職者を見極めてください。採用時は適性検査でストレス耐性や対応力などをチェックするのもおすすめです。組織の特徴や社風に合う人材に入ってもらうため、選考前に求める人物像を明確化してください。
会社のフォロー体制を改善する
会社のフォロー体制を改善することで、若手の離職問題に対応できます。同世代のつながりが多かった学生時代からは変わり、1年目の新卒社員はさまざまな世代が集まる会社に最も若い社員として加わるのです。経験したことがない環境でストレスを感じ、気軽に本音を話せる人がいなくて1人で悩んでいるかもしれません。在宅勤務などのリモートワークに積極的な企業の場合は新入社員が孤立する可能性が高くなるのでより注意が必要です。
そのため、業務面だけでなく精神面で周囲がサポートできるようにすることが大切になります。対策例として考えられるのが、メンター制度の導入です。メンターは、新入社員と入社年の近い先輩社員が候補になります。いわば相談窓口、相談役の立場です。1on1で仕事や働き方の悩みを聞いたり、場合によってはプライベートの相談を受けたりします。このほか業務のサポートもすることで、新人の不安な思いに寄り添ってもらいます。
レクリエーションやイベントの実施も有効です。普段は接することがない他の社員との交流の機会を設けて会社の空気になじみやすくします。業務時間外に行う場合は強制にならないよう、注意してください。
キャリアアップを支援する
働くことへのモチベーションが落ちてきて退職を考えている新人がいる場合には、能力を磨いて経歴を上げるキャリアアップを支援することも有効になります。新人が現状に不満を抱えている場合、上司と面談するなどして短期的な目標設定を一緒に検討していきます。成長を通して自分の将来のキャリアデザインを描きやすくしてあげることで、新入社員が能動的にやりたいことを考えられるようになり、スキルアップにもつながるでしょう。定期的に職場や仕事内容を変えるジョブローテーションも活用できます。
キャリアアップ支援の一環として、適切な人事評価制度とそれに連動した報酬制度を設定するのが有効です。能力を高めてキャリア形成することで得られる待遇や賃金が明確であるほど、社員の意欲向上につながります。
労働時間を是正する
離職防止に労働環境の見直しは欠かせません。特に労働時間の是正は重要です。新卒社員の労働時間を定期的に把握し、長時間労働が常態化するような業務内容や職場環境になっていないか確認してください。若者の退職理由では労働時間や休日などの問題が上位に入っています。残業が多ければ原因を分析し、社員に負荷がかかっているようなら、解消に向けて軽減策を図ることが大切です。ハラスメント禁止の徹底や、通勤時間を減らすテレワークの活用も有効でしょう。
休日出勤が多いなど休暇の取りにくさが不満になっているケースもあります。休暇を取りやすいシステムや職場文化をつくることが大切です。厚生労働省は休暇の取得を促すため、仕事を個人ではなくチームで行うことや、年次有給休暇の計画的付与制度を使うことを推奨しています。管理職のマネジメントスキルが問われる部分です。
離職率を下げるため新卒社員に寄り添った対応を

人手不足が続く中で人材採用競争は激しくなっています。ミスマッチを減らしたり、フォロー制度を充実させたり、労働環境の改善策を実現したりする取り組みは、新卒のみならず既存社員の離職防止にもつながり、重要性は増してくるでしょう。離職防止の取り組みのコツは、プレッシャーを感じている新卒社員に寄り添う対応を図ることです。離職を防ぐ対策に力を入れることで、社員が会社に愛着を抱く従業員エンゲージメントの向上につながる可能性が高まります。社内コミュニケーションを深めることが重要です。
学生と企業側とのミスマッチを防止するには、ダイレクトリクルーティングの活用が有効になります。ダイレクトリクルーティングは、応募を待つ従来の採用手法ではなく、企業が求職者を探して応募を直接呼び掛ける手法です。株式会社ワンキャリアのサービスなら、大学、学部、学科、ゼミ・研究室などの所属情報はもちろん、学生時代の活動実績やスキルで絞り込むことが可能です。就活生の2人に1人が利用しており、幅広い学生にアプローチできます。